マルセロ・ピニェイロ、レトロスペクティブ賞ガラ*マラガ映画祭2024 ⑨ ― 2024年03月18日 17:04
アルゼンチンの監督マルセロ・ピニェイロにレトロスペクティブ賞

★3月8日金曜日、日刊紙マラガ・オイがコラボするレトロスペクティブ賞―マラガ・オイが、アルゼンチンの監督、脚本家、製作者のマルセロ・ピニェイロに与えられました。総合司会者はセリア・ベルメホでした。本賞は映画功労賞の意味合いがありベテラン・シネアストが受賞する賞です。1953年ブエノスアイレス生れのピニェイロは、70歳を超えていますが勿論現役です。プレゼンターは撮影監督のアルフレッド・マヨ、監督で製作者のヘラルド・エレーロ、Netflix ラテンアメリカ担当の副会長フランシスコ・ラモス、俳優のホアキン・フリエル、作家で脚本家のクラウディア・ピニェイロの5名でした。

★プレゼンター各氏の温かい紹介スピーチを会場で聞き入っていた受賞者は、セリア・ベルメホに促されて颯爽と登壇すると、クラウディア・ピニェイロの手からトロフィーを受けとりました。40代で監督デビューした受賞者は、「まず何よりも、私を受賞者に選んでくださったフェスティヴァルに御礼を申し上げたい。以前にこの賞を誰が受賞したか知ったとき、この賞の価値に気づきました。私は多くの素晴らしい人々に支えられて幸運でした、例えば映画や演劇の先生、脚本家、撮影監督、プロデューサー、俳優、私の映画を輝かせてくれた沢山の人々です。皆さんにありがとうを言いたい」と拍手に囲まれながらエモーショナルに締めくくった。

(右端にクラウディア・ピニェイロ)
★当ブログでは2回にわたってキャリア&フィルモグラフィー紹介をしていますが、系統だった記事ではないので補足します。アルゼンチンのラプラタ大学で映画を専攻、1983年、ルイス・プエンソと制作会社シネマニアを設立、アルゼンチンに初めてオスカー像をもたらした『オフィシャル・ストーリー』(85)の製作を手掛けました。アルゼンチン映画アカデミー設立メンバーの一人で副会長に就任している。1993年、「Tango feroz: la leyenda de Tanguito」で監督デビュー、監督第1作に与えられる銀のコンドル賞オペラ・プリマ賞を受賞した。監督デビューが遅かったこともあり、映画作家としては寡作です。しかし評価は高く多くが映画祭や映画賞を受賞している。フィルモグラフィーは以下の通り:
1995年「Caballos salvajes」監督・脚本(共同アイダ・ボルトニク)
サンダンス映画祭1996オナラブルメンション、レリダ映画祭1997観客賞
1997年「Cenizas del paraíso」監督・脚本(共同アイダ・ボルトニク)
ゴヤ賞1998スペイン語外国映画賞、ハバナFF1997脚本賞、レリダFF1998観客賞
2000年「Plata quemada」監督・脚本(共同マルセロ・フィゲラス)
邦題は『炎のレクイエム』『逃走のレクイエム』『燃やされた現ナマ』
ゴヤ賞2001スペイン語外国映画賞、銀のコンドル脚色賞
2001年「Historias de Argentina en Vivo」監督
2002年「Kamchatka」監督・脚本(共同マルセロ・フィゲラス)
カルタヘナ映画祭2003脚本賞、バンクーバーFF2003ポピュラー賞、
ハバナ映画祭2003脚本賞・サンゴ賞3席
2005年「El método」監督・脚本(共同マテオ・ヒル)
ゴヤ賞2006脚本賞、シネマ・ライターズ・サークル賞、フランダース映画祭観客賞
2009年「Las viudas de los jueves」監督・脚本(共同マルセロ・フィゲラス)
『木曜日の未亡人』DVDタイトル
2013年「Ismael」監督・脚本(共同マルセロ・フィゲラス、ベロニカ・フェルナンデス)
2021~23年「El reino」TVシリーズ、監督・脚本(共同クラウディア・ピニェイロ)
邦題『彼の王国』Netflix配信、銀のコンドル2022オリジナル脚本賞、
イベロアメリカ・プラチナ賞2022 TVミニシリーズ部門作品賞
★クラウディア・ピニェイロとは、彼女のベストセラー小説 “Las viudas de los jueves”(2005年刊)を映画化した。公開には至らなかったが『木曜日の未亡人』(09)の邦題で2010年DVD化された。最近ではTVミニシリーズ「El reino」(8話)の共同執筆者でもあり、また今回のマラガ映画祭セクション・オフシアルの審査委員長を務めている。また本シリーズには主演男優賞を受賞したホアキン・フリエルが重要な役どころで出演している。アップが受賞結果と前後したので3月8日段階では 分からなかったが、監督お気に入りのようです。

(監督と脚本家クラウディア・ピニェイロ)

(ヘラルド・エレーロ、監督、ホアキン・フリエル)
★アルフレッド・マヨは「Caballos salvajes」「Cenizas del paraíso」「Plata quemada」「Kamchatka」「El método」とヒット作を手掛けているスペインの撮影監督です。マドリード出身のヘラルド・エレーロは監督と同じ1953年生れ、スペインだけでなく多くのラテンアメリカの監督とタッグを組んでいる。ピニェイロとは、「Plata quemada」や「El método」を製作している。
*「El método」の作品紹介は、コチラ⇒2013年12月19日
*『逃走のレクイエム』の作品紹介は、コチラ⇒2022年06月16日
第68回バジャドリード映画祭2023*結果発表 ― 2023年11月25日 19:05
新星ラウラ・フェレスのデビュー作「La imatge permanent」に金の穂

★10月28日、バジャドリード映画祭がバルセロナ出身のラウラ・フェレスの長編デビュー作「La imatge permanent」を金賞(Espiga de Oro)に選んで閉幕しました。スペインが初めて受賞したのは2007年のヘラルド・オリバレス監督の「14 kilómetros」にも驚きますが、今回が68回目という長い歴史のある映画祭で「女性監督の受賞は初めて」の記事に感慨深いものがありました。作品&監督キャリア紹介は後述しますが、1989年にバルセロナのエル・プラット・デ・リョブレガット生れの34歳、監督、脚本家です。その若さにも驚きましたが、予告編を見ただけでもそのエネルギーとユニークさに引きこまれました。キャストはおおむね本作が初出演というからそれも楽しみ、演技賞はさておき少し荒削りの感もありますが、ゴヤ賞新人監督賞ノミネートは間違いないと予想します。

(金の穂賞のトロフィーを手にしたラウラ・フェレス、10月28日ガラ)
★バジャドリード映画祭は、今年で68回目というスペインでも老舗の国際映画祭です。1956年Semana del Cine Religioso de Valladolid(バジャドリード宗教映画週間)としてスタート、その後名称が何回か変わり、1973年Semana Internacional de Cineとなり現在に至っています。バジャドリード映画祭よりSEMINCIの名で親しまれていますが、SeminciでなくSem-In -Ciに拘る人々もいるわけです。本祭のディレクターは今年からセビーリャ映画祭の総ディレクターだったホセ・ルイス・シエンフエゴスに変わり、彼が初めて統率する映画祭でもありました。本祭はレッドカーペットでなくグリーンカーペットの映画祭としても知られています。

(ホセ・ルイス・シエンフエゴス新ディレクターの祝福を受けるラウラ・フェレス)
★国際映画祭ですが、スペイン映画関係の受賞者をピックアップしますと、栄誉賞にブランカ・ポルティリョ、彼女はパウラ・オルティスの「Teresa」でテレサ・デ・ヘススに扮しフォルケ賞2024女優賞にノミネートされており、本祭でもアウト・オブ・コンペティションですが上映されました。同じフォルケ賞でノミネートされているマレナ・アルテリオ主演の「Que nadie duerma」(監督アントニオ・メンデス・エスパルサ)もコンペティション部門で上映されており、フォルケ賞も作品賞以上に混戦が予想されます。

(栄誉賞のトロフィーを手にしたブランカ・ポルティリョ)

「La imatge permanent」
(西題「La imagen permanente」英題「The Permanent Picture」)
製作:Fasten Films(スペイン)/ Le Bureau(フランス)/ ICAA / ICEC / TV3
/ Volta Producción
監督:ラウラ・フェレス
脚本(共同):ラウラ・フェレス、カルロス・ベルムト、ウリセス・ポッラ
撮影:アグネス・ピケ・コルベラ
編集:アイナ・カジェハ
音響:ダニ・フォントロドナ
音楽:フェルナンド・モレシ・ハベルマン、セルヒオ・ベルトラン
製作者:アドリア・モネス・ムルランス、ガブリエル・ドゥモン、ガブリエル・カプラン、他
データ:製作国スペイン=フランス、2023年、スペイン語・カタルーニャ語、ドラマ、94分、長編デビュー作、撮影地エル・プラット・デ・リョブレガット(バルセロナ、監督の生地)、配給La Aventura(スペイン)、公開スペイン11月17日
映画祭・受賞歴:ロカルノ映画祭2023コンペティション部門でプレミア(8月6日)、ケンブリッジ映画祭(10月22日)、テッサロニキ映画祭(11月9日)、第68回バジャドリード映画祭コンペティション部門、作品賞を受賞。
ストーリー:スペイン南部の片田舎で暮らしていた10代の母親アントニアは、赤ん坊を残して真夜中に出奔する。50年後、はるか彼方の北の町では、引っ込み思案のキャスティング・ディレクターのカルメンが、次のプロジェクトのためのヒロイン探しに逡巡していたとき、偶然アントニアと出会います。新しい街に越してきて共通の繋がりを発見するという女性に出会ったとき、その衝動性がカルメンの孤独に侵入してきます。映画は20世紀のアンダルシアで始まり、現在のバルセロナで繰り広げられる。「時間がすべての傷を癒してくれると誰が言いましたか?」これはスペイン内戦後、アンダルシアからカタルーニャに移住してきた人々の歌や物語の一部です。自分の経験を共有してくれる人を探す物語。

アンダルシアからカタルーニャに移住してきた人々のルーツを探る
★長編デビュー作「La imatge permanent」は、アンダルシア出身の監督の母方の祖母にインスパイアされた作品で、ディアスポラの不安を探求している。自身の家族史のなかにフィクションを滑りこませ、キャスティング・ディレクターとしての自身の過去を、スペイン内戦後にアンダルシアの田舎から北の都会に移住してきた家族の伝承として掘り下げる。農村から都市への切り替えの影響を受けている人々への頌歌、それが理解できない世間知らずの為政者への風刺、監督は「憂鬱なコメディ」と称している。内向的なカルメンには監督が投影されている。監督は「この映画の最も重要な要素の一つは時間です」と、時間がテーマの一つのようです。「批評家週間」のネクスト・ステップ・イニシアチブ、トリノ・フィルム・ラボの支援を受け、マラガ映画祭のワーク・イン・プログレスプロジェクトに選ばれていました。


★ラウラ・フェレスは、1989年生れ、監督、脚本家。バルセロナのESCAC(カタルーニャ映画視聴覚上級学校)卒、最終課程で制作した「A perro flaco」(14)がバジャドリード映画祭スペイン短編の夕べ部門にノミネート、他にモントリオール映画祭2015などで上映された。2017年、カンヌ映画祭併催の「批評家週間」短編部門にドキュメンタリー「Los desheredados」(18分、The Disinherited)がノミネート、ライカ・シネ・ディスカバリー賞を受賞、後にSeminciでも上映され、翌年のゴヤ賞2018短編ドキュメンタリー映画部門で製作者のバレリー・デルピエールと受賞した。ガウディ賞は短編賞、ポルトガルのビラ・ド・コンデ短編映画祭のヨーロピアン短編賞、アルカラ・デ・エナレス短編映画祭では脚本賞、父親のペレ・フェレスが男優賞を受賞するなどした。本短編はドキュメンタリーとフィクションを行ったり来たりするような手法で父親の会社の倒産を描いている。ゴヤ賞ガラには父親と出席した。金の穂受賞作には俳優として出演している。

(父親ペレ・フェレスと監督、ゴヤ賞2018ガラ)
★第11回フェロス賞2024のノミネーションが発表になっています。2年連続でサラゴサ開催でしたが、マドリードに戻って、1月26日開催です。
ビクトル・エリセにドノスティア栄誉賞*サンセバスチャン映画祭2023 ⑫ ― 2023年09月02日 16:27
二人目の受賞者がビクトル・エリセにびっくり

★8月22日、第71回サンセバスチャン映画祭事務局は、二人目のドノスティア栄誉賞受賞者がビクトル・エリセ(ビスカヤ県カランサ1940)監督とアナウンスしました。一人目が5月12日に発表された俳優のハビエル・バルデム、第71回の顔になっています。順序が逆のような印象を受けますが、SSIFFの栄誉賞受賞者の公式サイトには、エリセ、バルデムの順になっており、先輩エリセに敬意をはらったようです。
*ハビエル・バルデムのドノスティア栄誉賞受賞記事は、コチラ⇒2023年06月09日
★授賞式は9月29日、メイン会場クルサールではなく、最新作「Cerrar los ojos / Close Your Eyes」(スペイン=アルゼンチン合作)が上映されるビクトリア・エウヘニア劇場、50年前に長編デビュー作『ミツバチのささやき』(73)が上映された劇場です。本作はSSIFFの金貝賞受賞作品、2003年には『ミツバチのささやき』金貝賞受賞30周年記念上映会が開催されています。プレゼンターは撮影時7歳だったアナ・トレント、長編4作目となる新作にも出演しています。本祭上映後に、スペインでは一般公開が確定しています。

(左から、製作者エリアス・ケレヘタ、アナ・トレント、姉役イサベル・テリェリア、
エリセ監督、サンセバスチャン映画祭2003年)
★1986年に新設されたドノスティア栄誉賞は、第1回に俳優グレゴリー・ペックを選出、以来演技者の受賞者が続き監督にも光があたるようになったのは、アグネス・ヴァルダ(17)、是枝裕和(18)、コスタ・ガブラス(19)、クローネンバーグ(22)など最近のことです。エリセで受賞者はトータル69人となり、スペイン人の受賞者は今回の2人を含めて7人です。フェルナンド・フェルナン=ゴメス(99)、パコ・ラバル(01)、アントニオ・バンデラス(08)、カルメン・マウラ(13)、ペネロペ・クルス(19)、ハビエル・バルデム、監督一筋の受賞者はビクトル・エリセが初めてでしょう。
★授賞理由は書くまでもないのか公式のコメントはありませんし、当ブログでも監督キャリア&フィルモグラフィーは「Cerrar los ojos」で最近アップしたばかり、カンヌ映画祭2023欠席の経緯も紹介済みです。以下の写真は、3つのエピソードで構成されたオムニバス「Los desafíos」(DVD邦題『挑戦』)がサンセバスチャン映画祭1969の監督賞を受賞したときの、エリセ他、ホセ・ルイス・エヘア、クラウディオ・ゲリンの新人3人です。今は亡き大物プロデューサーであったエリアス・ケレヘタのお眼鏡にかなった3人です。4年後にエリセは『ミツバチのささやき』で金貝賞に輝いたことは上述の通りです。

(エリセ、ホセ・ルイス・エヘア、クラウディオ・ゲリン、
本祭の招待客宿泊ホテルである、マリア・クリスティナ、1969年)
*「Cerrar los ojos」の撮影予告、短編の紹介記事は、コチラ⇒2022年07月15日
* 全フィルモグラフィーの紹介記事は、コチラ⇒2022年07月25日
*「Cerrar los ojos」内容紹介記事は、コチラ⇒2023年04月29日
*カンヌ映画祭2023レッドカーペット欠席のニュースは、コチラ⇒2023年05月25日
*「カンヌ映画祭欠席についての公開書簡」の記事は、コチラ⇒2023年05月30日
エレナ・マルティンの2作目が「監督週間」にノミネート*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月22日 13:50
スペインのエレナ・マルティンの第2作「Creatura」が監督週間に

★今年第55回を迎える「監督週間」にスペインのエレナ・マルティンの「Creatura」がノミネートされました。「監督週間」と「批評家週間」はカンヌ映画祭とは選考母体も異なりますが、本体と同期間にカンヌで開催されることからカンヌFFと称しています。今回は本体より1日遅れの5月17日から26日まで、従って結果発表も先になります。長編部門は60分以上、短編部門は60分未満という区別があり、SACD賞、ヨーロッパ・シネマズ賞、観客賞などがあります。

(最近のエレナ・マルティン)
「Creatura」
製作:Avalon PC / Elástica Films / Filmin / S/B Films / Vilauto Films / ICEC / ICAA / Lastro Media / TV3
監督:エレナ・マルティン
脚本:エレナ・マルティン、クララ・ロケ
音楽:クララ・アギラル
撮影:アラナ・メヒア・ゴンサレス
編集:アリアドナ・リバス
キャスティング:イレネ・ロケ
プロダクション・デザイン&美術:シルビア・ステインブレヒト
音響:レオ・ドルガン、ライア・カサノバス、オリオル・ドナト
衣装デザイン:ベラ・モレス
メイクアップ&ヘアー:ダナエ・ガテル(メイク)、アレクサンドラ・サルバ(ヘアー)
製作者:(Vilauto Films)アリアドナ・ドット、マルタ・クルアーニャス、トノ・フォルゲラ、(Elástica Films)マリア・サモラ、(Avalon PC)シュテファン・シュミッツ、(S/B Films)パウ・スリス、ジェイク・チーサムCheetham、他多数
データ:製作国スペイン、2023年、カタルーニャ語、ドラマ、112分、撮影地バルセロナのサンビセンツ・デ・モンタルト、公開スペイン2023年9月18日予定、国際販売LuxBox
映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭併催の「監督週間」にノミネート(5月20日上映)
キャスト:ミラ・ボラス(ミラ5歳)、クラウディア・ダルマウ(ミラ15歳)、エレナ・マルティン(ミラ35歳)、アレックス・ブランデミュール(父ジェラルド)、マルク・カルタニャ(ジェラルド)、クリスティーナ・コロム(大人のアイナ)、カルラ・リナレス(ディアナ)、オリオル・プラ(ミラの恋人マルセル)、ベルナ・ロケ(アンドレ)、クララ・セグラ(ディアナ)、テレサ・バリクロサ、ダビ・ベルト
ストーリー:少女のミラはビーチで夏を過ごします。彼女の大好きな父親は彼女に優しく世界を見せます。母親は控えめです。少女から急成長するミラのエネルギーは、彼女の周囲、彼女の体、海との繋がりを変えてしまいます。大人たちは自意識の高いミラの変化に戸惑いを感じます。ミラと父親のあいだで何かが壊れます。30代になったミラは、深刻な危機に向き合っています。ミラは自分の欲望と喪失が心の奥底にあることに気づき始めます。過去の関係を再訪する自己探求の旅をしていますが、再び海に戻ることができるでしょうか。

(思春期のミラ)
★監督紹介:エレナ・マルティン・ヒメノは、1992年バルセロナ生れ、監督、脚本家、映画・舞台女優。ポンペウ・ファブラ大学(1990年設立)で映画を学ぶ。長編デビュー作は主役も自身で演じた2017年の「Júlia ist」、マラガ映画祭2017のZonaZine 部門の作品・監督・モビスター+賞を受賞、他トゥリア第1作監督賞も受賞、バレンシア映画祭、翌年のガウディ賞(カタルーニャ語以外部門)の作品賞にノミネートされている他、ワルシャワFF、レイキャビクFFに出品された。本作については簡単ですが作品紹介をしています。
*「Júlia ist」の作品紹介は、コチラ⇒2017年07月10日

(エレナ・マルティン、「Júlia ist」から)

★エレナ・マルティンは、女優としてスタートしました。2015年のライア・アラバルト他4人の共同監督作品「Les amigues de l’Ágata」(Las amigas de Ágata)のアガタ役で好演し、名前が知られるようになった。2019年イレネ・モライの短編「Suc de síndria」(20分、英題「Watermelon Juice」)に主演し、マラガFF、メディナFF、イベロアメリカンFFなどで主演女優賞を受賞している。モライ監督はゴヤ賞2020の短編映画賞以下、ガウディ賞、メディナFF、バレンシアFF、イベロアメリカン短編映画賞など多数受賞しています。

★TVシリーズでは、2019年、レティシア・ドレラが創案者のコメディ「Vida perfecta」(14話、19~20)に参加、2話を監督している。5話からなるTVミニシリーズ「En casa」(1話、20)、ミュージック・ビデオ「Rigoberta Bandeni:Perra」を監督している。他にロス・ハビス(ハビエル・アンブロシ、ハビエル・カルボ)のシリーズ「Veneno」(全8話)のスタッフライターとして6話にコミット、脚本2話を執筆している。
フェリペ・ガルベスのデビュー作が「ある視点」に*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月15日 11:36
「ある視点」にフェリペ・ガルベスのデビュー作「Los colonos」がノミネート

★チリのフェリペ・ガルベスのデビュー作「Los colonos」が「ある視点」に正式出品、チリ、アルゼンチン、オランダ、フランス、デンマークなど8ヵ国との合作、ガルベス監督は1983年チリのサンティアゴ生れ、監督、脚本家、フィルム編集者。「ある視点」ノミネートは2011年のクリスティアン・ヒメネスの「Bonsai」以来12年ぶりです。本作は東京国際映画祭2011ワールド・シネマ部門で『Bonsai~盆栽』としてアジアン・プレミアされた。「Los colonos」の舞台は20世紀初頭のチリ南端ティエラ・デル・フエゴ島、先住民族セルクナム(またはオナス)のジェノサイドをテーマにした歴史物、彼らがチリの正史から消されてきた過程を探求している。
「Los colonos / Les colons / The Settlers」(仮題「入植者たち」)
製作:Quijote Films(チリ)、Rei Cine(アルゼンチン)、Quiddity Films(英)、Volos Films(台湾)、共同製作:Cine Sud Promotion(仏)、Snowglobe(デンマーク)、Film I Vast(スウェーデン)、Sutor Kolonko(独)
監督:フェリペ・ガルベス
脚本:フェリペ・ガルベス、アントニア・ヒラルディ
音楽:Harry Allouche
撮影:Simone D’Arcangelo
編集:Mattieu Taponier
プロダクション・デザイン:セバスティアン・オルガンビデ
衣装デザイン:ナタリア・アラヨン、ムリエル・パラ
メイクアップ&ヘアー:ダミアン・ブリッシオ
製作者:ジャンカルロ・ナシ、ステファノ・センティニ、ベンジャミン・ドメネク、サンティアゴ・ガレッリ、エミリー・モーガン、マティアス・ロベダ、ティエリー・ルヌーベル、(エグゼクティブ)コンスタンサ・エレンチュン、エイミー・ガードナー、ほか共同製作者多数
データ:製作国アルゼンチン、チリ、イギリス、台湾、ドイツ、スウェーデン、フランス、デンマーク、スペイン語・英語、2023年、歴史ドラマ、97分
映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2023「ある視点」部門正式出品、初長編監督作品賞カメラドールにもノミネートされている。
キャスト:カミロ・アランシビア(メスティーソのセグンド)、ベンジャミン・ウェストフォール(アメリカ人傭兵ビル)、マーク・スタンリー(イギリス人マクレナン中尉)、サム・スプルエル(マルティン大佐)、アルフレッド・カストロ(スペイン人地主ホセ・メネンデス)、マリアノ・リナス(フランシスコ・モレノ)、ルイス・マチン(司教)、マルセロ・アロンソ(大統領勅使ビクーニャ)、アグスティン・リッタノ(アンブロシオ大佐)、ミシェル・グアーニャ(キエプジャ)、アドリアナ・ストゥベン(ホセフィナ・メネンデス)、ほか
ストーリー:19世紀末に羊牧場はチリのパタゴニア地方の領土を拡大していきました。1901年、裕福な地主ホセ・メネンデスは先住民の土地を開拓し、大西洋への道を開くために3人の男を雇いました。最終的な目的は当時の白人の使命に従って、この広大で肥沃な領土を文明化することでした。メスティーソのセグンド、元ボーア戦争のイギリス人船長のマクレナン、アメリカ人傭兵ビルの3人は、国家がメネンデスに与えた土地の境界を定める遠征に乗り出していった。最初は行政上の遠征のように見えたものが、次第に先住民に対する暴力的な狩猟へと変質していった。1901年から1908年のあいだにティエラ・デル・フエゴ島での先住民セルクナム虐殺を描き、先住民が被った植民地化、暴力、不正義というテーマを探求しています。



★ガルベス監督談によると「誰が歴史を書くのか、どのように書かれるのか、その過程で映画の立ち位置はどのように占めるのかを考えさせてくれる」映画だとコメント。チリの正史から消されてきた先住民虐殺の事実が、如何にして闇に葬られてきたのか、その過程がどうして可能だったのか、メネンデス一家がどのように資金調達をしたのかが語られる。「この映画は、内なる旅とその登場人物の精神の崩壊を通して、強制的に文明化されたモデルを反映させた」とプレスリリースで語っている。チリが建国(1818年)100周年を迎えようとしていた頃の過去にさかのぼり、現在にまで及ぶ理念が語られる。

★監督紹介:フェリペ・ガルベス(Felipe Galvez Haberle)、1983年サンティアゴ生れ、監督、脚本家、フィルム編集。2008年フィルム編集者としてキャリアをスタートさせる。2009年の短編「Silencio en la sala」(12分)がBaficiブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭に正式出品されベスト短編賞を受賞。2018年「Rapaz」(13分)がカンヌ映画祭併催の「批評家週間」にノミネートされたことで、その後ウルグアイ映画祭2018、ダウンタウン・ロスアンゼルスFF、ノーステキサスFF、ダラスFF2019のグランプリを受賞、バレンシアFFのCinema Joveにノミネートされた。本作は携帯電話の盗難で告発された十代の少年の市民拘留を描いている。フィルム編集ではクラウディオ・マルコネの「En la Gama de los Grises」(15)、マルティン・ロドリゲス・レドンドのデビュー作「Marilyn」(18)など受賞歴のある映画を多数手掛けている。
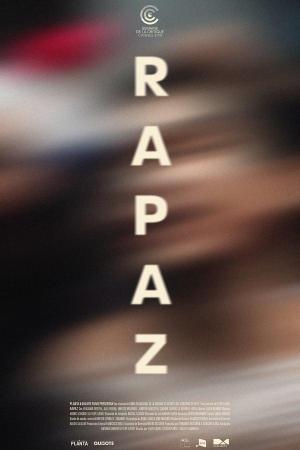
(短編「Rapaz」のポスター)
★カンヌFF2000「ある視点」にノミネートされたミゲル・リティンの「Tierra del Fuego」は、ティエラ・デル・フエゴを舞台にしている。セルクナム虐殺をリードした一人であるルーマニア人ジュリアス・ポッパーを主人公にしたクロニカである。他に先住民ジェノサイドに言及している作品にパトリシオ・グスマンのドキュメンタリー「El botón de nácar」(15)があり、この作品は『真珠のボタン』の邦題で公開されています。
*監督作品は以下の通り:
2009年「Silencio en la sala」短編12分、監督、脚本、編集
2011年「Yo de aqui te estoy mirande」短編、監督、脚本、編集
2018年「Rapaz」短編13分、監督、脚本、編集
2023年「Los colonos」長編デビュー作、監督、脚本
*「Marilyn」の作品紹介は、コチラ⇒2018年02月25日
*『真珠のボタン』の作品紹介は、コチラ⇒2015年11月16日
*追加情報:本作は『開拓者たち』の邦題で、東京国際映画祭2023にノミネートされた。
「ある視点」にロドリゴ・モレノの犯罪コメディ*カンヌ映画祭2023 ― 2023年05月11日 15:09
アルゼンチンから自由と冒険を求める犯罪コメディ「Los delincuentes」

★「ある視点」部門にはスペインはノミネートなし、アルゼンチン、チリなどラテンアメリカ諸国が気を吐いている。アルゼンチンのニューシネマの一人ロドリゴ・モレノの長編4作目「Los delincuentes」(アルゼンチン、ブラジル、ルクセンブルク、チリ)は、ブエノスアイレスに支店をおく銀行の従業員2人が勤務先で強盗を計画するというコメディ仕立ての犯罪もの、彼らの運命は如何に。モレノ監督はドキュメンタリーや共同監督作品を含めると10作近くなる。なかで単独監督デビュー作の「El custodio」は、ベルリン映画祭2006でアルフレッド・バウアー賞を受賞、サンセバスチャン映画祭、マイアミ、グアダラハラ、ハバナなど国際映画祭の受賞歴は30以上に上りました。フィルモグラフィー紹介は後述するとして、新作のデータ紹介から始めます。
「Los delincuentes」(英題「The Delinquents」)
製作:(アルゼンチン)Wanka Cine / Rizona Films / Jaque Producciones / Compañia Amateur /(ブラジル)Sancho &Punta /(ルクセンブルク)Les Films Fauves /(チリ)Jirafa films 協賛INCAA
監督・脚本:ロドリゴ・モレノ
撮影:イネス・ドゥアカステージャ、アレホ・マグリオ
編集:カレン・アケルマン、ニコラス・ゴールドバート、ロドリゴ・モレノ
プロダクション・デザイン・美術:ゴンサロ・デルガド、ラウラ・カリギウリCaligiuri
衣装デザイン:フローラ・カリギウリ
音響:ロベルト・エスピノサ
製作者:エセキエル・ボロヴィンスキー(エグゼクティブ)、エセキエル・カパルド(プロダクション・マネジャー)、レナタ・ファルチェト(ヘッド)、フロレンシア・ゴルバクスGorbacz、Eugenia Molina、マティアス・リベラ・バシレ(アシスタント)、(以下ルクセンブルク)Jean-Michel Huet、Yahia Sekkil、Manon Santarelli、Alexis Schmitz
データ:製作国アルゼンチン、ブラジル、ルクセンブルク、チリ、2023年、スペイン語、コメディ、90分、撮影地ブエノスアイレス、コルドバの山地、期間2022年3月末~6月、配給マグノリア・ピクチャーズ・インターナショナル
映画祭・受賞歴:カンヌ映画祭2023「ある視点」正式出品、シドニー映画祭(6月)
キャスト:エステバン・ビリャルディ(ロマン)、ハビエル・ソロ(モラン)、マルガリータ・モルフィノ(モランの恋人ノルマ)、ダニエル・エリアス、セシリア・ライネロ(モルナ)、ヘルマン・デ・シルバ、ラウラ・パレデス、ガブリエラ・サイドン(ロマンの妻フロール)、セルヒオ・エルナンデス、他
ストーリー:ロマンとモランは、ブエノスアイレスに小規模な支店をおく銀行の従業員です。二人は自由と冒険を探しています。モランは日ごとに彼らを灰色の人生に陥れるルーチンを振りはらうというそれだけの意図で、同僚と共謀して大胆な計画を実行することにします。彼らが定年まで稼ぐ給料に相当する金額を銀行から前もって頂くことにしました。どういうわけか彼の強盗計画は成功し、自分の運命を同僚ロマンの運命に委ねます。まず全額を彼に預け、その後土地を探すつもりでコルドバに逃れます。旅先で出会った女性ノルマに無分別にも夢中になります。彼女は姉と山地の分譲地販売をしている彼氏と同居している。数日間一緒に過ごし、必ず戻ってくるが、3年間待ってくれと頼みこむ。ノルマにはすべてが馬鹿げているとしか思えない。一方ロマンは銀行で働きつづけていますが、折悪しくお金の不足についての内部調査が始まりました。非常に多額のお金を隠しているロマンは恐怖に襲われます。同僚たちだけでなく妻フローラにも隠さねばなりません。計画を変更したらいいのでしょうか・・・

(混乱する銀行支店、左から3人目ヘルマン・デ・シルバ)


★モレノ監督によると「モランは犯罪を犯して代価を支払うとしても、解放感を得るために危険な計画を考案する。共犯者のロマンも働かずに義務から解放され自由のなかでより良い生活、つまり都会、仕事、家族から離れ、海とか山とかレジャーが楽しめる田舎暮らしを誰にも依存せずに送りたい。しかし夢を達成するには、どうやって生計を立てるかという実存的な障害が立ちはだかる」。じゃあ目標を追求するにはどうしますか、というお話です。モランの計画は刑務所暮らしも想定内なのです。



★監督紹介:ロドリゴ・モレノ、1972年ブエノスアイレス生れ、監督、脚本家、製作者、ブエノスアイレスのシネ大学の監督プログラムを卒業、独創的なストーリーテリングを目指すアルゼンチンの若い世代のグループの一人です。1993年短編「Nosotros」(8分)で監督デビュー、ビルバオ・ドキュメンタリー短編映画祭で作品賞を受賞する。2012年制作会社「Compañia Amateur」を設立し、「Reimon」以降を製作している。脚本を執筆したルシア・メンドサの「Diarios de Mendoza」、コロンビアのフアン・セバスティアン・ケブラダの「Días extraños」を製作している。フアン・ビジェガスとMoVi cineを共有している。主なフィルモグラフィーは以下の通り:
1993年「Nosotros」短編(8分)、監督、脚本
1998年「Mala época」監督、脚本、マリアノ・デ・ロサ、ほか4名の共同作品
(マル・デル・プラタ、トリノ、シカゴ、サンセバスチャン、他)
2002年「El descanso」監督、脚本、ウリセス・ロセル、アンドレス・タンボルニーノ、
3名の共同作品(Bafici*、ロンドン、ベネチア、トゥールーズ)
2006年「El custodio」単独長編デビュー作、監督、脚本
(ベルリン、サンセバスチャン、マイアミ、ニューヨーク、グアダラハラ、ハバナ)
2007年「La señal」TV Movie、監督、脚本
2011年「Un mundo misterioso」第2作、監督、脚本
(ベルリン、トロント、サンパウロ、Bafici)
2014年「Reimon」第3作、監督、脚本、製作、72分
(ロッテルダム、ハンブルク、Bafici、サンパウロ、バルでビア)
2017年「Una ciudad de provincia」ドキュメンタリー、監督、脚本、製作、88分、IBAFF
(ロッテルダム、ビエンナーレ、Bafici)
2018年「Our Nighttime Story」ドキュメンタリー、監督、フアン・ビジェガス、
ほか3名の共同作品
2023年「Los delincuentes」第4作、監督、脚本
2014年、ルシア・メンドサの「Diarios de Mendoza」(55分)脚本、製作
2015年、フアン・セバスティアン・ケブラダの「Días extraños」(70分)脚本、製作
*Baficiは、1999年設立されたブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭

(ロドリゴ・モレノ)
★上述したように1993年に短編「Nosotros」でスタートした。オムニバス長編「Mala época」は、4名の共同作品ですが、マル・デル・プラタ映画祭1998で、若い映画製作者の視点で現代を切り取ったことが評価されてFIPRESCI賞とスペシャルメンションを受賞、その他トゥールーズ・ラテンアメリカ映画祭1999で観客賞を受賞、ノミネート多数。共同監督作品「El descanso」は、リェイダ・ラテンアメリカFFでICCI脚本賞を受賞した。

★ベルリン映画祭でアルフレッド・バウアー賞を受賞して国際的な評価を受けたのは、単独で監督したデビュー作「El custodio」だが、本作は前年のサンダンスFFに出品されラテンアメリカ部門のNHK賞を受賞している。その他ボゴタFFで作品賞、監督賞、サンセバスチャンFFホライズンズ・ラティノ部門でスペシャルメンションを受賞している。


(アルフレッド・バウアー賞のトロフィーを披露する監督)
★5月10日「ある視点」の審査団が発表になりました。審査委員長は俳優、コメディアンのジョン・C・ライリー、ほか俳優パウラ・ベーア、俳優エミリー・ドゥケンヌ、監督デイヴィー・チョウ、監督アリス・ウィノクールの5名です。
追加情報:邦題『ロス・デリンクエンテス』で2024年3月公開されました。
アグスティ・ビリャロンガ逝く*闇と光の世界を生きる ― 2023年04月14日 18:39
映画への情熱を手引きした郵便配達人の父親

★去る1月22日の明け方、アグスティ・ビリャロンガが突然別れを告げました。カタルーニャ映画アカデミーは「今朝、映画監督のアグスティ・ビリャロンガは、私たちをバルセロナに残して、愛する家族や友人に見守られて旅立ちました。彼の才能、感性、豊かな愛に満ちた包容力、そして数々の映画は永遠に残るでしょう」と報じた。彼が人生の最後の2年間闘ってきた癌は、スペインの支配的な傾向に逆らって、ユニークな作品を作り続けた、この並外れた映画人を連れ去りました。1週間の緩和ケアの後、バルセロナで69歳の生涯を閉じたということですから、突然ではなかったわけです。当ブログで紹介した「El ventre del mar」がマラガ映画祭2021で作品賞以下6冠を制したときには、既に闘病中だったことになります。
★訃報のアップは本当に気が重い。特に彼のように早すぎる死は猶更です。ガウディ賞の受賞者としてバルセロナ派を牽引してきただけにその死は惜しまれてなりません。ガウディ賞は毎年アップしていたわけではありませんが、今年は気が滅入ってアップする気になれませんでした。なにしろ旅立ちは、第15回ガウディ賞授賞式の当日でした。ガラはビリャロンガ逝くの追悼式のようだったということでした。因みに受賞結果は、発表を待つまでもなく作品賞はカタルーニャ語部門がカルラ・シモンの「Alcarràs」、カタルーニャ語以外の部門はゴヤ賞ではノミネートさえされなかったアルベルト・セラの『パシフィクション』と、下馬評通りの結果でした。

(在りし日のビリャロンガ、サンセバスチャン映画祭2010)
★ビリャロンガと言えば、カタルーニャ語映画が初めてゴヤ賞を受賞した「Pa negre」(2010「Pan negro」)でしょうか。本作はラテンビート映画祭2011で上映され、翌年『ブラック・ブレッド』の邦題で公開されました。ゴヤ賞では作品賞を含めて9部門を制覇、彼自身も監督賞と脚本賞の2冠、ガウディ賞は13冠とほぼ総なめ状態でした。その他サンジョルディ賞、トゥリア賞、フォトグラマス・デ・プラタ賞、アリエル賞(イベロアメリカ部門)作品賞などを受賞しています。
*まだ当ブログは存在しておらず、目下休眠中のCabinaさんブログに、テーマ、監督キャリア&キャスト紹介などをコメントとして投稿しています。(コチラ⇒2011年03月03日)

(受賞スピーチをするビリャロンガ、監督・脚本賞を受賞したゴヤ賞2011から)
★1953年3月4日、パルマ・デ・マジョルカ生れ、監督、脚本家、俳優。スペイン内戦時に15歳で戦線に引きずり込まれた父親から映画への情熱を植え付けられた。カタルーニャの操り人形師の家系に生まれた父親は、後にパルマに定住して郵便配達員として働いていた。彼は映画に情熱を注ぎ息子アグスティを映画の世界に導きました。父親の影響を受けた息子はデッサン、マッチ箱、懐中電灯を使って手作りの映写機を作ったほど映画に熱中した。
★監督が「El ventre del mar」のプロモーションの過程で語ったところによると、「14歳で映画監督になる決心をして、ローマの映画学校のロベルト・ロッセリーニに手紙を書いた。彼の学校に本当に入りたかったのです。しかし若すぎるという理由で拒否されました」。彼らはまず大学を卒業すべきだと返事してきた。イエズス会の中学校を終了していた十代のアグスティはやや失望しパルマを出ることにした。バルセロナ自治大学で美術史を専攻して学位を取り、その後バルセロナの公立舞台芸術学校である演劇研究所 Institut del Teatre に入学、舞台美術を学んだ。当時を振り返って「今は彼(ロッセリーニ)の映画はあまり好きではありません。若いころには理解できなかったパゾリーニに情熱を注いでいます」と、またイングマール・ベルイマン映画にも言及し、彼は「私に多くの足跡を残した」と同じインタビューに答えている。

(「El ventre del mar」のカタルーニャ語版ポスター)
俳優としてキャリアをスタートさせた―ヌリア・エスペルトとの出会い
★キャリアをスタートさせて間もなく、ビクトル・ガルシアと出会い、女優で演出家のヌリア・エスペルトが設立した劇団に俳優として入る。ガルシア・ロルカの『イェルマ』ツアーに参加、ヨーロッパ、アメリカを巡業する。帰国後映画俳優としてホセ・ラモン・ララスの「El fin de la inocencia」(77)、フアン・ホセ・ポルトの「El último guateque」(78)、ホセ・アントニオ・デ・ラ・ロマの「Perros callejeros II」(79)などに出演する。しかし1982年、製作者のぺポン・コロミナスが彼を監督業に引き戻した。というのも彼は既に短編3作を撮っていたのである。
★そして誕生したのが、長編デビュー作「Tras el cristal」(86、110分)である。ギュンター・マイスナー、マリサ・パレデス、ダビ・スストを起用したホラー・サスペンス。ベルリン映画祭で上映され、ムルシア・スペイン映画週間で初監督に与えられるオペラ・プリマ賞を受賞、ほかサンジョルディ賞1988のオペラ・プリマ賞も受賞した。第2作となるSFファンタジー「El niño de la runa」はカンヌ映画祭1989コンペティション部門にノミネートされ、翌年のゴヤ賞オリジナル脚本賞を受賞、監督賞にノミネートされた。キャストはマリベル・マルティンやルチア・ボゼーのようなベテラン女優を軸に、前作出演のギュンター・マイスナーやダビ・スストを起用している。本邦では1992年『月の子ども』の邦題で公開された。

(公開された『月の子ども』のポスター)
★メルセ・ロドレダの小説 “La mort de primavera” の映画化を模索したが、製作者を見つけることができなかった。1997年、マリア・バランコを主役に据え、テレレ・パベスやルス・ガブリエルで脇を固めたホラー「99.9」は、モントリオール、トロント、ローマ、各映画祭で上映されシッチェス映画祭に正式出品された。撮影を手がけたハビエル・アギレサロベが撮影賞、彼はヨーロッパ・ファンタジー映画に贈られる銀のメリエス賞を受賞した。続いて現れたのが同性愛をテーマにした「El mar」(邦題『海へ還る日』)である。カタルーニャ語を採用、生れ故郷マジョルカで撮られた本作はベルリン映画祭2000に出品され、新しく設けられた独立系映画に与えられるマンフレッド・ザルツベルガー賞を受賞して、認知度は国際的になった。ザルツベルガーはテディ賞生みの親の一人、20世紀ドイツのLGBT運動の推進者である。本作で映画デビューした、後の『ブラック・ブレッド』や「El ventre del mar」に出演したロジェール・カザマジョールとの出会いがあった。
*「El mar」の作品紹介、ロジェール・カザマジョールのフィルモグラフィー&キャリア紹介は、コチラ⇒2021年06月24日
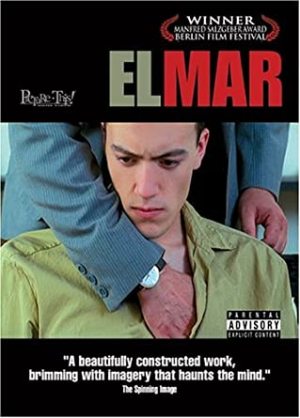
(カザマジョールを配した『海へ還る日』のポスター)
★2002年、サンセバスチャン映画祭を驚かせた「Aro Tolbukhin (en la mente del asesino)」(メキシコとの合作)は、メキシカン・ヌーベルバーグと称された偽造ドキュメンタリーである。アイザック=ピエール・ラシネ、リディア・ジマーマンとの共同監督、翌年のアリエル賞を作品賞以下全カテゴリーにノミネートされるも作品賞には及ばなかった。しかし脚本賞を含む7冠を制し、時間の経過とともにファンを増やしていった。ハンガリーの船乗りで連続殺人犯アロ・トロブキンがグアテマラに逃亡し捕らえられ銃殺刑になるまでを描き、彼の犯罪の背後にある「殺人者の心のなか」の闇に迫った。実際のドキュメンタリー映像を広範囲に使用しているが、これはドラマであってドキュメンタリーではない。本作は後にラテンビート映画祭に統一された第1回「ヒスパニックビート2004」に、『アロ・トルブキン―殺人の記憶』として上映されている。
『ブラック・ブレッド』がルールを変えた
★海外での評価と人気はあってもスペイン全体に届いたとは言えなかった。彼はしばらく映画を離れカタルーニャTV映画「Després de la pluja」(07「After the Rain」)やTVシリーズのドキュメンタリーを手がけている。何作か映画製作を模索していたが、いずれも財政的な支援が得られなかったようだ。2010年、一部の批判的な評価を覆した『ブラック・ブレッド』(フランスとの合作)が到着した。
★本作はエミリ・テシドール(1932~2012)の同名小説 “Pa negre” を軸に、彼の2冊の小説をベースにして映画化されたダークミステリーである。内戦後のカタルーニャの小さな町に起きた不可解な事件を軸に、1940年代を生きた少年アンドレウに焦点を当て、真実を求める過程で過去の亡霊に出会うなかで自分のセクシュアリティに目覚める。少年は嘘と欺瞞に満ちた大人たちを許すことなくモンスターに変貌していく。マドリード派が優勢なゴヤ賞も14部門ノミネート、作品賞を含む9冠に輝いた。ゴヤ賞2011年のライバル作品は、ロドリゴ・コルテスの『リミット』、イシアル・ボリャインの『ザ・ウォーター・ウォー』、アレックス・デ・ラ・イグレシアの『気狂いピエロの決闘』と誰が受賞してもおかしくない豊作の年、いずれも公開されている。ガウディ賞は13冠、プレミアされたサンセバスチャン映画祭では、少年の母親に扮したノラ・ナバスが女優賞を受賞した。

(少年アンドレウを配したオリジナル・ポスター)

(左から、アグスティ・ビリャロンガ、ロドリゴ・コルテス、イシアル・ボリャイン、
アレックス・デ・ラ・イグレシア、ゴヤ賞2011ノミネートの4監督)
★サンセバスチャン映画祭2012でプレミアされたTVミニシリーズ「Carta a Eva」(2話)を製作、翌年放映された。アルゼンチンのエバ・ペロンのヨーロッパ・ツアーをめぐるドラマである。エバにはアルゼンチンのフリエタ・カルディナルが主演、フランコ総統にヘスス・カステジョン、ほかアナ・トレント、カルメン・マウラ、ノラ・ナバスなどスペインサイドが出演している。2015年の「El rey de La Habana」は、ラテンビート2015で『ザ・キング・オブ・ハバナ』の邦題で上映された折、当ブログで作品紹介をしています。ペドロ・フアン・グティエレスの不穏な同名小説の映画化。亡命することなくキューバに止まり、故国の悲惨を弾劾しつづけている作家、詩人、ジャーナリスト、。
*『ザ・キング・オブ・ハバナ』の原作者&作品紹介は、
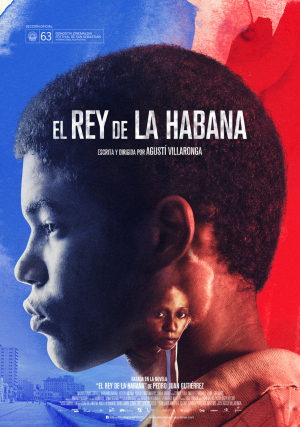
★中編ドキュメンタリー「El testament de la Rosa」(16、仮題「ロザの遺言」45分)は、女優ロザ・ノベル(バルセロナ1953-2015)が癌で亡くなる直前をカメラに収めたドキュメンタリー。既に視力を失っていた女優の最後の作品(コルム・トビンの「El testament de la Maria」)になるであろう舞台リハーサルをモノクロで追っている。結果的には亡くなってしまったのでブランカ・ポルテーリョが演じた。本作には監督自身と『海へ還る日』や『ブラック・ブレッド』の製作者イソナ・パッソラ、脚本家エドゥアルド・メンドサ、テレビでの活躍が多い女優フランセスカ・ピニョンが出演している。バジャドリード映画祭2016でプレミアされた。

(ブランカ・ポルテーリョと監督)
★2017年、時代背景を1937年のスペイン内戦中のアラゴン戦線にした「Incerta glòria」は、ジョアン・サレスの同名小説の映画化、ゴヤ賞では脚色賞に共同執筆のコラル・クルスとノミネート、ガウディ賞はキャスト陣、技術部門のスタッフにトロフィーを多数もたらしたが、監督自身は無冠に終わった。2019年にはアンドレス・ビセンテ・ゴメスがプロデュースした「Nacido rey」(言語は英語「Born a King」)が公開された。サウジアラビアの偉大な君主として知られるファイサル国王(1906~75)のビオピックである。監督は「私は映画が大好きで、お金目当てではありません。本作はアラブ諸国で撮影されましたが、経済的なもの以外の魅力も加えました。本題に無関係な話を差し挟むような依頼は受けておりません」と語っている。
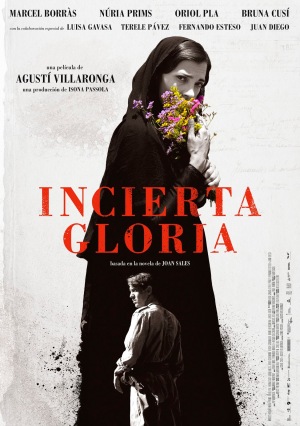
★2021年の「El ventre del mar」がマラガ映画祭2021に正式出品され、上述したように金のビスナガ作品賞を含む6冠を制した(金のビスナガ作品賞・監督・脚本・撮影・音楽・男優賞)。作品紹介は簡単ですがアップ済みです。イタリアの作家アレッサンドロ・バリッコが実話に基づいて書いた小説 ”Océano mar” にインスパイアーされて製作されている。本作に「20年間取りくんできた」ということです。遺作となったスシ・サンチェスを主役に起用したコメディ「Loli Tormenta」(23)は、先月末に公開された。本作については別個に紹介したい。
*「El ventre del mar」の作品紹介、マラガFFガ授賞式の様子は、

(銀のビスナガ監督賞を受賞、マラガFF2021 授賞式)
★生涯を通じて演技者としても活躍していたが、最後の作品はルーマニアのコルネリュ・ポルンボイュの「La gomera」出演で、冷徹なマフィアに扮した。ルーマニア、フランス、ドイツなどの合作映画だが、原題の「ラ・ゴメラ」はカナリア諸島の島名から採られている。カンヌ映画祭2019に出品され、今回は演技者としてカンヌを訪れた。2021年に『ホイッスラーズ 誓いの口笛』の邦題でWOWOWで放映され、プライムビデオでも配信されている。
★変わり者が多いスペインでも独特の作風をもつ監督として駆け抜けたビリャロンガですが、晩年「私のスタイルにとても近い人を見つけることはできませんが、今日では私は変わり者 bicho raro ではないと思います。ただ自分にできることをするだけです」と、フィルモグラフィーを振り返って語っている。彼は比較的早い段階で性的マイノリティを公表していたが、こどものときから「人と違うこと」に敏感だった。その内なる世界は『ブラック・ブレッド』の少年アンドレウや『海へ還る日』の青年に投影されている。
◎上記以外の受賞歴
2001年、カタルーニャ自治州の文化省が選考母体のカタルーニャ映画国民賞を受賞した。前年に国際的な活躍をした人に贈られる賞、映画のほか文学・音楽など各分野から原則1年に1人選ばれる。彼の場合は2000年の『海へ還る日』の成功によるものと思われる。
2011年、スペイン文化省が選考母体の映画国民賞を受賞、2010年の『ブラック・ブレッド』が評価されたことによる。
2012年、ゲイ-レスボ映画と舞台芸術国際フェスティバル栄誉賞、カタルーニャ・ラテンアメリカ映画祭ジョルディ・ダウダ賞などを受賞した。
2021年12月1日、芸術功労金のメダルを受賞、国王フェリペ6世、レティシア王妃列席のもと授与された。

(左から一人おいて、国王フェリペ6世、王妃レティシア、ビリャロンガ、
背後に控えているのがミケル・イセタ教育・文化・スポーツ大臣)
グティエレス・アラゴン審査委員長インタビュー*マラガ映画祭2023 ⑬ ― 2023年03月31日 18:19
ベルリン映画祭で幸運なスタートをきる
★マラガ映画祭の「審査委員長にマヌエル・グティエレス・アラゴン監督」のアナウンスには、スペイン映画のオールドファンの一人として驚きを隠せなかった。民主主義移行期から1980年代を通して、多くの名作が本邦にもたらされ、若手ながら批評家の評価は高かったが、突然の引退表明から大分時が経っていたからでした。2008年製作の「Todos estamos invitados」(銀のビスナガ審査員特別賞受賞作)を最後に60代での引退はいかにも早すぎ、いずれ撤回するに違いないと思っておりましたが、TVシリーズはあっても長編映画を撮ることはありませんでした。インタビューの前段として監督キャリア&フィルモグラフィーをアップします。

(フリックスオレのインタビューを受けるグティエレス・アラゴン、マラガFF2023)
★マヌエル・グティエレス・アラゴン、1942年カンタブリア州トレラベガ生れの監督は81歳、ゴヤ賞ガラの前日に鬼籍入りしたカルロス・サウラの次の世代に当たります。ホセ・ルイス・ボラウの『密漁者たち』やハイメ・カミーノの『1936年の長い休暇』に監督とシナリオを共同執筆した名脚本家としての評価も高い。マドリード大学で哲学と文学を学ぶかたわら、1947年設立の国立映画研究所(IIEC)を1962年に組織替えした国立映画学校(EOC)に入学、監督を学び、卒業制作「Hansel y Gretel」(ヘンゼルとグレーテル)を撮る。短編数編を撮ったのち、1973年エリアス・ケレヘタの製作によってデビュー作「Habla, mudita」が誕生した。当時の大物プロデューサーだったケレヘタとの出会いが幸運だった。
★長編第1作がベルリン映画祭に正式出品されるという幸運に恵まれただけでなく、いきなり「芸術文学科学の普及国際委員会賞」という批評家賞を受賞してしまった。非常に早い段階で成功がもたらされたことになります。本作はスペイン映画が初めて23本まとまったかたちで紹介された「スペイン映画の史的展望〈1951~1977〉」(1984年10月~11月、東京国立近代美術館フィルムセンター)で『話してごらん』の邦題で上映された。彼はルイス・ブニュエル以下20名の監督のなかで一番の若手でした。この映画祭終了後1週間おいて渋谷東急名画座で開催された「第1回スペイン映画祭」では、1982年製作の6作目「Demonios en el jardín」が『庭の悪魔』の邦題でエントリーされた。駆け出しの監督が10年間に6作というのは、当時としては驚異的な数字でした。1986年のカルロス・サウラの映画特集に続いて、翌年「アラゴン映画特集」というミニ映画祭が開催され、以下の6作が上映された。

(『庭の悪魔』のポスター)
1977年「Camada negra」2作目、邦題『黒の軍団』ベルリン映画祭1978監督銀熊賞受賞
1977年「Sonámbulos」3作目、同『夢遊病者』サンセバスチャン映画祭1978監督銀貝賞受賞
1978年「El corazón del bosque」4作目、『森の中心』ベルリンFF 1979正式出品
1980年「Maravillas」5作目『マラビーリャス』シカゴ映画祭1981銀のヒューゴー賞受賞、
サンジョルディ賞1982受賞、フォトグラマス・デ・プラタ1982など受賞
1982年「Demonios en el jardín」6作目、『庭の悪魔』サンセバスチャンFF FIPRESCI賞、
フォトグラマス・デ・プラタ1983、イタリアのドナテッロ(ルネ・クレール賞)、
モスクワ映画祭1983 FIPRESCI 賞などを受賞
1984年「Feroz」『激しい』カンヌ映画祭「ある視点」正式出品
★ミニ映画祭とはいえ、若手監督の映画特集は異例のことでしたが劇場公開には至りませんでした。サンセバスチャンFFで金貝賞を受賞した9作目「La mitad del cielo」(86)が『天国の半分』の邦題で初めて公開されたのは、1990年の年末でした。本作ではアラゴン監督のお気に入り女優アンヘラ・モリーナが女優賞(銀貝)を受賞している。スペイン内戦後のマドリードを舞台にした本作は、「第2回スペイン映画祭1989」の1本でした。監督の故郷カンタブリアの州都サンタンデール出身の女性がマドリードに出て、二人の姉や成功を妬む人の密告などに苦労しながらも予知能力のある祖母の霊に守られてレストラン経営で成功する話だが、日本の観客に受け入れられたかどうか。
★1998年、スペイン大使館主催、国際交流基金後援の「スペイン映画祭’98」(会場シネ・ヴィヴァン・六本木)は本当に力作ぞろいの7作品でした。うちアラゴンはキューバの俳優とスタッフを起用した「Cosas que dejé en la Habana」(97)がエントリーされ、『ハバナから来た娘』で上映された。監督がキューバに拘るのは、祖父と父親がキューバ生れのクリオーリョということがあるようです。より良い人生を築くため祖国を離れてマドリードに移住してきた3人の娘たちの誇りと郷愁が描かれた。
★公開作品は上記『天国の半分』1作だけだが、キューバを舞台にした「Una rosa de Francia」(06)が、2009年に『カリブの白い薔薇』でDVDが発売された他、フェルナンド・レイとアルフレッド・ランダ主演の『ドン・キホーテ』(1991年版)がNHK衛星第2で放映された。10年後2002年に再びフアン・ルイス・ガリアルドとカルロス・イグレシアス主演のコンビで製作されたものは、前作のレベルには到達しなかったと評された。これは2015年5月にインスティトゥト・セルバンテス東京で英語字幕入りで上映されている。
「検閲は私たちを萎縮させ、苛立ちを引き起こした」と監督
★以下の記事は、マラガ映画祭期間中に監督とFlixOlé*とのインタビューを簡単に要約したものです。まだ結果発表前に行われたインタビューなので、ノミネートされた個別の作品についての言及はありません。( )内は管理人が追加したものです。
Q: 審査委員長を引き受けた経緯についての質問。
A: 去年も打診がありましたがお断りしました。忘れてくれることを期待しましたが、やはり今年も要請がありましたので、やるしかないと引き受けました。私は何度もマラガに来ており、審査員になることでスペインとラテンアメリカ両方の映画を楽しんでいます。
Q: 今年の映画の一般的なレベルについての質問。
A: まだ審査前ですから、お話しすることはできません。しかし、ラテンアメリカ映画は多様で感銘を受けています。私たちが知らない不思議な世界を描いていて、訛りがとても魅力的なのです。今年のスペイン映画の質も高く、人々の関心を高めています。審査はラクではありませんが、有意義な時間を過ごしています。
Q: デビュー作がベルリン映画祭で受賞したことがキャリアにどう影響したかの質問。
A: 当時スペインでは、映画祭に出品するというのはそう多くなかったので注目されました。しかし映画祭は数が多すぎて出品しただけでは気づいてもらえず、ですから受賞はとても重要でした。注目を集めるには何かプラスが必要なのです。
Q: フランコ政権後期から民主主義移行期に登場した世代に属しています。その頃の映画製作の実情についての質問。
A: フランコがまだ死んでいなかったので(1975年没)、第1作(「Habla, mudita」73)は検閲を受けましたが、受けたのはこの1作だけです。しかし、何よりも検閲は私たちを萎縮させ、苛立ちを引き起こした。しかしそれと引き換えに、人々はどこが検閲され削られたかを見つけたりして、それなりに惹かれました。観客との一種の共犯関係があったのです。移行期にはそれが特に顕著でした。検閲を気にする必要がなくなって共犯関係は失われました。
Q: キャリアを最も決定づけた作品は何かの質問。
A: 私が若くて欲望が強かった頃の初期の映画によい思い出があります。70年代から80年代にスペインで映画を撮るのは非常に困難でした。撮影期間が今より長いこともありました。今は残念ながら短くなって数週間です。今よりずっと製作状況は厳しかったのに、最高の思い出は初期の作品で、記憶に残るのは(名優フェルナンド・フェルナン=ゴメス主演、1980年製作の)『マラビーリャス』です。

(最高の思い出がある『マラビーリャス』のポスター)
Q: 『夢遊病者』や『庭の悪魔』もお気に入りと思いますが、2作についての質問。
A: 私が映画を撮り始めたとき、『夢遊病者』や『マラビーリャス』はかなり稀な作品、破壊的でした。伝統的なスペイン映画との決別がありました。一部の人には受け入れられましたが、一方ほかの人は好きではありませんでした。それで少なくともより古典的な映画に切り替えました。私も年を取ったわけです(笑)。これは一般の観客に門戸を開きましたが、破壊的な映画の新鮮さを少し失いました。一部の人にしか受け入れられなかった映画でも、初期の作品は気に入っています。いつも批判的なサポートを受けます。ほかの監督は批判されると不平を言いますが、私の場合は専門家の評価でキャリアが推進されたので、文句は言えないのです。そうでなければ、私はここにいないでしょう。それから私の映画は緩慢な領域に入りましたが製作できただけ満足です。映画製作は高価で役に立たない複雑な面があり、最終的には批評家ではなく、多くの観客に受け入れられることを望んでいます。
★監督が審査員になることの是非について「ご存じのように、監督は一般的に私たち自身の映画の良い判断者ではありません。ある人には共感できるが、他の人はそうではない。打ちのめされた映画というのは、それはまさにあなたが好きな映画で、あなたが良い映画だと思っているものです。自分たちの映画を審査することになると、私たちは信頼できません」ということでした。「然り」ですね。
*FlixOlé フリックスオレというのは、月額3.99ユーロでサブスクリプションして、スペイン映画をタブレットや携帯にダウンロードして視聴できる。追加料金を払えば海外の映画も見ることができる。携帯で映画を見る時代になったのでしょうか。「映画は映画館で見る」という管理人の世代は、もはや化石人間なのでしょう。
ビクトル・エリセの第4作目「Cerrar los ojos」② ― 2022年07月25日 17:09
国立映画学校の実習制作「テラスにて」から「Cerrar los ojos」まで
★ビクトル・エリセの長編4作目となる「Cerrar los ojos」が映画データベースIMDbにアップされました。前回紹介した内容に止まり新味はありませんが、かつて何回かあった脚本段階での打ち切りはないと判断して、キャリア&フィルモグラフィーを列挙します。前回は『マルメロの陽光』(92)以降をご紹介しましたが、今回は国立映画研究所 IIEC(1947年設立)の実習制作「テラスにて」から「Cerrar los ojos」までとします。日本語版ウイキペディアとスペイン語版には、製作年ほか若干の相違がありますが、概ね後者によりました。1998年、詩人のイサベル・エスクデロ、ラモン・カニェリェス監督と自身の制作会社ノーチラス・フィルムズ Nautilus Films を設立、それ以後の作品を製作している。
◎主なフィルモグラフィー◎(「」は仮訳、『』は公開・DVDの邦題)
1961 En la terraza(「テラスにて」4分、無声、モノクロ)監督・脚本
1962 Entre las vías(「レールの軌間」9分、無声、モノクロ)監督・脚本
1962 Páginas de un diarios perdido(「失われた日記のページ」12分、無声、白黒)
監督・脚本
1963 Los días perdidos(中編「失われた日々」41分、モノクロ)監督・脚本
1969 Los desafíos(『挑戦』第3話、邦題DVD)監督・脚本
1973 El espíritu de la colmena(『ミツバチのささやき』97分)監督・脚本
1983 El sur(『エル・スール』94分)監督・脚本
1992 El sol del membrillo(『マルメロの陽光』135分)監督・脚本
2002 Ten Minutes del Older:The Trumpet(Lifeline)監督・脚本
(オムニバス『10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス』ライフライン、10分)
*スペインでは配給の問題で未公開。
2002 Alumbramiento(「誕生」10分、上記を短編として独立させたもの)
*パンプローナ開催の第3回プント・デ・ビスタ映画祭2007のクロージング作品
2006 La morte rouge(「緋色の死」34分、カラー&モノクロ)
2007 Sea-Mail(「船乗り-メール」4分、カラー)
2007 Victoe Erice: Abbas Kiarostami: Correspondencias
(「アッバス・キアロスタミとのビデオ往復書簡」98分)
*2005年~2007年に交わした10通のビデオレター
2011 3.11 Sense of Home(Episodio Ana Three Minutes ドキュメンタリー、3分)
2012 Centro Histórico(Episodio Vidrios partidos)監督・脚本
(オムニバス『ポルトガル、ここに誕生す~ギマランイス歴史地区』
割れたガラス」30分)
2019 Piedra y cielo(「石と空」ドキュメンタリー、17分)
2023 Cerrar los ojos (製作年は未定)
1967 El próximo otoño(監督アントニオ・エセイサ「今度の秋」)
脚本、監督との共同執筆
1968 Oscuros sueños de agosto(監督ミゲル・ピカソ「8月の暗い夢」)
脚本、監督との共同執筆
1998 La promesa de Shanghai(「上海の約束」)
*1994年、フアン・マルセの小説 ”El embrujo de Sanghai” の映画化を、プロデューサーのアンドレス・ビセンテ・ゴメスはエリセに依頼した。作家の熱意もあって3年かけて10バージョンほど脚色したが、3時間という長尺は経済的な理由で調整できず、主演の一人にフェルナンド・フェルナン・ゴメスを決定していたにもかかわらず、1999年3月突然中止になった。その後フェルナンド・トゥルエバの手に渡り、2002年、別バージョンで「El embrujo de Sanghai」として完成させたので、エリセの脚本は使用されなかった。
エリアス・ケレヘタに見出された才能、オムニバス映画「Los desafíos」
★1940年6月30日、バスク自治州ビスカヤ県カランサ生れ、監督、脚本家。一家は数ヵ月後にサンセバスティアンに引っ越し、彼の地で育った。高校卒業後、17歳でマドリードに移り、マドリード中央大学(現マドリード・コンプルテンセ大学)では、政治学と法学を専攻した。その後、1960年に国立映画研究所に入学して映画を学んだ。このイタリア映画のネオレアリズモの新しい流れを汲む映画学校の第1期生が、フアン・アントニオ・バルデムやルイス・ガルシア・ベルランガである。エリセは実習制作として1961年の短編「En la terraza」と、1962年の「Páginas de un diarios perdido」を16ミリで撮り、1963年の「Los días perdidos」で監督資格をとって卒業した。
★映画評論家として「芸術と思想」や「ヌエストロ・シネ」などの雑誌に映画批評を執筆するかたわら、バシリオ・マルティン・パティノの「Tarde de domingo」の進行記録係、ミゲル・ピカソの「Oscuros sueños de agosto」やアントニオ・エセイサの「El próximo otoño」の脚本を監督と共同執筆、俳優としてマヌエル・レブエルタの映画に出演している。
★1969年、エリセはクラウディオ・ゲリン(第1話)とホセ・ルイス・エヘア(第2話)の3監督によるオムニバス映画「Los desafíos」(『挑戦』)を撮る。3人ともIIECの有望な卒業生として、当時の大物プロデューサーであったエリアス・ケレヘタが推薦した。脚本には名脚本家であったラファエル・アスコナが共同執筆者として参加している。音楽にルイス・デ・パブロ、撮影にルイス・クアドラド、編集にパブロ・G・デル・アモ、美術にはまだ監督デビューしていなかったハイメ・チャバリと、4年後の長編デビュー作『ミツバチのささやき』と同じ布陣で臨んでいる。第3話を務めたエリセは、チンパンジー連れのアメリカ人、スペイン人、キューバ人の若者グループが突然おこすハプニングを描いている。

(唯一生き残るチンパンジーのピンキーを配したポスター)
★3話に共通して主演したディーン・セルミエがアメリカ的生活様式と価値観を体現し、スペイン側の相克と攻撃性が語られており、3話ともに出口なしの結末である。サンセバスチャン映画祭1969で監督部門の銀貝賞、シネマ・ライターズ・サークル賞では脚本賞と第2話に主演したアルフレッド・マヨが男優賞を受賞してケレヘタの期待に応えている。キャストはブニュエル映画でお馴染みのフランシスコ・ラバル、アスンシオン・バラゲル、テレサ・ラバル、フリア・グティエレス・カバ、フリア・ペーニャ、ルイス・スアレスなど、当時のスターが出演している。

(ディーン・セルミエとピンキー)
★2019年、エリセは「Piedra y cielo」をナバラで撮影した。これはビルバオ美術館がプロデュースしたホルヘ・デ・オテイサの彫刻作品とアギーニャ山の頂上にあるミュージシャンのアイタ・ドノスティアのモニュメントについてのビデオ・インスタレーション。「Espacio Día」(11分)と「Espacio Noche」(6分)の二部構成。映像にはピアニストのホス・オキニェナの演奏によるアイタ・ドノスティアの音楽テーマと、オテイサの詩の断片が挿入されている。2019年11月13日ビルバオ美術館でプレミアされた。オテイサはギプスコア県(オリオ1908~サンセバスティアン2003)出身のバスクを代表する彫刻家で詩人。ナバラにホルヘ・オテイサ美術館がある。
★長編3作(『ミツバチのささやき』『エル・スール』『マルメロの陽光』)については、いずれアップするとしても既に語りつくされている感があり、今回は受賞歴にとどめます。監督は常々フィクションとドキュメンタリーは同じと語っておりますので、『マルメロの陽光』は区別しませんでした。
*『ミツバチのささやき』(El espíritu de la colmena)1973
サンセバスチャン映画祭1973金貝賞
シカゴ映画祭1973シルバー・ヒューゴ
シネマ・ライターズ・サークル賞1974 作品・監督・男優賞(フェルナンド・F・ゴメス)
フォトグラマス・デ・プラタ賞1974俳優賞(アナ・トレント)
ACE賞1977女優賞(アナ・トレント)、監督賞


(フランケンシュタインに出会った瞬間のアナ・トレント)
*『エル・スール』(El sur)1983
シカゴ映画祭1983ゴールド・ヒューゴ
サンジョルディ賞1984作品賞
サンパウロ映画祭1984批評家賞
ASECAN(アンダルシア・シネマ・ライターズ)1984 スペインフィルム賞
フォトグラマス・デ・プラタ賞1984作品賞
シネマ・ライターズ・サークル賞1985監督賞
他、カンヌ映画祭1983コンペティション部門にノミネートされ好評をえる。
フォトグラマス・デ・プラタ賞にイシアル・ボリャインがノミネートされた。


(15歳の少女を演じたイシアル・ボリャイン)
*『マルメロの陽光』(El sol del membrillo)1992
カンヌ映画祭1992審査員賞・国際映画批評家連盟賞FIPRESCI
シカゴ映画祭1992ゴールド・ヒューゴ
サンジョルディ賞1993 特別賞
ADIRCAE1993 監督賞
ASECAN1994 スペインフィルム賞
トゥリア賞1994 スペインフィルム賞
ACE賞1996 作品賞


(画家アントニオ・ロペス)
★他に栄誉賞として、1993年映画国民賞、1995年芸術功労賞金のメダル、2012年スペイン映画史家協会栄誉賞、2014年ロカルノ映画祭生涯功労賞としてヒョウ賞を受賞している。

(トロフィーを手にしたビクトル・エリセ、ロカルノ映画祭2014)
ビクトル・エリセ、30年ぶりに商業映画に復帰*「Cerrar los ojos」 ― 2022年07月15日 12:10
カンヌ映画祭2023プレミアを視野に新作「Cerrar los ojos」に着手

(ビクトル・エリセ、2019年11月、ビルバオ美術館にて)
★先日、7月5日にビクトル・エリセ(ビスカヤ県カランサ、1940)が4作目となる長編映画「Cerrar los ojos」を準備中というニュースが駆けめぐった。プロダクションの正式なプレス会見での発表ではなく、アンダルシア州の公共テレビのカナル・スールが資金提供する11本のフィクションと18本のドキュメンタリーのなかにエリセの新作も含まれており、「ホセ・コロナドとマリア・レオンが主演します」というアナウンスをした。続いて制作会社はタンデム・フィルムズTandem Filmsのほか、マラガの制作会社ペカド・フィルムズPecado Films、エリセ自身の制作会社ノーチラスNautilusであることが明らかになった。ただし本作の準備を秘密裏に進めてきたタンデムの製作者クリスティナ・スマラガは、この報道の取材に応じなかったようです。というわけでウラがとれておらず全体像が見えておりませんが、脚本の執筆は昨年の秋から着手、共同執筆者はミシェル・ガスタンビデということも分った。今年の10月にクランクインの予定なら、2023年のカンヌ映画祭上映の可能性もゼロではないか。

(新作を準備中のビクトル・エリセ)
★7月10日付のエル・パイス紙の記事によると、物語は2012年4月、「Quién sabe dónde」というスタイルのテレビ番組から始まり、今は引退して漁業をしているベテラン監督、作家でもあった人物を探しあてます。家族の不幸と2作目となるはずだった大作の頓挫で沈黙していた監督役にヒネス・ガルシア・ミリャンが扮します。この監督の兵役時代からの友人であり、2作目の主人公であった俳優が姿を消してしまったことで映画は未完成になっていた。この46歳でゴヤ賞を受賞したガラン俳優役にホセ・コロナドが扮します。このカップルはガールフレンドたちも共有しており、この切っても切れない二人の友情とアバンチュールを中心に展開するようです。マリア・レオンはそのガールフレンドの一人ということでしょうか。以上の3人以外は未発表、まだIMDbがアップされておらず、本格的なキャスティングはスクリプト完成後になるのでしょうか。
★肝心のスクリプトは目下推敲中だそうですが、読んだ関係者は「大幅な変更はない」と保証していますので、4作目となるエリセの商業映画への復帰作は、ベテラン監督と彼の映画の主演俳優間の友情についてのノスタルジックなドラマとなりそうです。ビクトル・エリセの紹介など今更の感がありますが、1992年のドキュメンタリー『マルメロの陽光』以来、30年間長編を撮っておりません。1999年、フアン・マルセの小説 ”El embrujo de Shanghai” の映画化の脚本に3年間費やしましたが、最終的に撮影に至りませんでした。2002年、別バージョンの脚本でフェルナンド・トゥルエバが完成させました。

(画家アントニオ・ロペス、『マルメロの陽光』から)
★しかし今回は上述しましたようにミシェル・ガスタンビデが共同執筆者、予断は許しませんが大いに期待できます。彼はフリオ・メデムの『バカス』(92)でシネマ・ライターズ・サークル賞、エンリケ・ウルビスの『悪人に平穏なし』ではゴヤ賞2012オリジナル脚本賞を監督と受賞しています。ウルビスとはホセ・コロナドが主演した『貸し金庫507』(02)でも共同執筆しています。1958年プロヴァンス生れ、主に監督との共同執筆がもっぱらですが、相手によって仕事のやり方を選んでいる。気難しいエリセとの共同執筆はうまくいってるのでしょうか。詩人、監督、脚本の指導教官と多才な人です。
冬眠していたわけではないビクトル・エリセ
★ビクトル・エリセのキャリア&フィルモグラフィーは後日にアップしますが、エリセは結構短編を撮っているほか、イランのアッバス・キアロスタミとのオーディオビジュアルによる書簡をやりとりしています。また2002年には、7人の監督による10分間ずつのオムニバス映画『10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス』に、「ライフライン」で参加した。本作の舞台はエリセが生まれた年と同じ1940年、スペインの片田舎で一つの生命が誕生する自伝的なモノクロ作品。アキ・カウリスマキ、ヴェルナー・ヘルツォークなどをおさえて7作中では最も印象深い秀作、批評家からも観客からも絶賛されました。
★2006年、「La morte rouge」(32分)は、5歳のとき初めて見た映画を語る短編、映画とはロイ・ウィリアム・ニールのミステリー『シャーロック・ホームズ 緋色の爪』(1944)を指し、後年の自作に大きなインパクトを与えたという。2007年「Sea-Mail」(4分)と「Víctor Erice:Abbas Kiarostami:Correspondencias」(96分)は、バルセロナの現代文化センターの依頼によるアッバス・キアロスタミとのビデオ往復書簡、2011年、21人の監督からなる共同作業「3.11 Sense of Home」は、河瀨直美の呼びかけで2011年3月11日に起きた東日本大震災の犠牲者に捧げられた各3分11秒の短編でした。エリセはアナ・トレントと再びタッグを組んで参加した。

(短編「La morte rouge」のポスター)

(ビデオレター「Víctor Erice:Abbas Kiarostami:Correspondencias」のポスター)
★2012年、「Centro Histórico」は、ポルトガルの世界遺産ギマランイス歴史地区を題材にしたオムニバス映画。エリセの「Vidrios partidos」(「割れたガラス」)のほか、アキ・カウリスマキ、ペドロ・コスタ、マノエル・ド・オリヴェイラの4監督が参加している。本作は第13回東京フィルメックス映画祭2012の特別招待作品として上映され、翌年『ポルトガル、ここに誕生す~ギマランイス歴史地区』の邦題で公開された。

(ペドロ・コスタ、ビクトル・エリセ、バジャドリード映画祭、2013年10月)
★そのほか、昨年11月にエリセは、バスクの彫刻家ホルヘ・オテイサに関するエッセイ「Piedra y cielo」を発表しました。その折りのマスメディアとの会談で、90年代から業界は根本的に変化して、リュミエール兄弟以来の映画は映画館のスクリーンで見る体験がなくなり、映画館が残骸として残った。テレビやタブレットで見ることを否定しないが、映画を見る理想の場所は映画館であると語っている。
★「問題は映画を製作することではなく、それが映しだされる場所なのですが、これが難問です。1992年以来、私は長編ではありませんがかなりの仕事をしてきましたが、ほとんど知られていません。私の最後の商業映画のリリースは、アキ・カウリスマキ、ペドロ・コスタ、マノエル・ド・オリヴェイラと一緒に作った「Centro Histórico」ですが、映画を上映する場所を確保するためにお金を払わねばならず、監督たちの知名度にもかかわらず、スペインではほとんど誰も見ていません。これがこの国で起こっている現実です」とも語っている。しかし新作「Cerrar los ojos」のニュースは駆けめぐり、映画界はエリセの新作を熱心に待っています。
★キャスト紹介は気が早いと思いますが、主役の監督役に決定しているヒネス・ガルシア・ミリャンを簡単に紹介しておきます。1964年ムルシア州プエルト・ルンブレラス生れ、映画、TV、舞台俳優、1992年デビュー。当ブログでの紹介記事は初めて、主にTVシリーズに出演、2008年「Herederos」でスペイン俳優組合TVシリーズ部門の助演男優賞を受賞している。イサベル女王の生涯を描いた「Isabel」(14話11~13)のフアン・パチェコ役、「Matadero」(10話19)のパスクアル役、直近では Netflix 初出演のメキシコを舞台にした『そしてサラは殺された』(3シーズン25話、21~22)で主役のセサル・ラスカノを演じている。他に字幕入りで見られる『海のカテドラル』(8話、2018)も Netflix で配信された。
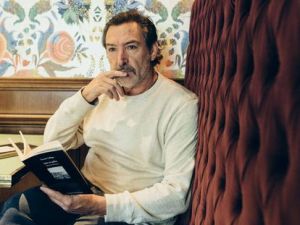
(ヒネス・ガルシア・ミリャン)
★映画では、主に脇役ですが、チェマ・デ・ラ・ペーニャの1981年2月23日に起きた軍部のクーデタを描いた「23-F: la pelicula」(11)でアドルフォ・スアレス首相を演じた。グラシア・ケレヘタのコメディ「Felices 140」(15)、エンリケ・ウルビスの歴史物「Libertad」(21)ほか、脇役が多いので出演数は多い。主役を演じるのは今回が初めてでしょうか。
*「Felices 140」の作品紹介は、コチラ⇒2015年01月07日
*「Libertad」の作品紹介は、コチラ⇒2021年04月06日
★ホセ・コロナド(マドリード1957)については、Netflix で配信されたミゲル・アンヘル・ビバスの『息子のしたこと』(18)、TVシリーズ『麻薬王の後継者』(18・20)など、最近の出演作はアップしておりませんが、既にキャリア紹介をしています。マリア・レオン(セビーリャ1984)については、ベニト・サンブラノの『スリーピング・ボイス 沈黙の叫び』(11)他でキャリア紹介をしています。いずれキャスティングが確定してからアップします。
*ホセ・コロナド関連記事は、コチラ⇒2014年03月20日/2017年04月17日
*『貸し金庫507』の紹介記事は、コチラ⇒2014年03月25日
*マリア・レオンの紹介記事は、コチラ⇒2014年04月13日/2015年02月02日
*『スリーピング・ボイス 沈黙の叫び』の作品紹介は、コチラ⇒2015年05月09日
最近のコメント