イベロアメリカ映画賞の行方*ゴヤ賞2016ノミネーション ⑩ ― 2016年01月23日 20:58
パブロ・トラペロ“El clan”で決まり?

(プッチオ家ファミリーをバックにしたポスター、中央がギジェルモ・フランセージャ)
★ガラがあと2週間に迫ってきました。秋のラテンビートに関係が深いラテンアメリカ諸国の映画を大急ぎでおさらいしておきます。ノミネーションは例年通り4作品、アルゼンチン、チリ、ペルー、キューバの4カ国です。キューバはアカデミー賞とゴヤ賞に作品を送らないと表明しておりましたが、フタを開けてみればノミネーションされていたのでした(アカデミー賞はキャンセルした)。どうして気が変わったのかちょっとばかりミステリー、2014年の旧作ですがICAIC製作です。IMDbによれば、目下のところスペインでは2015年10月末にバルセロナで開催された「ゲイ&レズ映画祭」で上映されただけです。ただIMDbのスペイン語映画情報はアップが遅く実際は公開されているのかもしれません。というのもノミネーション条件の一つが「授賞式前の公開」だからです。
★個人的な好みから言えば、一押しは迷うことなくパブロ・トラペロです。ラテンビートでの上映を切に願っております。今までのトラペロ監督とは一味違う問題作、ベネチア映画祭監督賞受賞作品。ノミネーション4作品は以下の通りです。
◎“El clan”(The Clan)監督パブロ・トラペロ(アルゼンチン=スペイン)
◎“Magallanes” 監督サルバドル・デル・ソラル
(ペルー=アルゼンチン=コロンビア=スペイン)
◎“La Once”監督マイテ・アルベルディ(チリ)ドキュメンタリー
◎“Vestido de novia”(His Wedding Dress) 監督マリリン・ソラヤ(キューバ=スペイン)
★◎印は既にご紹介済み作品です。次回はチリの女性監督マイテ・アルベルディの長編ドキュメンタリー第2作目“La Once”、コメディです。元気すぎるおばあちゃん6人組の「仲良しお茶べり会」の話です。チリのシネアストの層の厚さを感じさせるドキュメンタリー。スペインでは条件を満たすためか、1月8日マドリード、翌日バルセロナと大急ぎで公開されました。

(全員ふくよかすぎる「仲良しお茶べり会」のメンバー、映画から)
*“El clan”は、ベネチア映画祭2015でアップ済み、コチラ⇒2015年8月7日・9月21日
*“Magallanes”は、サンセバスチャン映画祭2015「ホライズンズ・ラティノ」でアップ済み、
チリ映画”La Once”*ゴヤ賞2016ノミネーション ⑪ ― 2016年01月25日 16:04
食べて喋って、こんなに元気で長生きです

★マイテ・アルベルディの長編ドキュメンタリー第2弾はコメディ“La Once”です。昨年、オスカー賞代表作品の選定にパブロ・ララインの“El Club”『ザ・クラブ』(ベルリン映画祭2015グランプリ審査員賞受賞)と“La Once”というドキュメンタリーのどちらにするかチリ映画アカデミーが迷っているという記事を目にしました。結局オスカー代表作品はララインに決定したのでゴヤ賞も『ザ・クラブ』と予想していました。だってドキュメンタリーは分が悪いし、監督の知名度もイマイチだから。ところが違った。ドキュメンタリーと言ってもこれはコメディだという、本当に珍しい。検索をかけたら厚化粧の貫禄充分のおばあさんたちが美味しそうにケーキを食べている。毎月1回、60年間続いているお茶会だという。監督の実のお祖母さんがメンバーの一人、なるほど、これで繋がった。

(お茶とケーキ、おしゃべりに余念がない老人パワーに圧倒される?)
“La Once”(“Tea Time”)2014
製作:Micromundo Producciones
監督・脚本:マイテ・アルベルディ
撮影:パブロ・バルデス
編集:フアン・エドゥアルド・ムリージョ、セバスチャン・Brahm
音楽:ホセ・ミゲル・トバル、ミゲル・ミランダ
プロデューサー:クララ・タリッコ
データ:チリ、スペイン語、2014年、80分、ドキュメンタリー、公開チリ2015年6月4日、(マドリード)プレミア2015年11月29日・公開2016年1月9日、(バルセロナ)プレミア12月4日、公開1月8日
映画祭:サンティアゴ映画祭2014、メキシコ移動ドキュメンタリー映画祭2015(1月),以下マイアミ(3月)、ブエノスアイレス・インディペンデント・シネマ(4月)、シアトル(5月)、シドニー(6月)、シェフィールド・ドキュメンタリー(UK 6月)、など各映画祭で定栄された。
受賞歴:サンティアゴ映画祭作品賞・監督賞、アムステルダム・ドキュメンタリー映画祭監督賞、カルタヘナ映画祭でゴールデン・インディア・カタリナ・ドキュメンタリー賞受賞、バルセロナ・ドキュメンタリー映画祭でTV3賞、他、マイアミ映画祭、グアダラハラ映画祭でも受賞している。
主演者:マリア・アンヘリカ・シャルペンティエル(元スペイン語教授)、マリア・テレサ・ムニョス(監督の祖母)、シメナ・カルデロン、アリシア・ペレス、マヌエラ・ロドリゲス、フアニータ・バスケス、ニナ・キッカレッリ Chiccarelli、他(全員女性)
解説:タイトルのLa Onceラ・オンセ(午前11時という意味)というのは、イギリスの午前11時頃にとるお茶と軽食「elevenses」とか、スペインの昼食前に摂るメリエンダ「merienda」に相当するようです。現在では午後のおやつ、または昼食にも使用されており、いわゆるアフタヌーンティーです。チリでは定冠詞laを複数にしてlas oncesともいう。現在では時刻に拘らず夕食前に会話を楽しみながら摂る広義の「お茶と軽食会」を指すよう変化している。1日3食どころか5食になって肥満人口の増加に拍車をかけているのではないでしょうか。
物語:ひと月1回のペースで延々60年間も続いているお茶とケーキを楽しみながらのお喋り会。メンバーの共通点は多くが1930年代生れ、同じカトリック系の女学校の卒業生ということ。もう間もなくあの世に旅立つことが避けられない人生最後の時間を過ごしている女性たち。アジェンデ政権やピノチェトの軍事クーデタという変革期をリアルタイムで目撃したツワモノたち。ラテンアメリカ映画の定番テーマでもある老人の孤独、貧困、社会の疎外者というテーマを避けて、かつてはドラマティックな人生を歩んだ女性たちの老い方のレシピ。意見の違いや時には秘密も曝露される。老いとか、死という重荷は取り敢えず下ろして、人生の最後においても尚且つエネルギッシュに輝いている女性たちの「愛と友情」についての物語だ。

(しっかりお化粧も致します 映画から)
★監督キャリア& フィルモグラフィー:マイテ・アルベルディMaite Alberdi 1983年首都サンティアゴ生れ、監督、脚本家。チリ・カトリック大学オーディオビジュアル監督と美学科で社会情報を専攻、小宇宙の日常的な事柄に興味があり、フィクションとノンフィクションのジャンル区別をセず、あるのは映画だけという立場をとっている。複数の大学で教鞭をとるかたわら、“Teorías del cine decumental en Chile: 1957-1973”(共著)という著書がある。「チリ映画は全体的にみて、折衷主義で多様性に富んでいる」と語っている。“La Once”は12の映画祭で上映され、なかには参加した出演者たちもいる。
2007“Las peluqueras”(短編ドラマ)監督・脚本
カサ・デ・アメリカ、TVEよりイベロアメリカ短編賞、バルディビア映画祭2008ユース賞
2011“El Salvavidas”(長編ドキュメンタリー)監督・脚本
バルディビア映画祭2011観客賞、グアダラハラ映画祭2012審査員特別賞、バルセロナ、ドキュメンタリー映画祭2013新人ドキュメンタリー賞、ほか
2014“La Once”省略
2014“Propaganda”(長編ドキュメンタリー、脚本のみ)
★製作者クララ・タリッコのキャリア:Clara Taricco ブエノスアイレス大学文学部卒、チリ・カトリック大学オーディオビジュアル表記法のマスター号取得。2009年より5年間アルベルティ監督の“La Once”の製作を手掛ける。2010~11年、アニメ・シリーズ“Libertas”を製作、“Antología de textos críticos sobre Raúl Ruiz”の翻訳、2009年よりバルディビア映画祭の産業研究室に在籍している。

(左から、ラ・オンセを楽しむアルベルティ監督とクララ・タリッコ)
★子供のときから伝統的な慣習の目撃者だったが、大人になってからはチリの女性たちが体験した記録を残すドキュメンタリー監督になる道を選んだ。本作の目的は「社会の中で女性だけに課せられた役割をどうやって変革していくか」に焦点を当てて描いた。祖母が学んだ女学校はいわゆる「良妻賢母教育」をしていた。当時の女性には参政権はなく政治に参加することは出来なかった。しかしチリに限ったことではなく、日本でも敗戦後の1946年10月、チリはもっと遅く1949年です。出演してくれた女性たちは自分たちが人生の最後に差し掛かっていることを自覚している。差し迫っている死の不安は常にあるが、映画の中ではっきり死が語られることはない。重要なのは一緒にテーブルを囲んで時間を共有することだと語っている。
★2009年から5年間をかけて撮ったから、中には本作の成功を知らずに鬼籍入りした女性もいた。監督によると、出演してくれた女性たちにお披露目をするときには、彼女たちがどんな反応を示すか怖かったという。彼女たちも自分たちがどのように映っているか神経質になっていた。しかし互いの心配は最初だけで、しばしばおこる笑い声、終いには皆な感動して気に入ってくれた。ドキュメンタリーの場合、一般観客よりスクリーンに出てくれた人々の反応の予測が難しいという。出演者を知らずに傷つけてしまう可能性もあるからでしょうね。
★ドキュメンタリーがゴヤ賞にノミネーションされる可能性は少ない。「チリ代表作品に選ばれたのは2003年が最後で、そのキャンペーンの難しさがネックだったと聞いています。だから今回ノミネーションされたことを素直に喜びたいし、出演してくれた女性たちを誇りに思う」と監督は締めくくった。甘党の観客にはヨダレが出そうなケーキが登場します。
キューバ映画”Vestido de novia”*ゴヤ賞2016ノミネーション ⑫ ― 2016年01月27日 19:22
キューバ初の性転換をテーマにした差別と不寛容の物語
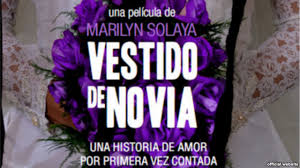
★イベロアメリカ映画賞ノミネーションの最後はキューバ映画“Vestido de novia”、監督は『苺とチョコレート』(1993,トマス・グティエレス・アレア)でハバナ大学生ダビドの恋人ビビアンになったマリリン・ソラヤの長編初監督作品です。ホモフォビア、貧困、ジェンダー、性暴力、マチスモ、家父長制度、ダブルモラルなどベルリンの壁崩壊後未曽有の危機にあった1990年代半ばのキューバが抱える問題を切り取ったドラマ。
“Vestido de novia”(His Wedding Dress)2014
製作:ICAIC(キューバ映画芸術産業庁)/
監督・脚本:マリリン・ソラヤ
撮影:ラファエル・ソリス
編集:ミリアム・タラベラ
録音:カルロス・デ・ラ・ウエルタ
製作者:カルロス・デ・ラ・ウエルタ、イサベル・プレンデス
データ:キューバ=スペイン、スペイン語、2014年、100分、撮影ハバナのベラード、カマグエイ、協力者マビィ・スセル、キューバ未公開
映画祭・受賞歴:ハバナ映画祭2014観客賞・スペシャル・メンション受賞、オタワ・ラテンアメリカ映画祭2015上映,マラガ映画祭2015ラテンアメリカ部門観客賞受賞、バルセロナ・ゲイ&レズ映画祭2015上映
キャスト:ラウラ・デ・ラ・ウス(ロサ・エレナ)、ルイス・アルベルト・ガルシア(夫エルネスト)、ホルヘ・ペルゴリア(ラサロ)、イサベル・サントス(シシー)、マリオ・ゲーラ(ロベルト)、マヌエル・ポルト(パブロ)、パンチョ・ガルシア(ラファエル)、アリナ・ロドリゲス(サンドラ)、他
プロット:1994年ハバナ、結婚したばかりのロサ・エレナの物語。ソビエト崩壊後、共産主義の小さな島を襲った経済危機のなか、40歳になる准看護師ロサ・エレナは、夫エルネストと認知症を患う車椅子生活の父親の三人で貧しいながらも幸せであった。夫はキューバの観光政策に欠かせない建築現場の監督をしていた。しかし彼女には夫の知らないもう一つの顔があった。エルネストと知り合う前に働いていた男声合唱団のメンバーであった。生活費の助けになるその仕事を内緒で今も続けていた・・・やがて妻の過去の秘密は夫の知るところとなり、二人の関係は家父長制的な構造、ジェンダー、暴力、マチスモ、ダブルモラルなどが次第に表面化していく。

(結婚したばかりでアツアツのエルネストとロサ・エレナ)
★監督キャリア&フィルモグラフィー:Marilyn Solaya 1970年ハバナ生れ、監督、脚本家、女優。おそらく世界でもっとも有名なキューバ映画といえば、それは『苺とチョコレート』にとどめを刺す。本作で女優デビュー、22歳でこの〈アレア映画〉に出演したことが、自分の原点だと語る。「ティトン(アレアのこと)がおり、セネル(・パス原作者)、フアン・カルロス(・タビオ助監督)などと仕事ができた」ことが今の自分を作ったと。その後、エリセオ・スビエラの“Despabilate amor”(1996,アルゼンチン映画)に脇役で出演した他、チリ、アルゼンチン製作の短編に出演しているが、結局ドキュメンタリー作家の道を歩むことになる。
1999“Alegrías”(短編ドキュメンタリー)監督・脚本
2001“Hasta que la muerte nos separe”(同上)監督・脚本
2002“Mírame mi amor”(同上)監督・脚本
2004“Roberto Fernández Retamar”(同上)監督
2010“En el cuerpo equivocado”(長編ドキュメンタリー)監督
2014“Vestido de novia”省略

(マビィ・スセルを配した“En el cuerpo equivocado”の英題ポスター)
★2010年の長編ドキュメンタリー“En el cuerpo equivocado”は、“In the Wrong Body”の 英題で国際映画祭でも上映された。1988年キューバで最初の性転換手術を受けたマビィ・スセルの心の内面を旅する作品で、8年間の調査研究を経て映画化された。マビィ・スセルは性同一障害(心の性と身体の性が一致しない)で苦しんでいた。男でも女でもない異形の存在は親からも理解されなかったという。当時センセーショナルなニュースだったが、まだ自分には何の知識もなかったという。十年掛かりだったという“Vestido de novia”にも脚本からコラボしている。実父はロサ・エレナの父親に投影されている印象を受けたが、この父親の認知症は息子が受けた性転換手術の苦しみから逃れるための仮病だったことが最後に分かる。他の性転換者たちとの交流、俳優たちの演技相談にものり、スセルの体験は主人公ロサ・エレナや性転換を受けた友人シシーの人格造形に役立っているようだ。

(左から、ラウラ・デ・ラ・ウス、監督、マビィ・スセル)
登場人物のすべてが「わたし」です
★目下2作品ともキューバでは未公開(映画祭上映のみ)、本作について忌憚なく話題にすることは控える状況にあり、ホモセクシャルに対する理解が進んだとはいえ、ホモフォビアの存在は根強いという。トマス・グティエレス・アレアの『苺とチョコレート』を嫌悪するひとがおり、「TV放映まで15年以上に及ぶ歳月を必要とした」とソラヤ監督。他は推して知るべしです。つまりキューバの1990年代半ばの「特別な時代」を背景に性転換をテーマにした映画が、よくICAICの検閲を通ったということです。

(ウェディングドレス姿のロサ・エレナと性転換前のアレハンドロ)
★しかし「この映画は性転換に触れていますが、それが本質ではありません。私たちが暮らしているキューバには三つの国が存在しています。一つはいわゆるキューバと言われる国、二つ目は殆どのキューバが実際に暮らしている国、もう一つが或る人たちが暮らしている国です」と、ハバナ映画祭上映前にソラヤ監督が語っている。ハバナでのインタビューなので、奥歯に物が挟まったような印象を受けるが、二つ目はフェルナンド・ペレスのドキュメンタリー『永遠のハバナ』(2003)に出てくるような一般のキューバ人、「或る人たち」というのは特権階級にいる人、映画ではホルヘ・ペルゴリアが演じたエリート階級のラサロのような人を指しているようだ。キューバに「赤い貴族」ノーメンクラトゥーラは存在しないというのは幻想でしょう。F・ペレス監督の“La pared de las palabras”(2014)には、J・ペルゴリア、L・デ・ラ・ウス、I・サントスなど演技派が出演しているが、なかなか日本には紹介されない。

(愛が壊れてしまったエルネストとロサ・エレナ)
★「この映画の視点は人間性を重んじ敬意を払っている点です。多くの人々の共感を得られると信じています。他人の不幸を喜ぶべきではないし、キューバには必要な映画です」と監督。どうして舞台を1994年にしたかというと、「特別の時代」と現在はあまり変わっていないからだという。当時機能しなかったことは今もって機能していない。庶民の経済的困難は続いているし、革命が起こった1959年以来、マイノリティたちの居場所がないことに変わりはない。国を出た人、残った人、エイズで亡くなった人、そういう違いはあっても、忘れられ、遠ざけられ、無視され、根拠なく裁かれる存在、差別と不寛容に耐えている。ロサ・エレナの未来も明るくない。
「映画に登場する女性たちの全てが私です。男性たちの全ても私です。“Vestido de novia”は私の叫びなのです」

(最後は筏でアメリカに向かうシシー役のイサベル・サントス)
★最初から最後までリアリズムで押していくやり方は、今日の映画技法からみると物足りないが、スペイン映画アカデミーが本作を推した理由が何となくお分かり頂けたでしょうか。1994年を舞台にしたアグスティ・ビリャロンガの『ザ・キング・オブ・ハバナ』も脚色賞・新人女優賞(ヨルダンカ・アリオサ)・撮影賞(ジョセプ・マリア・アモエド)と3カテゴリーにノミネーションされています。ハバナでの撮影を「あまりにも脚本が悪すぎる」とICAICで拒絶され、やむなくドミニカ共和国のサント・ドミンゴで撮影されました。皮肉にも脚色賞にノミネートされております。パブロ・トラペロの“El clan”受賞を予想しますが、こればかりは蓋を開けてみないと分かりません。
*ラテンビート2015上映の『ザ・キング・オブ・ハバナ』の記事は、コチラ⇒2015年9月17日
*ベネチア映画祭監督賞受賞の“El clan” の記事は、コチラ⇒2015年8月7日・9月21日
女優賞の行方*ゴヤ賞2016ノミネーション ⑬ ― 2016年01月30日 10:57
誰が受賞してもおかしくない主演女優賞
★フォルケ賞とフェロス賞の両方にノミネートされフォルケ賞を手にしたのがナタリア・デ・モリーナ、フォルケ賞では全く無視されたかたちのインマ・クエスタがフェロス賞を受賞した。こんな困難な役を引き受けてくれる女優は、「ぶっ飛んだクレージーなジュリエット・ビノシュ以外にいなかったのよ」とイサベル・コイシェ監督を感激させたフランスの大女優、ノーメイクも厭わない役者魂にはコイシェならずとも応援したくなる。両方にノミネート、無冠だったが自らも初めてプロデューサーに挑戦して全力投球したペネロペ・クルスと、もう誰が受賞してもおかしくない。クルスは過去に主演女優賞を『美しき虜』(98)と『ボルベール』(06)で2度受賞していますが、今回はそれより格段にいい。これはスペインの映画賞だからビノシュの分が悪いのは仕方ありません。

(左から、インマ・クエスタ、J・ビノシュ、P・クルス、ナタリア・デ・モリーナ)
インマ・クエスタ“La novia”監督パウラ・オルティス フェロス賞主演女優賞受賞
ペネロペ・クルス“Ma Ma”同フリオ・メデム
ジュリエット・ビノシュ“Nadie quiere la noche”同イサベル・コイシェ
ナタリア・デ・モリーナ“Techo y comida”同J・M・デル・カスティジョ フォルケ賞女優賞受賞
*“Ma Ma”の記事は、コチラ⇒2015年1月5日
*“Nadie quiere la noche”の記事は、コチラ⇒2015年3月1日
ベテラン演技派が顔を揃えた助演女優賞
★エルビラ・ミンゲスは『暴走車ランナウェイ・カー』で紹介しております。マリアン・アルバレスとノラ・ナバスは、グラシア・ケレヘタの“Felices 140”で共演、アルバレスは“La herida”(13)で、ナバスは『ブラック・ブレッド』(10)で既に主演女優賞を受賞しています。ケレヘタは今年は短編映画賞に“Cordelias”がノミネーションされています。ルイサ・ガバサは、1951年サラゴサ生れのベテラン、TVドラマが多い。アルモドバルの『バチ当り修道院の最期』(83)ではその他大勢の尼僧役、パウラ・オルティスのデビュー作“De tu ventana a la mía”(11)では三人の主役の一人を好演し、それが今回の「花婿の母親」抜擢に繋がったようです。全員フェロス賞にノミネーション、ノラ・ナバスだけが無冠だったが両方にノミネートされていた。

(左から、マリアン・アルバレス、ルイサ・ガバサ、エルビラ・ミンゲス、ノラ・ナバス)
エルビラ・ミンゲス“El desconocido”『暴走車ランナウェイ・カー』監督ダニ・デ・ラ・トーレ
マリアン・アルバレス“Felices 140”同ガルシア・ケレヘタ
ノラ・ナバス “Felices 140”同上
ルイサ・ガバサ“La novia”同パウラ・オルティス
*“Felices 140”の記事は、コチラ⇒2015年1月7日
新人といっても80代も混じっている新人女優賞
★80代の新人とはアントニオ・グスマンのデビュー作“A cambio de nada”に出演したアントニア・グスマン、監督の実のお祖母さんです。監督自身も作品賞、新人監督賞、脚本賞にノミネーションされています。以前にもパコ・レオンのデビュー作 “Carmina o revienta”(2012)に実母カルミナ・ガルシアが主役カルミナで出演ノミネーションされたが、それでも59歳の若さだった。こちらはライバルの『ブランカニエベス』の白雪姫マカレナ・ガルシアの手に渡ってしまった。個人的には応援していたから残念だった。受賞には巡り合わせの運不運がありますね。
★イレネ・エスコラルだけがフォルケ賞とフェロス賞にノミネートされていました。サンセバスチャン映画祭バスク映画部門で上映され、彼女はスペシャル・メンションを受賞しました。将来性を感じさせる女優で先頭を走っている印象です。本作はララ・イサギーレ監督の初監督作品、1985年バスク州のビスカヤ県アモレビエタ生れ、最近の若手監督の特徴でもあるアメリカ留学で映画を学んでいる。若いだけに初々しさに溢れている。恋人になるタマル・ノバスは、アメナバルの『海を飛ぶ夢』でハビエル・バルデムの甥役を好演し、確か新人男優賞を受賞したはずです。
★ヨルダンカ・アリオサはサンセバスチャン映画祭の女優賞受賞者ですが、あちらは国際映画祭、こちらはスペインの映画賞と性格の違いがあります。さらにキューバの女優ということでビノシュ同様分が悪い。イライア・エリアスはアシエル・アルトゥナの“Amama”に主演、本作は同じサンセバスチャンのコンペティションに出品され、「バスク映画Irizar賞」を受賞した。

(左から、ヨルダンカ・アリオサ、イライア・エリアス、イレネ・エスコラル、A・グスマン)
アントニア・グスマン“A cambio de nada”監督ダニエル・グスマン
イライア・エリアス“Amama”同アシエル・アルトゥナ
ヨルダンカ・アリオサ“El rey de La Habana”『ザ・キング・オブ・ハバナ』同A・ビリャロンガ
イレネ・エスコラル“Un otoño sin Berlín”同ララ・イサギーレ
*サンセバスチャン映画祭2015の結果発表記事は、コチラ⇒2015年9月29日
最近のコメント