アルゼンチン映画 『明日に向かって笑え!』*8月6日公開 ― 2021年07月17日 16:26
ダリン父子がドラマでも父子を共演したコメディ

(スペイン語版ポスター)
★セバスティアン・ボレンステインの「La odisea de los giles」(英題「Heroic Losers」)が『明日に向かって笑え!』の邦題で劇場公開されることになりました。いつものことながら邦題から原題に辿りつくのは至難のわざ、直訳すると「おバカたちの長い冒険旅行」ですが、無責任国家や支配階級に騙されつづけている庶民のリベンジ・アドベンチャー。リカルド・ダリンとアルゼンチン映画界の重鎮ルイス・ブランドニが主演のコメディ、2年前の2019年8月15日に公開されるや興行成績の記録を連日塗り替えつづけた作品。本当は笑ってる場合じゃない。公開後ということで、9月にトロント映画祭特別上映、サンセバスチャン映画祭ではアウト・オブ・コンペティション枠で特別上映された。ダリンの息チノ・ダリンがドラマでも息子役を演じ、今回は二人とも製作者として参画しています。

(ドラマでも親子共演のリカルド・ダリンとチノ・ダリン)
*「La odisea de los giles」の作品紹介は、コチラ⇒2020年01月18日
*ボレンステイン監督キャリア&フィルモグラフィー紹介は、コチラ⇒2016年04月30日
*リカルド・ダリンの主な紹介記事は、コチラ⇒2017年10月25日
*チノ・ダリンの紹介記事は、コチラ⇒2019年01月15日
★公式サイトと当ブログでは、固有名詞のカタカナ起しに違いがありますが(長音を入れるかどうかは好みです)、大きな違いはありません。リカルド演じるフェルミンの友人、自称アナーキストのバクーニン信奉者ルイス・ブランドニ、フェルミンの妻ベロニカ・リナス(ジナス)、実業家カルメン・ロルヒオ役のリタ・コルテセ、などのキャリアについては作品紹介でアップしています。悪徳弁護士フォルトゥナト・マンツィ役アンドレス・パラ、銀行の支店長アルバラド役ルチアノ・カゾー、駅長ロロ・ベラウンデ役ダニエル・アラオスなど、いずれご紹介したい。

(監督と打ち合わせ中のおバカちゃんトリオ)
★原作(“La noche de la Usina”)と脚本を手掛けたエドゥアルド・サチェリは、大ヒット作『瞳の奥の秘密』(09)でフアン・ホセ・カンパネラとタッグを組んだ脚本家、ボレンステイン監督とは初顔合せです。大学では歴史を専攻しているので時代背景のウラはきちんととれている。
*『瞳の奥の秘密』の作品紹介は、コチラ⇒2014年08月09日
★作品紹介の段階では、受賞歴は未発表でしたが、おもな受賞はアルゼンチンアカデミー賞2019(助演女優賞ベロニカ・リナス)、ゴヤ賞2020イベロアメリカ映画賞、ホセ・マリア・フォルケ賞2020ラテンアメリカ映画賞、シネマ・ブラジル・グランプリ受賞、ハバナ映画祭2019、アリエル賞2020以下ノミネート多数。

(ゴヤ賞2020イベロアメリカ映画賞のトロフィーを手にした製作者たち)
★ネット配信、ミニ映画祭、劇場公開、いずれかで日本上陸を予測しましたが、一番可能性が低いと思われた公開になり、2年後とはいえ驚いています。公式サイトもアップされています。当ブログでは原題でご紹介しています。
★1都3県の公開日2021年8月6日から順次全国展開、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネマカリテ、ほか。新型コロナウイリスの感染拡大で変更あり、お確かめを。
フェルナンダ・バラデスの 『息子の面影』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑪ ― 2020年11月26日 10:20
豊かなアメリカに一番近い国メキシコの苦悩――メタファーを読みとく

★フェルナンダ・バラデスの『息子の面影』は、北の豊かな大国アメリカに一番近い国メキシコの不幸と苦悩を静かに訴えている。バラデス監督が主役マグダレナにメルセデス・エルナンデスを念頭に脚本を書きすすめていき、メルセデスも台本を見ることなしにオーケーしたという信頼関係が伝わってくる秀作でした。自然の静寂と人間の暴力のコントラスト、秩序の崩壊、自分探しの若者たち、麻薬密売カルテルの恐怖、母親の揺るぎない子供への愛、苦悩するメキシコから届いた苦いクリスマス・プレゼント。2014年9月26日の夜に起きた、メキシコ南部ゲレロ州イグアラ市アヨツィナパ教員養成学校の学生たち43名の謎の失踪事件や、2018年6月に起きたオカンポ市長選挙候補者の射殺事件などが背景にあるようです。本日から配信が開始されたアイ・ウェイウェイのドキュメンタリー『ビボス~奪われた未来』は前者がテーマ、この世界の注目を集めた未解決事件の不条理が今日のメキシコを象徴している。
『息子の面影』(原題「Sin señas particulares」、
英題「Identifying Features」)
製作:Corpulenta Producciones / Avanti Pictures
監督:フェルナンダ・バラデス
脚本:フェルナンダ・バラデス、アストリッド・ロンデロ
撮影:クラウディア・べセリル・ブロス
美術:ダリア・レイェス
編集:フェルナンダ・バラデス、アストリッド・ロンデロ、スーザン・コルダ
録音:ミサエル・エルナンデス、(サウンド・デザイン)オマル・フアレス
音楽:クラリス・ジェンセン(オリジナル・ミュージック)
製作者:フェルナンダ・バラデス、アストリッド・ロンデロ、ジャック・サガ・カバビエ、ヨシー・サガ・カバビエ、ほか
データ:製作国メキシコ=スペイン、スペイン語・サポテコ語・英語、2020年、ドラマ、97分、公開スペイン11月27日、ドイツ12月10日、フランス12月16日
映画祭・受賞歴:SSIFF2019「シネ・エン・コンストルクシオン36」受賞、サンダンス映画祭2020ワールド・シネマ部門観客賞&特別審査員脚本賞、トゥールーズFFシネラテン部門オフィシャル・セレクション、MOOOVE映画祭(ベルギー)ユース賞、カルロヴィ・ヴァリFFオフィシャル・セレクション、平昌ピョンチャンFFグランプリ、サンセバスチャンFFホライズンズ・ラティノ部門オリソンテス・ラティノス賞&スペイン協力賞、ロンドンFF、東京国際FFワールド・フォーカス部門、チューリッヒFF作品賞ゴールデン・アイ賞、モレリアFF観客賞・女優賞・作品賞、テッサロニキFFコンペティション部門、ストックホルムFFコンペティション部門、トリノFFオープニング作品、他インターネット、バーチャルシネマ多数

(オリソンテス・ラティノス賞&スペイン協力賞の賞状を手にした監督、SSIFF授賞式)
キャスト:メルセデス・エルナンデス(マグダレナ)、ダビ・イジェスカス(ミゲル)、フアン・ヘスス・バレラ(メルセデスの息子ヘスス)、アナ・ラウラ・ロドリゲス(オリビア)、アルマンド・ガルシア(リゴ)、ラウラ・エレナ・イバラ(リゴの母チュヤ)、シコテンカティ・ウジョア(リゴの父ペドロ)、ジェシカ・マルティネス・ガルシア(看護師)、リカルド・ルナ(国家公務員)、フリエタ・ロドリゲス(検視官)、ベルタ・デントン・カシーリャス(レヒス)、カルメン・ラモス(レヒスのボイス)、マヌエル・カンポス(アルベルト・マテオ)、アルカディオ・マルティネス・オルテガ(マテオのボイス)、ナルダ・リバス(マテオの孫)、ほか宿泊施設やバス会社の職員、麻薬カルテルのシカリオなどエキストラ多数
ストーリー:マグダレナは2ヵ月前、国境行きのバスに乗ってアメリカに向かったまま連絡の途絶えた息子を探す旅に出る。一緒に出掛けた友人が無言の帰宅をしたからだ。メキシコの寂れた町や静かな自然の中を旅するなかでミゲルと名乗る青年に出会う。アメリカから強制退去されたばかりの青年は、長い不在のあと、母親との再会を求めて故郷オカンポを目指していた。道連れになった二人、一人は愛する息子を探す母親マグダレナ、もう一人は故郷の母親に許しを求めたい青年ミゲル、二人の犠牲者は危険な加害者たちが蔓延している危険地帯を一緒にさまようことになる。たとえ罪びとになろうとも母の深い愛に変わりはない。 (文責:管理人)
★監督紹介:フェルナンダ・バラデス、1981年グアナフアト生れ、監督、脚本、製作、編集。2006年メキシコの映画養成センターCCCに入学、既に26歳とかなり遅い出発だった。2014年、アストリッド・ロンデロと制作会社EnAguas Cineを設立する。ロンデロは本作の共同脚本家・編集者、また美術を手掛けたダリア・レイェスのChulada Films ともコラボしている。製作者としては自身の3作を含めて7作ほどプロデュースしている。代表作がアストリッド・ロンデロのデビュー作「Los días más oscuros de nosotras」(17)である。ボゴタ映画祭2018の作品賞、ロス・カボス映画祭2017のメキシコ賞を受賞している。ロンデロもバルデスの長編デビュー作や短編2作をプロデュースしている。女性作家輩出の胎動を予感させる。現在はメキシコシティに住んでいる。

(バラデス監督と脚本&編集を手掛けた盟友ロンデロ監督、サンダンス映画祭2020にて)
★短編映画デビューは、2010年「De este mundo」(26分)監督、脚本、製作、編集。長編デビュー作のもとになった短編第2作目「400 Maletas」(14、23分、CCC製作)でも監督、脚本、製作、編集を担当、サンティアゴ短編映画祭、サンパウロ・ラテンアメリカ映画祭に出品された。メルセデス・エルナンデスが母親マグダレナ、長編で合衆国から退去させられるミゲルを演じたダビ・イジェスカスが行方不明になるマグダレナの息子に扮している。短編完成後に起きたアヨツィナパ失踪事件に着想を得て脚本を推敲、完成させたのが長編デビュー作である。

(本作とリンクする短編2作目「400 Maletas」のポスター)
★メルセデス・エルナンデスは舞台女優と二足の草鞋を履いている。ラテンビートで上映されたフランシスコ・バルガスの『バイオリン』(05)、ホルヘ・ペレス・ソラノの「La tirisia」ではアリエル賞2015の助演女優賞ノミネート、本作でモレリア映画祭2020の女優賞を受賞している。ほかTVシリーズ出演、アニメのボイス出演もしている。ダビ・イジェスカスは、ビューティフル・ロードムービーと言われた、ディエゴ・ルナの『ミスター・ピッグ』(16)に出ている。これからの俳優です。

(ある決心をしてミゲルの家に戻ろうと帰路を急ぐマグダレナ)

(ミゲルの家の前に佇むマグダレナ、窓際にミゲルの姿、本作から)
2014年のアヨツィナパの謎の集団失踪事件が背景にある
A: 本作はスクリーンで見たい映画、多分印象がかなり変わると感じました。裏で繰り広げられている暴力を無視したように進行のテンポはゆったり、荒涼としたグアナフアトの自然は、母親マグダレナの心象風景のようでした。彼女を取りまく空虚感に胸が塞がる。
B: 静寂そのもののオカンポのダム湖を飛び立つ自由な鳥、風にそよぐ木々や草、人間の不自由さや愚かさが迫ってきます。
A: 本作には上記したように2014年9月26日に突発したアヨツィナパ教員養成学校の学生43名の失踪事件が絡んでいます。真相と称されるものが一転二転して、謎は深まるばかり今もって未解決の事件、政府は解決済みとしたいところだが、犠牲者の家族のみならず国民の大半は納得していない。
B: 配信開始のドキュメンタリー『ビボス~奪われた未来』と合わせてご覧になると、現代メキシコの傷痕の深さが浮き彫りになります。
A: もう一つ、2018年6月のメキシコ中西部ミチョアカン州オカンポ市長選挙中に候補者が射殺された事件もヒントになっている。オカンポという地名は何か所かあり、ミゲルの故郷のオカンポとは別のようです。本作には何本もの柱があって、中心は母親の息子への変わらぬ愛ですが、メキシコが抱える苦悩を背景にしている。
B: 母親は生死が分からなくては生きていくことができない。生きているなら連絡があり、連絡がないならば死んでいると当局は言うが、証拠がなくては受け入れられない。息子ヘススと一緒に国境に向かったリゴは無言の帰宅をした。一緒に死んだなら遺体があるはずだ。ないならどこかで生きてるはず。
A: リゴの父親ペドロは、暮しに困っていたわけでもないのに「自分の人生を探し」に北に行きたいという息子に激怒して、親身に話し合わなかった自分を責める。息子を探しに行くマグダレナを車で国境まで送ってくれる。
B: 母親チュヤは、マグダレナに必要なら使ってとお金を渡す。麻薬密売組織の残虐性と対照的に、市井の人々の優しさが丁寧に挿入されていて、希望のほのかな明かりを感じさせた。

(アリゾナ行を母親に告げるヘスス)

(母親に別れの手を振るヘススとリゴ)

(軽トラで国境までメルセデスを送っていくペドロ)
A: メキシコ人の連帯感は強い。バス会社の受付の年配の男性、移民用の宿泊施設の係官、ボートでダムの対岸まで運んでくれた漁師など、記憶に残る人物を多々登場させている。
B: それに対して若者たちはどうでしょうか。北に向かう理由は経済的理由だけでない、今より少しでも良くなりたい、自分には違う人生があるはずだ、という若者が抱く願望が不幸を呼び込んでいる。常に危険が待ち受けていることを無視している。
A: 最初は身の危険を感じてマグダレナを故郷に帰そうとする人々も、結局は情報を与えてマグダレナを助ける。例えばヘススと同じバスに乗り合わせて生き残った老人マテオの居場所を教えるレヒナの例、カメラは後ろ姿を映すだけで会話は声だけでした。レヒナもさりげなくお茶をすすめるなどゲイが細かい。
B: 風景描写だけでなく室内シーンでも、撮影監督クラウディア・べセリル・ブロスのフレームは素晴らしかった。ボイスにしたのは「壁に耳あり障子に目あり」で、職務上知りえた事実も知らなかったことにする。他言は直ちに危険が身に及ぶという事実を示唆している。
A: 国境地帯では他人を信用してはならないのです。マグダレナはレヒナにとって他人です。次々に身元不明の遺体が運び込まれてくるのが現状です。因みにレヒナのボイス出演をしたカルメン・ラモスは、短編「400 Maletas」に出演、他に当ブログでご紹介したアロンソ・ルイスパラシオスのデビュー作『グエロス』(16)に出ている。
マグダレナ、チュヤ、オリビア、息子を探す3人の母親と父親の不在
B: 冒頭部分で白内障の手術をしているシーンがあり、思わずブニュエルの『アンダルシアの犬』を思い出してしまった。この眼科医が4年前にモンテレイの友人を訪ねると言い残したまま行方不明になった息子ディエゴの母親であることが分かってくる。
A: 眼科医オリビアを演じたアナ・ラウラ・ロドリゲスについては、本作では重要な役柄ですが、IMDbにも載っていなかった。冒頭の4~5分で行方不明の息子を探す3人の母親が出揃う。白内障手術のメタファーは、国民が目を覚ましてほしいという願望がこめられているようだが、シカリオの残虐をとどめるのは、利害が複雑に絡まって絶望的です。

(字の読めないマグダレナを手助けするオリビア)
B: 政治家と警察がカルテルから雁字搦めにされている。アヨツィナパ然り、オカンポ市長候補者殺害然り、調査に入った世界も沈黙させられてしまっている。隣国の大国が絡んでいるから複雑です。
A: ディエゴのように何かの事件に巻き込まれて突然姿を消すことは、ここメキシコでは珍しくない。消息不明のケースもさまざま、合衆国への越境だけが理由ではない。
B: オリビアは、検視官から「2週間前のバス襲撃事件の犠牲者の一人」と説明されるが、焼け焦げた息子の遺体からは識別は難しい。
A: しかしDNA判定が一致したことで自身を納得させるしかない。そうしないと息子を弔うことすらできないからです。マグダレナにもオリビアにも、夫の存在が希薄でした。最後にマグダレナが法的に独身だった事実を観客は知るのですが。
B: ヘスス、ディエゴ、さらにいえばミゲルにも父親が不在だった。父親不在はラテンアメリカ映画の特徴の一つです。

(米国からメキシコに帰国するミゲル)
A: マグダレナが非識字者なのは早い段階で観客に知らされるが、襲撃されたバスに乗り合わせた老人マテオはスペイン語を解さなかった。先住民の言語サポテコ語しか分からない。
B: 主にオアハカ州で話されている言語のようですが地理的には離れている。スペイン語を解さない人口が3%以上いるということですから、相当な数です。
A: ナワトル、マヤ、ミシュテカなどが有名ですが、時間とともに消滅していく言語もある。サポテコ語は国民同士の意思疎通の困難さのメタファーとして挿入されている。
B: 本作では森の中で死体を焼く炎の中から現れる悪魔のシルエットなどメタファーが多い。悪魔は悪の象徴として登場させているのでしょうが、残虐性、秩序の崩壊のシンボルでもある。最後にマグダレナが見る悪魔はどう理解したらよいか、観客に委ねられる。
A: 映画のなかで暴力をただの暴力として描くのは避けたい。私たちはあまりに多くの暴力を目にしていますからストレートな暴力は見たくない。勢い観客の想像力に頼ることになる。
B: 本作では焚火の炎、蝋燭の炎、暖房の炎、車のライトや懐中電灯の灯り、月光などが効果的に使われていました。全体が暗い色調なのでコントラストが際立っていた。半月から満月に移り変わることで時間の流れを表現しているなど、本作は見る人によって感想が違うかもしれない。

(炎の中から立ち現れる悪魔は何を意味しているのか?)
A: 衝撃の結末については、配信中ですからさすがに書けない。しかし注意深くダイヤローグに耳澄ませば、伏線が張ってあるので想像できなくはありません。
マイテ・アルベルディの 『老人スパイ』 鑑賞記*ラテンビート2020 ⑩ ― 2020年11月22日 16:47
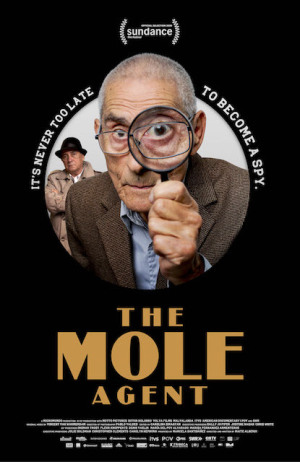
★いよいよ11月20日からオンライン上映が始まりました。東京国際映画祭TIFFで好感を与えた『老人スパイ』から鑑賞、愛すべき老人スパイ、セルヒオの人間味あふれる活躍なくしてこの傑作は生まれなかったでしょう。人間は老いようがボケようが死ぬまで生きがいと尊厳が必要だと泣かされました。作品紹介でも書いたことですが、「フィクションとドキュメンタリーの区別はない、あるのは映画だけ」というマイテ・アルベルディの言葉通りの傑作でした。老いとはいずれ我も行く道なのでした。若干ネタバレしています。便宜上、加筆訂正して出演者とストーリーを再録しました。
*作品紹介&監督キャリアは、コチラ⇒2020年10月22日
出演者:セルヒオ・チャミー(スパイ)、ロムロ・エイトケン(A&Aエイトケン探偵事務所所長)、(以下主な入居者)マルタ・オリバーレス、ベルタ・ウレタ、ソイラ・ゴンサレス、ペトロニタ・アバルカ(ペティータ)、ルビラ・オリバーレス、他にセルヒオの娘ダラルとその家族、サンフランシスコ介護施設長、介護士など多数
ストーリー:A&Aエイトケン私立探偵事務所に、サンティアゴの或る老人ホームに入居している母親が適切な介護を受けているかどうか調査して欲しいという娘からの依頼が舞い込んだ。元犯罪捜査官だったロムロ所長は、ホームに入居してターゲットをスパイしてくれる80歳から90歳までの求人広告を新聞にうつ。スパイとは露知らず応募して臨時雇用されたのが、最近妻に先立たれ元気のなかった御年83歳という好奇心旺盛なセルヒオ・チャミーだった。ロムロはスパイ経験ゼロのセルヒオに探偵のイロハを特訓する。隠しカメラを装備したペンや眼鏡のハイテクはともかく、二人を最も悩ませたのが現代人のオモチャ、スマートフォンの扱い方だった。その理解に充分な時間を費やすことになる。というのもミッションを成功させるには使いこなすことが欠かせないからだ。なんとかクリアーしていざ出陣、ジェームズ・ボンドのようにはいかないが、誠実さや責任感の強さでは引けを取らない。3ヵ月の契約でホームに送り込まれた俄かスパイは、果たしてどんな報告書を書くのだろうか。 (文責:管理人)
老人ホームのオーナーに真相を明かさなかった!
A: チリのドキュメンタリー作家といえば、「ピノチェト三部作」を撮った大先輩パトリシオ・グスマンが直ぐ思い起こされます。『光のノスタルジア』や『真珠のボタン』は、ドキュメンタリーにも拘わらず公開されました。
B: 当ブログではパブロ・ラライン兄弟やセバスティアン・レリオなどのドラマ作品をご紹介していますが、今世紀に入ってから特に活躍目覚ましいのがチリ映画です。
A: 本作を見ると、裾野の広がりを実感します。どこの国にも当てはまりますがドキュメンタリーは分が悪い。そんな中でドキュメンタリーとフィクションの垣根を取っ払っている監督の一人がマイテ・アルベルディです。『老人スパイ』が長編第4作目になります。

(老人スパイのセルヒオ・チャミーとマイテ・アルベルディ監督)
B: 「或る老人ホーム」というのは、チリ中央部に位置するサンティアゴ大都市圏タラガンテ県のコミューン、エル・モンテにある「サンフランシスコ介護施設」というカトリック系の中規模の老人ホームです。まずアイディア誕生、監督とA&Aの接点、介護施設との折衝などの謎解きから入りましょう。
A: 本作はTIFFワールド・フォーカス部門共催作品ですが、来日できない海外の監督とのオンライン・インタビュー「トーク・サロン」が上映後にもたれました。それによると「最初は探偵事務所をめぐるフィルムノワールを撮りたいと、あちこちの探偵事務所に掛け合ったがどこにも断られた。最後に辿りついたのがA&Aだった」と。折よく施設の入居者の娘から「母親がきちんと介護を受けているかどうか調査して欲しい」という依頼がきていた。当てにしていた人物が腰骨を折ったとかで身動きできない。
B: それで例の新聞広告を出すことになった。
A: 監督はもともと介護施設に関心があって、これは渡りに船ではないかと思った。つまり採用されたチャーミングなセルヒオの魅力に参ってテーマを変更したわけです。
B: セルヒオがトレーニングを受けてるシーンに監督の姿がチラリと映っていました。パブロ・バルデスが指揮を執る撮影班は、セルヒオが入居してくるシーンから撮っていたが。
A: ホーム側とは前もって伝統的な手法でドキュメンタリーを撮るという許可を受けていたが、真相は伏せていた。つまりオーナーを騙していたわけです。撮影のガイドラインを決め、ホームのルールに従った。撮影班は今か今かとセルヒオの登場を待っていたのでした。冷や冷やしながら見ていたが、最後までバレなかったというから可笑しい。
B: 変化の少ないホームでは、新入居者は格好の被写体だったから、カメラがセルヒオを追いかけても怪しまれない。それに83歳の新入居者がスパイとして潜入してくると誰が想像しますか。
入居者に必要なのは人間としての尊厳、最大の敵は孤独
A: このドキュメンタリーを見たら老人に対する考え方が変わるかもしれない。観客はセルヒオのお蔭で先入観をもって他人を判断してはいけないことに気づくでしょう。常にチャーミングで寛大、人生に前向き、苦しいときでも笑いは必要というのが本作のメッセージです。
B: バルデスも完成した「映画を見たら泣けたが、撮影中は笑うことのほうが多かった」と。前半と後半ではテーマも微妙に変化していきました。
A: 報告書の合言葉は <小包>、依頼人の母親ソニア・ぺレスを <標的> とか、QTHやらQSLやらのスパイ暗号で四苦八苦するセルヒオにやきもきするロムロだが、後半になると逆に老人の知恵に押され気味になっていくのが痛快だった。
B: ロムロ・エイトケンはインターポール・チリ支部の責任者ですね。人生を重ねていけば誰でもセルヒオのようになれるわけではない。他人に優しくできるには自分に余裕がないとできない。

(セルヒオにスパイのイロハを伝授するA&A所長ロムロ・エイトケン)
A: 4ヵ月前に亡くなったという奥さんは、さぞかし幸せな人生を送っただったろうと思った。違法なスパイ行為をしようとする父親の身を案ずる娘のダラル、幾つになっても人間には生きがいが必要、頭は疲れるが自由になったような気がする、心配するなと説得する父親、このシーンを入れたのもよかった。
B: 反対に <標的> ソニア・ぺレスの娘、クライアントの姿は一度も出さなかった。この判断もよかった。依頼者とは守秘義務の契約を結んでいたと思いますが、結構な金額だったのではないですか。
A: 母親に会いにくればどんな介護を受けているか、ある程度分かること、わざわざ探偵事務所に調査を依頼することはない。娘も病いを得ているのかもしれないが、信頼しあっていた母と娘とは少なくとも思えなかった。
B: 母親の移動は車椅子、単独歩行が無理で自由に出歩けない。気難しく、他人を寄せ付けないどころか、体が触れるのさえ嫌がる。怒りを溜めこんでいるのか、観客は遂に彼女の笑顔を見ることはなかった。
A: セルヒオがなかなか <標的> を見つけられなかったのも、<小包> がロムロに届かなかったのも、理由はソニア側にあった。進行と共にテーマが変化していくのは自然の成り行きでしょう。お蔭で私たちは人生勉強がたくさんできたわけです。老人スパイがどんな報告書を書くかは進行とともに想像できましたね。
辛い人生を受け入れることの難しさ、人生を愉しむテクニック
B: 本作は入居者の一人、セルヒオに愛を告白する85歳のセニョリータ・ベルタと、4人の子供を育て、自作の詩を諳んじるペティータ、それにメノ・ブーレマの3人に捧げられている。
A: ブーレマはアムステルダム出身の映画編集者、監督が2016年に発表した長編ドキュメンタリー第3作め「The Grown-Ups」、スペイン題「Los niños」を手掛けている。本作撮影中の2019年6月に61歳の若さで亡くなった。
B: 一生懸命育てた4人の子供たちからは忘れられ、「人生とは残酷なもの」と呟くペティータも、セルヒオがいる間に神に召されてしまった。お別れの日に読み上げられた彼女の詩は、本作の大きな見せ場でした。
A: 韻を踏んでいるようですが、字幕は英語なので分かりません。「母親が生きているなら、神の愛に感謝しなさい」と始まる詩でした。ペティータが「恩知らず」と嘆いていた4人の子供たちは参列していたのでしょうか。これもターゲットと無関係なエピソードですが、10月5日の開所記念日のユーモア溢れるシーンなど、名場面の数々は皮肉にも標的とは無関係なのでした。

(セルヒオとペティータ)
B: 彼らの青春時代に流行したザ・プラターズの「オンリー・ユー」のメロディーにのってダンスをする入居者たちも忘れられない。
A: 今年のキングに選ばれたセルヒオのパートナーを、施設長がさりげないしぐさで次々と変えていく。皆でお祝いすることが重要、独り占めは御法度です。ターゲットも参加していたのだろうか。
B: 最初のパートナー、セルヒオに恋を告白したセニョリータ・ベルタは、入所して25年ということですから、入居は60歳からになる。ホームでは広場を見渡せる日当たりのいい5つ星の部屋にいてお洒落さん、人生に前向きでソニアとは対照的な女性。セルヒオにお付き合いを断られても直ぐに立ち直る。
A: 心の内は分からないが孤独ともうまく折り合っている。信仰心が支えになって今の人生を受け入れている。女性の入居者は約40人ほどだが目立つ存在でした。

(ベルタとセルヒオ)
B: 認知症がグレーゾーンのルビラ、今は白髪だが若い頃はさぞかし美しかったろう。3人いる子供たちは1年以上会いに来ていない。だから次第に娘の顔もあやふやになってくる。孤独が入居者たちの最大の敵なのです。

(記憶を失う恐怖に怯えるルビラを支えるセルヒオ)
A: マルタは小さい女の子に戻ってしまい母親が迎えに来てくれる日を待っている。不安定になると偽の電話を掛けてやり落ち着かせる。手癖が悪く皆の持ち物を盗んでいるが、直ぐそれも忘れてしまう。
B: マルタの傍にいるソイラは、夫に辛く扱われていたらしくセルヒオの優しさに救われている。男性の友達は今まで一人もいなかったと。

(ソイラ、セルヒオ、マルタ)
A: セルヒオの退所の日の3人の会話に胸が熱くなった。どんな状況に置かれても愛は絶大です。エンディング曲はホセ・ルイス・ペラレスのオリジナル曲「Te quiero」(アイ・ラブ・ユー)をチリのシンガー・ソングライター、マヌエル・ガルシアがカヴァーしている。セルヒオのラスト・リポートは言わずもがなでしょう。ゴヤ賞2021イベロアメリカ映画賞部門のチリ代表作品に選ばれました。
*追加情報:『83歳のやさしいスパイ』の邦題で2021年7月9日公開決定。
ピラール・パロメロのデビュー作*マラガ映画祭2020 ② ― 2020年03月16日 19:14
ビエンナーレに続いてマラガ映画祭にもノミネートされたピラール・パロメロ

★マラガ映画祭2020は、延期か中止かまだはっきりしませんが、取りあえずセクション・オフィシアルの中から話題作をご紹介したい。ピラール・パロメロのデビュー作「Las niñas」(20)は、先だって閉幕したばかりのベルリン映画祭2020「ゼネレーションKplus」部門で既にワールド・プレミアされています。当時からマラガのセクション・オフィシアルにノミネートされていることが分かっていたので、アップを見合わせておりましたが、まさかこんなことになるとは思いませんでした。製作者は第67回ビエンナーレの同じセクションのグランプリ、カルラ・シモンの『悲しみに、こんにちは』(17「Summer 1993」)を手掛けたバレリー・デルピエールです。

(ピラール・パロメロ、マラガFF2020プレス会見、マドリード3月3日)
★ピラール・パロメロ Pilar Palomero は、北スペインのアラゴンの州都サラゴサ出身の監督、脚本家。サラゴサ大学スペイン哲学科卒。2013年、ハンガリーの監督タラ・ベーラ(最後の作品『ニーチェの馬』2011)の指導のもと、サラエボでの「フィルム・ファクトリー」映画監督マスター課程に参加する。短編はワルシャワ映画祭、バルセロナのD'A Film Festival、ウエスカFF、マラガFF、釜山短編FFなどで上映されている。2017年ベルリナーレ・タレント養成の一員に選ばれる。2009年短編「Niño balcón」、2016年「La noche de todas las cosas」、2017年「Horta」など。「Las niñas」が長編デビュー作。
「Las niñas」(「School Girls」)
製作:Inicia Films / Bteam Pictures / Las Niñas Mujeres A.I.E
監督・脚本:ピラール・パロメロ
撮影:ダニエラ・カヒアス
音楽:カルロス・ナヤ
編集:ソフィ・エスクデ
製作者:バレリー・デルピエール
データ:製作国スペイン、スペイン語、2020年、ドラマ、100分、配給Bteam Pictures、インターナショナル販売Film Factory、スペイン公開2020年9月4日予定
映画祭・受賞歴:第70回ベルリン映画祭2020「ゼネレーションKplus」部門ワールド・プレミア、第23回マラガ映画祭2020セクション・オフィシアルに正式出品
キャスト:アンドレア・ファンドス(セリア、11歳)、ナタリア・デ・モリーナ(セリアの母)、ソエ・アルナオ(友人ブリサ)、フリア・シエラ(クリスティナ)、エバ・マガニャ(アリシア)、アイナラ・ニエト(クララ)、エリサ・マルティネス(レイレ)、フランセスカ・ピニョン、他
ストーリー:1992年サラゴサ、11歳のセリアは母親と二人で暮らしている。サラゴサのある修道会の女子高に通っている。セリアは父親を知らない、そのことが友達の噂の種になっている。最近バルセロナから新しい生徒ブリサが編入してきて、新しい世界が開けてくる。スペインの1992年は、バルセロナ五輪とセビーリャ万博があった年だった。セリアは人生が多くの真実といくつかの嘘から成り立っていることを知ることになる。

(11歳の子供の母親役を演じるナタリア・デ・モリーナ)
「セリアは私と類似性がありますがフィクションです」とパロメロ監督
★ベルリナーレのインタビューで「セリアは自分と重なり合う部分がありますが、フィクションで伝記映画ではありません。サラゴサの修道会女子高、ディスコ、トランポリンなどは、私が記憶している部分です。観客がセリアの内部に入り込めるようにエモーショナルな部分をプッシュする筋書にしました。少女時代から思春期のとば口に少しばかり入りかけた女の子の物語です」と語っていた。セリアは父親がいないことで学校では汚名を着せられる。スペインの1992年は、オリンピックと万博という二大イベントがあった年で、大きな変化があった。

(トランポリンに興じるセリアと友人、映画から)
★「当時の女の子が受けていた教育や時代がどのようなものだったか、変えねばならないのは何かについて、映画を観た人が議論してほしい」、現在でもスペインでは男女間の不平等が存在している。「それは多くは表面化していないが、セリアに強いられた従順さ、将来は良妻賢母というメッセージが残響している」と監督。脚本を書き上げたときに、ここには男性の登場人物が多くなかったことに気づいた。「周囲には父親、弟、二人の従兄弟以外、男の子の友達は一人もいなかったからです」と、少女時代の不自然な環境に触れている。2013年、サラエボで体験したタラ・ベーラの教育プロジェクトに参加したことが、大きな転換となった。そこで「映画を撮ろうと自分の方向が決まったのです」と。


(女友達だけで完結していたセリアの狭い世界)
★現在スペインはイタリアに次ぐ新型コロナウイルスの蔓延で、政治も経済も麻痺状態、勿論映画館はオール閉鎖されました。感染者約7900人、死者288人からまた増えて295人と発表されましたが、今後も増え続けるのは必至です。パンデミックはアメリカを含むヨーロッパに中心が移ったようです。欧米諸国のリーダーたちの危機管理の甘さが問われることになる。
追加情報:『スクールガールズ』の邦題で劇場公開決定
東京は2021年09月17日から、新宿シネマカリテにて
ダリン父子が初共演の「La odisea de los giles」*ゴヤ賞2020 ⑬」 ― 2020年01月18日 17:25
イベロアメリカ映画賞にアルゼンチンの「La odisea de los giles」が有力

★アルゼンチン興行成績史上初という快挙を遂げたセバスティアン・ボレンステインの「La odisea de los giles」は、2019年8月15日公開以来過去の記録を更新し続けている。しかしアドベンチャー・コメディ、スリラーなら何でも成功するというわけではない。アルゼンチン人なら誰一人として忘れることができない2001年12月23日の<デフォルト>宣言に始まる<コラリート>を時代背景にしているからです。世界を震撼させた無責任国家の破産を舞台にして、煮え湯を飲まされた住民が反旗を翻す物語、それをリカルド&チノのダリン父子が初共演、ベテランのルイス・ブランドニやリタ・コルテセを絡ませているから、何はともあれ映画館に足を運ばねばならない。第1週380館でスタートしたが、12月半ばには482館、180万枚のチケットが売れたそうです。地元紙は2018年のルイス・オルテガの「El Angel」(『永遠に僕のもの』354館)をあっさり抜いたと報じている。因みにコラリートとは預金封鎖のことで、銀行に預けた自分のお金が引き出せないということです。

(現地入りしたダリン父子とブランドニ、サンセバスチャン映画祭2019フォトコールから)
★個人的には、アルゼンチン国民ほど近隣諸国から嫌われている国はないと考えていますが、このデフォルトによって中間層が貧困層に転落、それは国民の60%近くに及んだという。20世紀初頭には「南米のパリ」ともてはやされたブエノスアイレスも、夜中にゴミあさりをする人たちで、塵一つ落ちていない清潔な街になったと皮肉られた。アルゼンチン経済立て直しと称して、1990年にメネム政権が打ち出した1弗=1ペソ政策は見た目には成功しているかに思われたが、所詮錯覚に過ぎず、厚化粧が剥げれば経済だけでなく政治も社会も三つ巴になってデフォルトに直進した。相続・贈与税がそもそもなく、累進課税制度もないから、富める者はますます富み、貧しい人々はますます貧しくなる構図があり、自分さえよければよいという風潮が蔓延している。見た目と実態がこれほど乖離している国家も珍しい。そういう国で起きた騙されやすいオメデタイ人々が起こしたリベンジ・アドベンチャーです。
「La odisea de los giles」(「Heroic Losers」)2019
製作:Mod Producciones / K&S Films / Kenva Films 協賛:TVE / Televisión Federa(Telefe)
監督:セバスティアン・ボレンステイン
脚本:セバスティアン・ボレンステイン、原作者エドゥアルド・サチェリ
音楽:フェデリコ・フシド
撮影:ロドリゴ(ロロ)・プルペイロ
編集:アレハンドロ・カリージョ・ペノビ
特殊効果:Vfx Boat
録音:ビクトリア・フランサン
製作者:フェルナンド・ボバイラ、ハビエル・ブライア、ミカエラ・ブジェ、レティシア・クリスティ、チノ・ダリン、リカルド・ダリン、シモン・デ・サンティアゴ、Axel Kuschevatzky、他
データ:製作国アルゼンチン、スペイン語、2019年、アドベンチャー・コメディ、スリラー、116分、配給元ワーナーブラザーズ。第92回米アカデミー賞国際映画賞アルゼンチン代表作品(落選)。公開アルゼンチン8月15日、ウルグアイ同22日、パラグアイ同29日、以下ボリビア、チリ、コロンビア、ペルー、ブラジル、メキシコなどラテンアメリカ諸国、スペイン11月29日
映画祭・受賞歴:トロント映画祭2019特別上映、サンセバスチャン映画祭2019正式出品、パルマ・スプリングス映画祭2020外国語映画部門上映、など。
キャスト:リカルド・ダリン(フェルミン・ペルラッシ)、ルイス・ブランドニ(友人アントニオ・フォンタナ)、チノ・ダリン(息子ロドリゴ)、ベロニカ・ジナス(妻リディア)、ダニエル・アラオス(駅長ロロ・ベラウンデ)、カルロス・ベジョソ(爆発物取扱いのプロ、アタナシオ・メディナ)、リタ・コルテセ(実業家カルメン・ロルヒオ)、マルコ・アントニオ・カポニ(カルメンの息子エルナン)、アレハンドロ・ヒヘナ&ギレルモ・ヤクボウィッツJucubowicz(エラディオ&ホセ・ゴメス兄弟)、アンドレス・パラ(弁護士フォルトゥナト・マンツィ)、ルチアノ・カゾーCazaux(銀行家アルバラド)、アイリン・ザニノヴィチ(弁護士秘書フロレンシア)、他
ストーリー:2001年8月、アルシナはこれといった資源もない、アルゼンチン東部の寂れた小さな町である。元サッカー選手だったフェルミンと妻リディアは、廃業したサイロを購入して協同組合を立ち上げ、地域経済の活性化を図ろうと決意する。年長者の友人アントニオ・フォンタナ(自称アナーキストでバクーニンの信奉者)、駅長ロロ・ベラウンデ、実業家カルメン・ロルヒオ、爆発物のエキスパートのアタナシオ・メディナ、ゴメス兄弟などが資金を出し合ってグループ事業を計画する。フェルミンとリディアは、アルシナには銀行がなかったので、銀行家のアルバラドを信用して金庫ごと、近郊のビジャグラン市に運ぶことにする。一方銀行家は彼自身の銀行に金庫の中身を移し替えるよう二人を説得にかかる。果たしてマネーの行方は・・・? 破産させられた住民たちが彼ら独自の方法でリベンジできるチャンスを見つけるが、その方法とは? コラリートを生き延びるために隣人たちが乗り出したアドベンチャーが語られる。 (文責:管理人)
『瞳の奥の秘密』の原作者エドゥアルド・サチェリの小説の映画化
★原作はエドゥアルド・サチェリ(カステラル1967)の小説 ”La noche de la Usina”(2016年刊)の映画化、サチェリは2個目のオスカー像をアルゼンチンにもたらしたフアン・ホセ・カンパネラの『瞳の奥の秘密』(09)の原作者でもあります。大学では歴史学を専攻、現に高校や大学で教鞭を執っているから、時代背景などはきちんと裏が取れている。アルゼンチンの経済危機は1998年から2002年まで、多くの国が煮え湯を飲まされた。IMFの不手際も原因の一つだったから、日本も借金を棒引きして救済したのでした。彼らにしてみれば、返せる能力もない人にお金を貸すほうが悪いというわけで、ぼくたちは悪くない。
★セバスティアン・ボレンステイン(ブエノスアイレス1963)は、2011年のヒット作「Un cuento Chino」(「Chinese Take-Away」)で、リカルド・ダリンの魅力を思う存分引き出した監督。あれはまさにリカルドのための映画だった。アルゼンチン映画アカデミーの作品・主演男優・助演女優賞(ムリエル・サンタ・アナ)を受賞、米アカデミー賞アルゼンチン代表作品にも選ばれた。更にゴヤ賞2012イベロアメリカ映画賞も受賞した。

★コメディとスリラーを交互に撮っている監督は、2015年にスリラー「Kóblic」(スペインとの合作)を撮った。マラガ映画祭2016に正式出品、1977年の軍事独裁政権を時代背景に軍務と良心の板挟みになるコブリック大佐にリカルド・ダリンが扮した。悪玉の警察署長を演じたオスカル・マルティネスが助演男優賞、撮影監督ロドリゴ・プルペイロが撮影賞を受賞した(プルペイロはロドリゴの愛称Roloロロでも表記される)。スペイン側からインマ・クエスタが出演しているが、なかなかマネできないアルゼンチン弁に苦労した。翌年9月『コブリック大佐の決断』でDVDも発売されている。当ブログでは、詳細な監督紹介と時代背景をアップしています。
*監督キャリア&フィルモグラフィーと「Kóblic」の記事は、コチラ⇒2016年04月30日

(『コブリック大佐の決断』撮影中のボレンステイン監督とリカルド・ダリン)
一癖も二癖もあるキャスト陣が大いに興行成績に寄与している?
★新作「La odisea de los giles」出演の顔ぶれを見ると、なかなか味のあるキャスティング、主演のダリン父子は何回か登場してもらっているので、さしあたり自称アナーキストでバクーニンのファンというフォンタナ役を演じたルイス・ブランドニから。1940年ブエノスアイレス州の港湾都市アベジャネダ生れ、俳優で政治家、アルゼンチン映画界の重鎮の一人、UCR(ユニオン・シビカ・ラディカル)党員で国会議員に選ばれている。1962年舞台俳優としてデビュー、翌年TVシリーズ、映画デビューは1966年。1970年代から主役を演じている。1984年のアレハンドロ・ドリアの「Darse cuenta」で主役に起用された。本作は銀のコンドル賞の作品・監督賞他を受賞したことで話題になった。ブランドニはドリア監督の「Esperando la carroza」(85)でも起用されている。『笑う故郷』のガストン・ドゥプラットの「Mi obra maestra」(18)にギレルモ・フランチェラ(ギジェルモ・フランセージャ)と共演している。間もなく80代に突入だが依然として主役に抜擢されている。

(ガストン・ドゥプラットの「Mi obra maestra」から、左側はギレルモ・フランチェラ)
★長寿TVシリーズ「Mi cuñado」(93~96)で2回マルティン・フィエロ賞を受賞、他作でも2回、計4回受賞している。新作ではロシアの哲学者、無政府主義者の革命家ミハイル・バクーニン(1814~76)の信奉者という役柄、日本では教科書で習うだけの思想家バクーニンが、アルゼンチンでは今でもファンがいるというのがミソ、マルクスのプロレタリア独裁に対立した革命家でもあった。
*リカルド・ダリンの主な紹介記事は、コチラ⇒2017年10月25日

(ラテンアメリカから初のドノスティア賞のリカルド・ダリン、SSIFF 2017)

(リカルド・ダリン、ベロニカ・ジナス、ルイス・ブランドニの三人組、映画から)
★チノ・ダリンは、1989年ブエノスアイレスのサン・ニコラス生れ、俳優、最近父親リカルド・ダリンが主役を演じたフアン・ベラの「El amor menos pensado」で製作者デビューした。本作はSSIFF2018のオープニング作品である。映画デビューはダビ・マルケスの「En fuera de juego」(11)、本邦登場はナタリア・メタの『ブエノスアイレスの殺人』(「Muerte en Buenos Aires」14)の若い警官役、ラテンビートで上映された。翌年韓国のブチョン富川ファンタスティック映画祭で男優賞を受賞した。続いてディエゴ・コルシニの「Pasaje de vida」(15)で主役に抜擢されるなど、親の七光りもあって幸運な出発をしている。他にルイス・オルテガの「El Angel」(18、『永遠に僕のもの』)、ウルグアイの監督アルバロ・ブレッヒナーの『12年の長い夜』で実在した作家でジャーナリストのマウリシオ・ロセンコフを演じた。役者としての勝負はこれからです。
* 他にチノ・ダリンの紹介記事は、コチラ⇒2019年01月15日

(劇中でも父子を演じたリカルド&チノ・ダリン親子、映画から)
★女優軍は、フェルミンの妻リディア役のベロニカ・ジナス、1960年ブエノスアイレス生れ、女優、舞台、TVシリーズで活躍、映画監督、舞台演出家でもある。父は最近癌で鬼籍入りした作家のフリオ・ジナス、母は若くして癌に倒れた画家のマルタ・ペルフォ、映画監督のマリアノ・ジナス(1975)は実弟。自らラウラ・シタレラと共同監督・主演した「La mujer de los perros」(15)撮影中に夫も癌で亡くしている。本邦では馴染みがないなかで、サンティアゴ・ミトレの『パウリナ』に出演している。コメディ出演が多いが、マルティン・フィエロ賞をコメディとドラマ部門で受賞、銀のコンドル賞も受賞するなどの演技派です。

(デフォルトのニュースを聞いて気絶する夫フェルミンを支える妻リディア)

(監督&主演した「La mujer de los perros」から)
★実業家カルメン・ロルヒオ役のリタ・コルテセは、ダミアン・ジフロンの『人生スイッチ』で、同僚のウエートレスの家族を破滅に追い込んだお客に猫いらず入りの料理を出して殺害しようとする料理女(ゴリラ)、塀の中体験者で「刑務所暮らしのほうがシャバより余程まし」とうそぶく、アルゼンチンの社会的不公平を逆手にとって金持ちに復讐する迫力満点の料理人を演じた。パウラ・エルナンデスの『オリンダのリストランテ』(01、08年公開)で主役のオリンダに扮した。ここでも料理をしていた(笑)。物言う女優の一人、リタ・コルテセについては別の機会にご紹介したい。

(カルメン・ロルヒオ役のリタ・コルテセ)

(料理人に扮したリタ・コルテセ、『人生スイッチ』から)
★その他の出演者たち、アレハンドロ・ヒヘナ&ギレルモ・ヤクボウィッツが扮したゴメス兄弟、アンドレス・パラが扮したマンツィなど。


★いずれ何かの形で、つまりネット配信、ミニ映画祭、劇場公開、DVDなどで字幕入りで観られる機会があるのではないでしょうか。
*追加情報:邦題『明日に向かって笑え!』で公開されました。
コロンビア映画 『猿』 鑑賞記*ラテンビート2019 ⑮ ― 2019年12月06日 17:35
アレハンドロ・ランデスの第3作目『猿』――背景はコロンビア内戦

★アレハンドロ・ランデスの第3作目『猿』は、年初に開催されるサンダンス映画祭2019「ワールド・シネマ・ドラマ」部門で審査員特別賞を受賞して以来、国内外の映画祭にノミネートされ作品賞または観客賞などのトロフィーを手にしている。当ブログではサンセバスチャン映画祭SSIFF「ホライズンズ・ラティノ」部門にノミネートされた折り、原題「Monos」で監督及び作品紹介をしております。製作国はコロンビアの他、アルゼンチン、オランダ、デンマーク、スウェーデン、独、ウルグアイ、米の8ヵ国。第92回米アカデミー賞国際長編映画賞、ゴヤ賞2020イベロアメリカ映画賞のコロンビア代表作品。
*「Monos」のオリジナル・タイトルでの紹介記事は、コチラ⇒2019年08月21日

(アレハンドロ・ランデス監督)
主なキャスト:ジュリアンヌ・ニコルソン(ドクター、サラ・ワトソン)、モイセス・アリアス(パタグランデ、ビッグフット)、フリアン・ヒラルド(ロボ、ウルフ)、ソフィア・ブエナベントゥラ(ランボー)、カレン・キンテロ(レイデイ、レディ)、ラウラ・カストリジョン(スエカ、スウェーデン人)、デイビー・ルエダ(ピトゥフォ)、パウル・クビデス(ペロ、ドッグ)、スネイデル・カストロ(ブーンブーン)、ウィルソン・サラサール(伝令、メッセンジャー)、ホルヘ・ラモン(金探索者)、バレリア・ディアナ・ソロモノフ(ジャーナリスト)、他
ストーリー:一見すると夏のキャンプ場のように見える険しい山の頂上、武装した8人の若者ゲリラ兵のグループ「ロス・モノス」が、私設軍隊パラミリタールの軍曹の監視のもと共同生活を送っている。彼らのミッションは唯一つ、人質として拉致されてきたアメリカ人ドクター、サラ・ワトソン逃亡の見張りをすることである。この危険なミッションが始まると、メンバー間の信頼は揺らぎ始め、疑心暗鬼が芽生え、次第にサバイバルゲームの様相を呈してくる。(102分)
自国の内戦を描く――『蠅の王』にインスパイアーされて
A: アレハンドロ・ランデスはサンパウロ生れ(1980)ですが、父親はエクアドル出身、母親がコロンビア人ということです。コロンビア公開(8月15日)時に監督自身が語ったところによると「戦争映画はベトナムは米国が、アフリカはフランスが撮っているが、自分たちはコロンビアの戦争をコロンビア人の視点で作る必然性があった」と語っていました。
B: コロンビアの戦争というのは、20世紀後半から半世紀以上も吹き荒れたコロンビア内戦のこと、南米で最も危険なビオレンシアの国と言われた内戦のことです。
A: この内戦は、反政府勢力コロンビア革命軍FARC誕生の1966年から和平合意の2016年11月までの約半世紀を指しますが、麻薬密売が資金源だったことで麻薬戦争とも言われています。現在でも500万人という国内難民が存在しているという。
B: 丁度ノーベル賞の季節ですから触れますと、和平合意に尽力したことでサントス大統領が2016年のノーベル平和賞を受賞した。随分昔のように感じますが、ついこないだのことです。
A: ラテンビート上映後、フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』の原作となったジョセフ・コンラッドの『闇の奥』(1902刊)を思い出したとツイートしている方がおられました。しかしコンラッドの原作にあるような「心の闇」は皆無とは言わないが希薄だったように思いました。
B: 社会と隔絶された山奥、登場人物を若者グループにするなど、舞台装置はウィリアム・ゴールディングの『蠅の王』(1954刊)を思い起こさせた。しかし少年たちは飛行機事故をきっかけに偶然太平洋上の無人島でサバイバルゲームを余儀なくされるわけで、そもそもの発想が異なる。
A: 対立や裏切り、一見民主的に見えるリーダーの選出法、殺人機械になるための訓練など、閉塞された空間にいる人間の暗部を描いている点は同じです。あちらは豚の生首、こちらは乳牛シャキーラと異なるけど。(笑)
B: 大切な乳牛の世話もできない幼稚さ愚かさ、それが引き金になってリーダーのロボ(フリアン・ヒラルド)の自殺、伝令(ウィルソン・サラサール)への保身の嘘が始りで、グループは崩壊への道を歩むことになる。
A: ナンバー2のパタグランデ(モイセス・アリアス)の出番、リーダーを2人設定したのも小説と似ています。監督は影響を認めつつも「インスパイアーされた」と語っている。以前から「若者を主役にして戦闘やメロドラマを盛り込んだ目眩を起こさせるようなセンセショーナルな作品を探していた。私たちの映画にはあまり観想的ではなくてもアドレナリンは注入したかった。ジャンル的には戦闘とアクションを取り込んで、観客は正当性には駆られないだろうから、皮膚がピリピリするようなものにしたかった」とランデス監督は語っていた。
B: 目眩は別としてアドレナリンはどくどくだった。メロドラマというのはリーダーのロボ(ウルフ)とレディ(カレン・キンテロ)の結婚、ウルフ亡き後のランボーとの性愛などですか。

(新リーダーになるパタグランデ役のモイセス・アリアス)

(レディ役のカレン・キンテロ)
A: ランボーを演じた丸刈りのソフィア・ブエナベントゥラは映画初出演、まだ大学生とのこと。男性に偽装しているレズビアンか、両性具有なのか映画からはよく分からなかった。ベルリン映画祭パノラマ部門で上映されたとき受賞はならなかったがLGBTを扱った映画に贈られる「テディー賞」の対象作品だった。サンセバスチャン映画祭では同じ性格の賞「セバスチャン賞」を受賞している。
B: ブエナベントゥラは、ニューポート・ビーチ映画祭で審査員女優賞を受賞している。8人の中で心の闇を抱えている複雑な役柄を演じて、記憶に残るコマンドだった。彼女のように戦闘に疑問を感じる逃亡者は当然いたわけで、拾われた金探索者の家族とテレビを見るシーンが印象的だった。この家族のように紛争に巻き込まれた犠牲者はあまたいたわけで、その象徴として登場させていた。

(ランボー役のソフィア・ブエナベントゥラ)

(左から、ウィルソン・サラサール、モイセス・アリアス、ランデス監督、
ソフィア・ブエナベントゥラ、ベルリン映画祭2019のフォトコールから)
A: 人質の米人サラ・ワトソンの救出劇は、2008年のヘリコプター使用のイングリッド・ベタンクールと3人のアメリカ人救出劇を彷彿とさせた。FARC側の短波通信網に偽の情報を流して混乱させ救出を成功させた。国土はブラジルに次いで広く、多くが険しい山岳やアマゾンのジャングル地帯、有効なのは短波通信だけでした。
B: パタグランデたちが従っている自分たちには顔の見えない指令機関からの独立を宣言する。通信手段のラジオを破壊して通信網を遮断するが、それが命取りになる。戦闘部隊は細分化され小型化され、彼らのように消滅していった。
脚本を読んだ瞬間に魅せられコロンビアにやって来た――J.ウルフ撮影監督
A: 映画はコロンビア中央部のクンディナマルカ県、アンデス山系東部に位置する標高4020メートルのパラマ・デ・チンガサ頂上の雲の上から始まり、カメラはジャングルの奥深く移動する。冒頭で二つの舞台でドラマが展開することを観客に知らせる見事な導入でした。ジャスパー・ウルフの映像は批評家のみならず観客をも魅了した。
B: その厳しさ険しさから現地に撮影隊が入ったのは初めてだそうです。
 (冒頭部分の映像から)
(冒頭部分の映像から)

A: ゲリラ兵の掩蔽壕があるパラモ・デ・チンガサは美しく別世界のようであったが、荒々しく寒く、天候は気まぐれで、目まぐるしく晴、雨、霧の繰り返し、反対にサマナ・ノルテ川のジャングル地帯は高温多湿で蒸し暑く、流れも早かったとウルフは語っています。
B: スエカ(ラウラ・カストリジョン)と彼女の監視下に置かれた人質ドクター(ジュリアンヌ・ニコルソン)が激流の中で争うシーンから想像できます。

(人質サラ・ワトソン役のジュリアンヌ・ニコルソン)
A: あのシーンの「視覚的なインパクトは象徴的な力から得られます」とウルフは語っている。かなりの急流で演じるほうも残酷な条件だったろうと思います。


(視覚的なインパクトのあった水中シーンから)
B: コロンビア人ではなくオランダ人の撮影監督ということですが、キャリアとかランデス監督との接点は?
A: 生年は検索できませんでしたが、アムステルダム大学(1994~96)とオランダ映画アカデミー(1997~01)で撮影を学んでいますから1970年代後半の生れでしょうか。本作がニューポート・ビーチFFで審査員撮影賞を受賞していますが、既にオランダ映画祭2011でポーランド出身ですがオランダで活躍しているUrszula Antoniakの「Code Blue」でゴールデンCalf賞を受賞している。二人の接点は、同じ年のワールド・シネマ・アムステルダムにランデス監督が出品した長編劇映画としてはデビュー作になる「Porfirio」が、審査員賞を受賞している。
B: あくまで憶測の域を出ませんね。脚本を読んだ瞬間に魅せられて、ジャスパー・ウルフは即座にコロンビアへの旅を決心したと語っています。ランデスがあらかじめ準備したショットリストを土台にして進行し、「私たちは大胆で、怖れ知らず」だったとも。
A: 最初に考えていたステディカムの使用を再考して、構図も厳格に、俳優にできるだけ近づき彼らの目や体から放射されるエネルギーを吸収することに専念した。
B: 山頂のシーンでは、広角シネマスコープで撮影しており、暗い場所での撮影ではレンズの絞りを調整していた。これからの活躍が楽しみな撮影監督でした。

(山頂で戦闘訓練をする8人のコマンドと伝令のウィルソン・サラサール)
若いゲリラ兵の視点と感情で描いた主観的な戦争寓話
A: 極寒の地の厳しささのなかで、武器を持たされ軍事訓練を受ける若者のグループは、ついこの間までコロンビアに吹き荒れていた内戦のドラマ化と容易に結びつく。
B: あくまでフィクション、監督の主観的な戦争寓話として提出されている。
A: 音楽のミカ・レビはロンドン生れ。ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭BAFICI でオリジナル音楽賞を受賞している。パブロ・ララインの『ジャッキー ファーストレディ 最後の使命』を手掛けており、バイオリニストでもある。
B: ベルリン映画祭にはスタッフも大勢参加しており、監督を含めて4人のプロデューサー、編集も手掛けるベテランのフェルナンド・エプスタイン、長編デビューのサンティアゴ・サパタ、本作デビューのクリスティナ・ランデス、などがフォトコールされていた。
 (音楽監督ミカ・レビ)
(音楽監督ミカ・レビ)
A: これからも受賞歴が追加されていくでしょう。ゴヤ賞2020もポルトガルを含めてイベロアメリカ映画賞部門の各国代表作品は出揃いましたが、現在のところ最終候補は発表されておりません。今年は例年より早まって、1月25日(土)マラガ開催、総合司会は昨年と同じシルビア・アブリル&アンドレウ・ブエナフエンテのカップルがアナウンスされています。
訂正:12月2日ノミネーションが発表になっていました。ラテンビート上映からは、『猿』と『蜘蛛』が入りました。次回全体をアップします。
追加情報:2021年10月30日『MONOS 猿と呼ばれし者たち』の邦題で公開されました。
グアテマラ映画 『ラ・ヨローナ伝説』 *東京国際映画祭2019 ④ ― 2019年10月20日 18:25
ハイロ・ブスタマンテの第3作『ラ・ヨローナ伝説』がコンペティション部門上映

★デビュー作『火の山のマリア』(15)が公開され、本邦でも幸運なスタートを切ったハイロ・ブスタマンテの第3作目『ラ・ヨローナ伝説』(「La Llorona」)がコンペティション部門にノミネートされました。当ブログではサンセバスチャン映画祭2019「ホライズンズ・ラティノ部門」で第2作目「Temblores」を紹介、第3作はクロージング作品ではあったがコンペ外ということで割愛しました。ラテンアメリカ諸国で現在に至るまで語り継がれてきた「ラ・ヨローナ(泣く女)」の伝説を取り込んで、1980年代グアテマラに吹き荒れた先住民ジェノサイドを告発する社会派スリラーです。いわゆるファンタジー・ホラーではないが、その要素を内包しながら、30年後によみがえる先住民女性たちの復讐劇でもあるようです。

(ハイロ・ブスタマンテ監督、ベネチア映画祭2019「ベニス・デイズ」にて)
*デビュー作『火の山のマリア』の作品紹介は、コチラ⇒2015年08月28日/10月25日
*第2作「Temblores」の監督キャリア&作品紹介は、コチラ⇒2019年08月19日
『ラ・ヨローナ伝説』(「La Llorona」「The Weeping Woman」)2019年
製作:El Ministerio de Cultura Y Deportes de Guatemala / La Casa de Producción / Les Films du Volcan
監督・脚本:ハイロ・ブスタマンテ
撮影:ニコラス・ウォン
音楽:パスクアル・レイェス
編集:ハイロ・ブスタマンテ、グスタボ・マテウ
プロダクション・デザイン:セバスティアン・ムニョス
助監督:メラニー・ウォルター
製作者:ハイロ・ブスタマンテ、グスタボ・マテウ、その他
データ:製作国グアテマラ=フランス合作、スペイン語、マヤ語(カクチケル、イシル)、2019年、スリラードラマ、97分
映画祭・受賞歴:ベネチア映画祭2019「ベニス・デイズ」出品、作品賞Fedeora賞、GdA監督賞受賞、トロントFF、ミラノFF、エル・グーナFF(エジプト)、ベルゲンFFシネマ才能賞受賞、サンセバスティアンFF「ホライズンズ・ラティノ部門」ヨーロッパ⋍ラテンアメリカ協業作品賞受賞、チューリッヒFF「ヒューチャー・フィルム部門」、ロンドンFF、ヘントFF、シカゴFF、東京国際FFコンペティション部門、ストックホルムFFなど各映画祭に出品または出品予定。
キャスト:マリア・メルセデス・コロイ(アルマ)、サブリナ・デ・ラ・ホス(ナタリア)、マルガリタ・ケネフィック(カルメン)、フリオ・ディアス(退役将軍エンリケ・モンテベルデ)、マリア・テロン(バレリアナ)、フアン・パブロ・オリスラガーOlyslager(レトナ)、アイラ・エレア・ウルタド(サラ)、ペドロ・ハビエル・シルバ・リラ(警察官)、他
ストーリー:「お前が泣けば殺してしまうよ」という言葉が耳に響いてくる。アルマと彼女の子供たちはグアテマラの武力紛争で殺害された。そして30年後、ジェノサイドを指揮した退役将軍エンリケに対する刑罰訴訟の申立てが開始された。しかし裁判は無効となり、彼は無罪放免となった。ラ・ジョローナの魂は解き放たれ、生きている人々のあいだを彷徨い歩く亡霊のようになった。ある夜のこと、エンリケは泣き声を耳にするようになる。妻と娘はエンリケがアルツハイマー認知症になったのではないかと疑い始める。新しく雇われた家政婦アルマは、正義がなされなかった復讐を果たすためエンリケの家にやって来たのだ。1982年から83年にかけて、1ヵ月に3000人のペースでマヤ族を殺害したという先住民ジェノサイドを告発する社会派スリラー。
グアテマラ先住民ジェノサイドとジョローナ伝説のメタファー
★36年間吹き荒れたグアテマラの武力抗争(1960~1996)は、最初はイデオロギー対立で始まったのだが、ある時期からマヤ先住民ジェノサイドに変容する。それが1970年代終りから80年代前半にあたり、当時の指揮官がリオス・モント将軍、作品ではエンリケ・モンテベルデ将軍、約20万人とも調査が進むなかで25万人ともいわれる犠牲者のうち15万人が、この時期に集中して殺害されたという。うち女性が5分の4というのが何を意味するのか、ジェノサイドといわれる所以です。30年後というのが現在を指すようです。同胞セサル・ディアスの「Nuestras madres」(カンヌFFカメラドール受賞)も同時代を背景に同じテーマを扱っている。まだ真相は解明されたとは言えず、真の意味の和解はできていない。社会再生への道程は長い。
*セサル・ディアスの「Nuestras madres」の紹介記事は、コチラ⇒2019年05月07日

(エンリケの自宅前で抗議の声を上げる女性たち、映画から)
★マヤ語は21種類あり、本作で使用されたカクチケル語は、『火の山のマリア』でも使用されていた比較的話者の多いマヤ語の一つ。マヤ語使用者が人口の60%あるというのもジェノサイドの遠因の一つかもしれない。ラテンアメリカ諸国に生き残っている <ラ・ヨローナ伝説> は、メキシコから南米のアルゼンチン、チリまで、国によって、地域によって少しずつ異なるが存在する。表記は <ジョローナ伝説> のほうが一般的かと思われる(llo-の発音は地域によって違いがあるが、リョあるいはジョに近い)。ストーリーにも違いがあり、共通項は女性が高位の男性に思いを寄せ子供を生むが、いずれ捨てられて子供を水辺に沈めて自分も死のうとするが死にきれず、後悔と自責の念に駆られて彼の世と此の世を亡霊のように彷徨うというもの。水辺は川、湖、海などのバリエーションがあり、女性は先住民、女性より高位の男性とはヨーロッパから来た白人というケースが多い。この伝説のメタファーは簡単ではない。

(映画『ラ・ヨローナ伝説』から)
★キャスト陣に触れると、アルマ役のマリア・メルセデス・コロイは、『火の山のマリア』で主役のマリアを演じたほか、メキシコのTVシリーズ「Malinche」で征服者コルテスの通訳マリンチェを演している。メキシコではマリンチェは同胞を裏切りスペイン側についた極悪人の烙印を押されていたが、昨今では当然のことながら再評価が行われている。マリンチェはコルテスに献上された贈り物で、裏切りの代名詞とはかけ離れている。アステカ王国のナワトル語、マヤ語、スペイン語を駆使した聡明な女性で、コルテスとのあいだに男児を設けているが認知されていない。彼女も子殺しはしなかったがラ・ジョローナの一人である。他にこの秋公開されるポール・ワイツの『ベル・カント とらわれのアリア』(18、米国)でテロリストの一人になる。渡辺謙やジュリアン・ムーアとの共演はプラスに働くだろう。

(アルマ役のマリア・メルセデス・コロイ、映画から)
★『火の山のマリア』でマリアの母親を演じたマリア・テロンは、数少ないプロの女優の一人だった。先住民の知識に乏しかったブスタマンテ監督にマヤの文化や伝統を伝える役目を果たして脚本の書き直しに寄与している。またカクチケル語とスペイン語ができたことから、監督とスペイン語を解さない出演者たちのまとめ役でもあった。第2作目「Temblores」とブスタマンテ全作に出演している。

(家政婦アルマのマリア・メルセデス・コロイとマリア・テロン、映画から)

(マリア・テロンとマリア・メルセデス・コロイ、『火の山のマリア』から)
★「Temblores」の主任司祭役で映画デビューしたサブリナ・デ・ラ・ホスは、そのスタニスラフスキー・メソッド仕込みの演技力で注目を集めている。エンリケの娘ナタリアは教養の高い医師、父親の過去を知って苦しむ。プロの体操選手になることが夢だった少女は、長じてアートに目覚め体操を断念、ジョージア州のサヴァンナ大学で芸術史を専攻、かたわら写真、グラフィックデザインも学ぶ。ジョージア、アトランタ、グアテマラ、パナマなどでデザイナーの仕事をしているが、スタニスラフスキー・メソッドも学んでいる。2作品の出演だから評価はこれから。

(エンリケの娘ナタリア役のサブリナ・デ・ラ・ホス、映画から)

(ベルリン映画祭2019「Temblores」のサブリナ・デ・ラ・ホス)
★エンリケ・モンテベルデ将軍役のフリオ・ディアスは本作で映画デビュー、フアン・パブロ・オリスラガーは、「Temblores」の主役パブロを演じた俳優、ペドロ・ハビエル・シルバ・リラも「Temblores」にバーテンダー役で出演しているなど、両作に出演している俳優が多い。

(エンリケ将軍役フリオ・ディアスを採用したポスター)
★編集と製作を監督と共同で手掛けたグスタボ・マテウは、監督、脚本家、編集者、製作者。『火の山のマリア』の配給を手掛けている。本作の製作を担当した La Casa de Producciónの総マネジャーとして、ブスタマンテ監督と共に働いている。ベネチア映画祭2019「ベニス・デイズ」に授賞式まで残り、GdA(Giornate degli Autori)監督賞受賞(副賞2万ユーロ)のトロフィーを代わりに受け取った。

(GdA監督賞受賞のトロフィーを手にしたグスタボ・マテウ)
★TIFF での上映は3回、10月31日、11月3日、11月5日、チケット発売中。ハイロ・ブスタマンテ監督が来日、Q&Aがアナウンスされている。
追記:2020年7月、『ラ・ヨローナ~彷徨う女~』の邦題で公開されました。
コロンビア映画「Monos」*サンセバスチャン映画祭2019 ⑬ ― 2019年08月21日 16:03
ホライズンズ・ラティノ第3弾――アレハンドロ・ランデスの第3作「Monos」

★先日、ホライズンズ・ラティノ部門のラインナップをした折に、ウィリアム・ゴールディングの『蠅の王』(1954刊)の映画化とコメントしましたが、アレハンドロ・ランデスの「Monos」は、『蠅の王』にインスパイアされたが近い。過去にピーター・ブルック(63)とハリー・フック(90)の手で2回映画化されていますが、こちらは文字通り小説の映画化でした。最新ニュースによると、3度目の映画化をルカ・グァダニーノに交渉中という記事を目にしました。話題作『君の名前で僕を呼んで』の監督、実現すればどんな料理に仕上がるのか興味が湧く。
★アレハンドロ・ランデス(サンパウロ1980)は、監督、製作者、脚本家、ジャーナリスト。サンパウロ生れだが、父親がエクアドル人、母親がコロンビア人で、母語はスペイン語である。米国ロード・アイランドの名門ブラウン大学で政治経済を専攻した。ボリビア大統領エボ・モラレスについてのドキュメンタリー「Cocalero」でデビュー、本作はラテンビートLBFF2008で『コカレロ』の邦題で上映された。第2作の「Porfirio」は、カンヌ映画祭併催の「監督週間」に出品、その後トロントFFやメリーランドFFでも上映された。警察の不用意な発砲で下半身不随になったポルフィリオ・ラミレスの車椅子人生が語られる。本作はフィクションだが、本人のたっての希望でラミレス自身が主役ポルフィリオを演じている。第3作となる「Monos」は、製作国がコロンビアを含めて6ヵ国と、その多さが際立つ。米国アカデミー2020のコロンビア代表作品候補となっている。
「Monos」
製作:Stela Cine / Bord Cadre Films / CounterNarrative Films / Le Pacte 以下多数
監督:アレハンドロ・ランデス
脚本:アレハンドロ・ランデス、アレクシス・ドス・サントス
撮影:ジャスパー・ウルフ
音楽:ミカ・レビ
編集:テッド・グアルド、ヨルゴス・マブロプサリディス、サンティアゴ・Otheguy
製作者:アンドレス・カルデロン、J. C. Chandor、Charies De Viel Castel、ホルヘ・イラゴリ、Duke Merriman、グスタボ・パスミン、ジョセフ・レバルスキ、グロリア・マリア(以上エグゼクティブ)、アレハンドロ・ランデス、クリスティナ・ランデス、他多数
データ:製作国コロンビア=アルゼンチン=オランダ=ドイツ=スイス=ウルグアイ、スペイン語・英語、2019年、スリラー・ドラマ、102分、コロンビア公開2019年8月15日、他イタリア(7月11日)、以下オランダ、米国、イギリス、スウェーデン、ノルウェー、フランスなどがアナウンスされている。
映画祭・映画賞:サンダンスFFワールド・シネマ・ドラマ部門審査員特別賞、ベルリンFFパノラマ部門上映、BAFICI オリジナル作曲賞、アート・フィルム・フェスティバル作品賞ブルー・エンジェル受賞、カルタヘナFF観客賞・コロンビア映画賞、ニューポート・ビーチFF作品賞以下4冠、オデッサFF作品賞、トゥールーズ・ラテンアメリカFF CCAX賞、トランシルヴァニアFF作品賞などを受賞、ノミネーションは割愛
キャスト:ジュリアンヌ・ニコルソン(ドクター、サラ・ワトソン)、モイセス・アリアス(パタグランデ、ビッグフット)、フリアン・ヒラルド(ロボ、ウルフ)、ソフィア・ブエナベントゥラ(ランボー)、カレン・キンテロ(レイデイ、レディ)、ラウラ・カストリジョン(スエカ、スウェーデン人)、デイビー・ルエダ(ピトゥフォ)、パウル・クビデス(ペロ、ドッグ)、スネイデル・カストロ(ブーンブーン)、ウィルソン・サラサール(伝令)、ホルヘ・ラモン(金探索者)、バレリア・ディアナ・ソロモノフ(ジャーナリスト)、他
ストーリー:一見すると夏のキャンプ場のように見える険しい山の頂上、武装した8人の少年ゲリラ兵のグループ「ロス・モノス」が、私設軍隊パラミリタールの軍曹の監視のもと共同生活を送っている。彼らのミッションは唯一つ、人質として誘拐されてきたアメリカのドクター、サラ・ワトソンの世話をすることである。この危険なミッションが始まると、メンバー間の信頼は揺らぎ始め、次第に疑いを抱くようになる。 (文責:管理人)

(ロス・モノスに囲まれた拉致被害者サラ・ワトソン役ジュリアンヌ・ニコルソン)
コロンビアの半世紀に及ぶ内戦についての出口なしのサバイバルゲーム
★ストーリーから直ぐ連想されるのは、20世紀後半のコロンビアに半世紀以上も吹き荒れた内戦の傷である。比較されるのはフランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』の原作となったジョセフ・コンラッドの『闇の奥』(1902刊)であろうが、原作にあるような「心の闇」は希薄のようです。本作は目眩やアドレナリンどくどくでも瞑想的ではないようだ。社会と隔絶された場所、登場人物の若者グループなど舞台装置は、ウィリアム・ゴールディングの『蠅の王』を思い出させる。極寒の地の厳しさのなかで、武器を持たされ軍事訓練を受ける若者のグループは、ついこの間まで存在していたコロンビアに容易に結びつく。


(8人の武装グループ「ロス・モノス」と軍曹)
★コロンビア公開に際して受けたインタビューで、前から「若者を主役にして戦闘やメロドラマを織り込んだ目眩を起こさせるようなセンセショーナルな作品を探していた。私たちの映画はあまり観想的ではなくてもアドレナリンは注入したかった。ジャンル的には戦闘とアクションを取り込んで、観客は正当性には駆られないだろうから、皮膚がピリピリするようなものにしたかった」とランデス監督は語っていた。戦争映画はベトナムは米国が、アフリカはフランスが撮っているが、自分たちはコロンビア人の視点で自国の戦争映画を作る必然性があったとも語っている。

(アレハンドロ・ランデス監督)
★登場人物たちの名前も、政治的に左か右か分からなくてもかまわない。「イデオロギー・ゼロを観客に放り投げたかった。所詮世界は非常に偏向して、富も理想も違いすぎている。エモーションを通して揺さぶろうとするなら、どんなメタファーが有効かだ」、「何を語るかだけでなくどう語るか」、『蠅の王』や『闇の奥』が出発点にあったようです。
★キャスト陣のうち、ドクター役のジュリアンヌ・ニコルソン(マサチューセッツ州メドフォード1971、代表作『薔薇の眠り』『8月の家族』)とパタグランデ役のモイセス・アリアス(ニューヨーク1994、代表作SFアクション『エンダーのゲーム』、「The King of Summer」)は、アメリカの俳優、スエカ役のラウラ・カストリジョンはスペインのTVシリーズに出演している。金探索者のホルヘ・ラモンはルクレシア・マルテルの『サマ』に出演している。そのほかは本作が2作目か初出演。
*追加情報:ラテンビート2019で『猿』の邦題で上映が決定しました。
*追加情報:2021年10月30日『MONOS 猿と呼ばれし者たち』の邦題で公開されました。
ハビエル・フェセルの 『チャンピオンズ』*スペイン映画祭2019 ② ― 2019年07月01日 17:16
スペイン映画祭2019――インスティトゥト・セルバンテス東京主催

★インスティトゥト・セルバンテス東京のスペイン映画祭2019(6月25日~7月2日)が開催され、うち5作を鑑賞しました。期待通りの作品、それほどでもなかった作品などもありましたが、うち年内に公開が予定されているハビエル・フェセルの『チャンピオンズ』(原題「Campeones」)はお薦め作品です。当日の上映後には、スカイプでフェセル監督とのインタビューもありました。1年ほど前に公開を期待して作品&監督キャリア紹介をしておりますが、以下にストーリーとキャスト紹介を訂正加筆して再録、改めてその魅力をお伝えしたい。公開前なのでネタバレに気をつけてのご紹介です。
*「Campeones」の作品&監督キャリア紹介記事は、コチラ⇒2018年06月12日

『チャンピオンズ』(原題「Campeones」)2018、コメディ、スペイン=メキシコ合作
*キャスト*
ハビエル・グティエレス(マルコ・モンテス)『マーシュランド』
『オリーブの樹は呼んでいる』『クリミナル・プラン』「El autor」
アテネア・マタ(マルコの妻ソニア)『モルタデロとフィレモン』『ビースト 獣の日』
フアン・マルガージョ(ソーシャルセンター責任者フリオ)
『ミツバチのささやき』『孤独のかけら』
ルイサ・ガバサ(マルコの母アンパロ)パウラ・オルティスの「La novia」
ラウラ・バルバ(裁判官)『ロスト・アイズ』
ダニエル・フレイレ(カラスコサ)『ルシアとSEX』
ルイス・ベルメホ(ソニアの同僚)『となりのテロリスト』『KIKI』『孤独のかけら』
ビセンテ・ジル(ベニトの雇用者)
Yiyo アロンソ(マルコの弁護士)
イツィアル・カストロ(ヘススの母親)『ブランカニエベス』『あなたに触らせて』
チャニ・マルティン(クエンカ行きバスの運転手)
ホルヘ・フアン・ヌニェス(セルヒオの雇用者)
クラウディア・フェセル(ホテルのフロント係)『カミーノ』
ハビエル・フェセル(新聞記者)
◎以下バスケット・チーム「ロス・アミーゴス」の選手10人
ヘスス・ビダル(マリン)、グロリア・ラモス(紅一点コジャンテス)、セルヒオ・オルモ(セルヒオ)、フリオ・フェルナンデス(ファビアン)、ヘスス・ラゴ(ヘスス)、ホセ・デ・ルナ(フアンマ)、フラン・フエンテス(パキート)、ステファン・ロペス(マヌエル)、アルベルト・ニエト・フェランデス(ベニト)、ロベルト・チンチジャ(ラモン)
◎決勝戦対戦チーム「ロス・エナノス」の選手、ラモン・トーレス、アントニオ・デ・ラ・クルス以下多数。
ストーリー:マルコ・モンテスはスペイン・バスケット・ナショナルリーグのチームABCの副コーチである。マナーが悪く横柄なことから他のコーチとは上手くいってない。プロとしてのキャリアも人間関係にも多くの問題を抱えこんでいる。試合中に試合方針の違いからヘッド・コーチと口論になり退場させられる。むしゃくしゃして飲酒運転、あげくの果てにパトカーに追突事故、即刻クビになってしまった。妻ソニアにも言えず実家に転がり込んだマルコに、裁判官からは懲らしめの罰則として2年間の服役か、または90日間の奉仕活動「ロス・アミーゴス」という知的障害者のバスケットボール・チームのコーチのどちらかを選択するよう言い渡された。こんな罰則はマルコの好みではなかったが、しぶしぶコーチを選ぶことにした。しかしマルコは次第にこの奇妙なチームの面々から、自分が学ぶべき事柄の多さに気づかされていく。彼らは障害者のイメージからはほど遠く、率直で独立心に富んだ、肩ひじ張らずに生きている姿に、我が人生を見つめ直していくことになる。 (文責:管理人)
障害者とは何か、フツウとは何かの定義を迫られるマルコと観客
A: ストーリーは公開前なので、結末まで話したくても話せない。ただ自分の障害者観を見直さねばならないと思いました。コメディで「障害者とは何か、フツウとは何か」をこれほど明快に示した映画はそんなに多くないはずです。
B: さらに言えば「幸せとは何か」です。主役のマルコも私たち観客も考え直さねばならない。それが強制されずに自然に素直にできたことがよかった。
A: ハビエル・グティエレスの魅力については、度々当ブログで書き散らしているので今更ですが、彼以外に具体的な俳優名を思い浮かばないほど適役でした。実際のグティエレスにとって9人の新人たちは不思議でも何でもない。それは彼自身が障害者の息子の父親だからです。「社会の言われなき攻撃の目に晒されている。それは人々の無知と恐怖と無関係ではない」と語っている。
B: この事実が脚本にも隠されていますね。この映画は皆にとって必要だし、同時に自覚をうながしたり教育のためにもなるから、「学校で見てもらいたい」ともコメントしている。
A: 代表作のうち、アルベルト・ロドリゲスの『マーシュランド』のダメ刑事役も捨てがたいが、彼はコメディのほうが生き生きしている。イシアル・ボリャインのコメディ『オリーブの樹は呼んでいる』などのほうが好きですね。
B: 本作でも<チビ>という単語が何回も現れますが、本当に上背がない。しかしそれも個性の一つではないか。

(どうしたらいいものやらと、途方に暮れるマルコ)
* ハビエル・グティエレスのキャリア紹介は、コチラ⇒2015年01月24日
*『オリーブの樹は呼んでいる』の作品紹介は、コチラ⇒2016年07月19日
プロの俳優と知的障害者の見事なコラボレーション
A: 昨年の作品紹介で「プロの俳優はマルコ役のハビエル・グティエレス一人」と書きましたが、実際映画を見てみれば、次々に知った顔が現れました。「プロの有名な俳優」が正しいようで。
B: ロス・アミーゴスの選手はすべて初出演ですが、ソーシャル・センターの責任者フリオ役のフアン・マルガージョ、マルコの母親役ルイサ・ガバサ、他ルイス・ベルメホ、イツィアル・カストロ・・・
A: というわけでキャスト欄に主に邦題のある過去の出演映画を追加しました。フアン・マルガージョはハイメ・ロサーレスの『孤独のかけら』でヒロインの父親になった俳優、共演したもう一人の主役ペトラ・マルティネスと結婚している。マルコが「私の仕事はフツウの選手のコーチ、彼らは選手でもフツウでもない」と断わると、「いいかい、マルコ、ノーマルなのは誰? あんたや私かい?」と諭した。
B: 役柄も素敵だがいい味を出していた。イツィアル・カストロはあの巨体だから一目でわかります。

(正真正銘のインテリ役フリオを演じたフアン・マルガージョ、ゴヤ賞2019授賞式)
A: ロス・アミーゴスの俳優たちは、本作のメイン・プロデューサーのアルバロ・ロンゴリアが監督したドキュメンタリー「Ni distintos ni diferentes: Campeones」(27分)にヘスス・ビダル以外出演しています。同時進行か、あるいはこちらのほうが先だったかもしれません。
B: 『チャンピオンズ』は映画祭を通さずいきなり公開、あっという間に話題を攫い、世界各地をめぐっていますが、ドキュメンタリーはサンセバスチャン映画祭2018で上映されました。

(サンセバスチャン映画祭に出品されたドキュメンタリーのポスター)
障害者への友好・多様性・可視化に警鐘を鳴らす
A: ヘスス・ビダルはゴヤ賞2019新人男優賞を受賞しました。スカイプでフェセル監督から彼の受賞スピーチの素晴らしさが伝えられました。「YouTubeで見られるからご覧になってください」ということでしたが、本当に心に沁みる、当夜のハイライトの一つでした。当ブログでもゴヤ賞2019で簡単にご紹介しています。「無名の新人、10%の視力しかない視覚障害者の受賞スピーチは、友好・多様性・視覚化という三つの単語で、障害者を特別扱いする社会に警鐘を鳴らした」と。
B: フェセル監督は「全盲に近い」「彼らは自分自身を演じていた」と語っていましたが、彼だけは知的障害者ではなく視覚障害者ですね。ほかの出演者は自分自身を演じていたが、彼はマリンという役を演じたわけです。
*ゴヤ賞2019授賞式のヘスス・ビダルの記事は、コチラ⇒2019年02月05日

(受賞スピーチをするヘスス・ビダル、ゴヤ賞2019授賞式にて)
A: いま流行りの言葉で言えば、本作は「障害者の見える化」に貢献している。それが監督のテーマではなかったけれど、私たちがその存在を「できれば知らないでいたい」という風潮に釘を刺した。
観客の予想を裏切ることで観客の考えを変えたい
B: 監督から「ロベルト・チンチジャが扮したラモンの造形は、シドニー・パラリンピック2000バスケットボールのスペイン・チームの不祥事がヒントになった」と。
A: スペイン・チームは金メダルだったが、選手12人中10人が健常者、知的障害者はラモン・トーレスともう一人の選手だけだったことが発覚して、金メダルが剥奪されたという不祥事でした。これによりスペイン障害者スポーツ連盟の会長が辞任に追い込まれた。身体障害者と違って知的のほうは外見だけでは判断できないから、それ以降もパラリンピック事務局を悩ませているようです。
B: そのラモン・トーレスから名前をとった。だから劇中のラモンはラモン・トーレスの分身、つまり「コーチを信用しない理由」が判明する。
A: 実際のラモン・トーレスも決勝戦対戦チーム、カナリア諸島の「ロス・エナノス」の選手として出演していた。エナノスenanosというのは「背のひどく低い人たち」という意味で、マルコたちは競技場で大きな選手たちを見てびっくりする。
B: 監督は至る所でいたずらっ子ぶりを発揮していた。「最初の脚本は殆ど書き直し、スタートしてから彼らとコラボしながら書き進めていった」とも語っていました。
A: オーディションでは300人ぐらいと面接した。異色の登場人物のなかでもコジャンテスを演じたグロリア・ラモスは飛び切り魅力的だった。彼女がスクリーンに現れると何が起こるかとウキウキしてくる。
B: 監督は「知的障害者の女性とはこういうもの」という世間の固定観念を壊したかったと語った。
A: 他にも「この映画に出たことで人生が変わった」と語るフアンマ役のホセ・デ・ルナ、パキート役のフラン・フエンテス、ヘスス役のヘスス・ラゴなど、すべてをご紹介できないが、愛すべき人々が登場する。
B: 他人と違うことは個性の一つだと、寛容と多様性の重要さが語られている。

(ラモンにおんぶされてはしゃぐ紅一点コジャンテスとロス・アミーゴスの選手たち)

(出演したことで「人生が変わった」と語るフアンマ役のホセ・デ・ルナ)

(フォルケ賞でのヘスス・ラゴ、グロリア・ラモス、フラン・フエンテス、1月6日)
A: 他にもアテネア・マタ扮するマルコの奥さんソニアの偏見のない人格造形もよかった。マルコや選手たちを縁の下から支える役柄、実際にフェセル監督の信頼も厚かった。ルイサ・ガバサ演じる愛すべきマルコの母親アンパロ、美人裁判官役のラウラ・バルバ、ヘススのママ役のイツィアル・カストロなど、総じて女性が生き生きと描かれていた。ラウラ・バルバは舞台女優にシフトしており、ロンドンほか海外での活躍が多い。TVシリーズ出演の他、自身も短編を撮って監督デビューしている。

(インタビューを受けるアテネア・マタと監督、2018年4月6日)

(裁判官役ラウラ・バルバに刑罰の理不尽を訴えるマルコ)
B: これから公開だから、フィナーレに触れることはできないが、幸せな気分で映画館を出ることができます。
A: 観客の予想を裏切ることで観客の考えを変えたい部分も含めて、泣いて笑って考えさせられるコメディでした。「コメディは90分以内」がベターと言われるなかで、2時間越えを危惧していたが全くの杞憂だった。
B: 次回作が既に始動しているようだが、まだIMDbにはアップされておりません。
A: 監督は12月公開時には来日する予定でいるそうです。実現すれば「ラテンビート09」で上映された『カミーノ』以来のことになる。プロデューサーのルイス・マンソ、絵コンテと出演もしたビクトル・モニゴテと3人で来日、会場でも場外でも観客の質問に気軽に応えていた。マンソは新作でもエグゼクティブ・プロデューサーとして、モニゴテは絵コンテ・アーティストとして参画しているので、気取らないダンゴ三兄弟の来日が期待できるかもしれない。さて、魅力をお伝えすることが出来たでしょうか。
『誰もがそれを知っている』*アスガー・ファルハディ ― 2019年06月23日 17:40

★故国イラン、フランス、スペインと、社会のひずみと家族の不幸を描き続けているアスガー・ファルハディ監督、今回はマドリード近郊の小さな町を舞台に少女誘拐事件を絡ませたサスペンス仕立てにした。監督は『彼女が消えた浜辺』(2009「About Elly」)のようにミステリアスなテーマを織り込むのが好きだ。邦題は英題「エブリバディ・ノウズ」を予想していましたが、『誰もがそれを知っている』と若干長いタイトルになりました。そんなこと「みんな知ってるよ」という劇中のセリフが題名になりました。主な関連記事と登場人物が多いので、以下にキャスト名を再録しておきます。

(アスガー・ファルハディ監督と出演者、カンヌ映画祭2018にて)
*本作の主な関連記事*
*作品の内容・監督キャリア・キャストの紹介記事は、コチラ⇒2018年05月08日
*ペネロペ・クルスのセザール名誉賞受賞の記事は、コチラ⇒2018年03月08日
*ペネロペ・クルス近況紹介記事は、コチラ⇒2019年05月20日
*ハビエル・バルデム出演の経緯と近況の記事は、コチラ⇒2018年10月17日
*主な登場人物*
ペネロペ・クルス(ラウラ)
ハビエル・バルデム(ラウラの元恋人パコ)
リカルド・ダリン(ラウラの夫アレハンドロ、アルゼンチン人)
バルバラ・レニー(パコの妻ベア)
エルビラ・ミンゲス(ラウラの姉マリアナ)
インマ・クエスタ(ラウラの妹アナ)
エドゥアルド・フェルナンデス(マリアナの夫フェルナンド)
ラモン・バレア(ラウラ三姉妹の父アントニオ)
ロジェール・カザマジョール(アナの結婚相手ジョアン、カタルーニャ人)
カルラ・カンプラ(ラウラの娘イレネ)
サラ・サラモ(マリアナの娘ロシオ)
イバン・チャベロ(ラウラの幼い息子ディエゴ)
ホセ・アンヘル・エヒド(フェルナンドの友人、退職した元警官ホルヘ)
セルヒオ・カステジャーノス(パコの甥フェリペ)
パコ・パストル・ゴメス(ロシオの夫ガブリエル、出稼ぎ中)
ハイメ・ロレンテ(ルイス)
トマス・デル・エスタル(パコのワイナリー共同経営者アンドレス)
その他、インマ・サンチョ、マル・デル・コラル、多数
突然ひらめく一つのシーン――テーマは後から着いてくる
A: 監督によると「本作のアイデアは2005年、4歳になる娘を連れてスペインを旅行していたときに目にとまった<少女失踪>の張り紙だった」と語っています。最初からテーマを決めてストーリーを組み立てていくのではなく、「あるシーンが頭に浮かぶと、そこを起点にしてストーリーを語りたくなる。テーマが具体化するのはずっと後です」とも語っています。
B: 『彼女が消えた浜辺』のインタビューでも同じようなことを語っていた。今度はスペイン旅行中だったから、ここを舞台に撮ろうと思った?
A: というか、もともとスペインにシンパシーがあったので、スペインの俳優を使ってスペイン語で撮りたいと考え準備していたということでしょう。スペイン映画をたくさん観たうちからペネロペ・クルスに白羽の矢を立てた。彼女を念頭に執筆開始、何回も書き直しを繰り返して本人にオファーをかけたそうです。
B: ペルシャ語で執筆、それを翻訳してもらって、書き直して、を繰り返した。このやり方は2013年に公開されたフランス語で撮った『ある過去の行方』で既に体験済みでしたね。
A: スペイン語はフランス語よりずっと易しい。クランクインしたときにはスペイン語を完全にマスターしていたとハビエル・バルデムがエル・パイス紙に語っていたが、やはり通訳を介していたらしい。自分へのオファーが直ぐこなくてやきもきしたとジョークを飛ばしていた。当然パコ役は自分が演ると思っていた(笑)。
脚本の曖昧さともつれ方――犯人が誰であるかは重要ではない
B: 冒頭のシーンは古ぼけた教会の鐘楼で始まる。どうもデジャヴの印象でした。
A: ハトが窓から逃げようとして騒ぎはじめる。数秒後にこれから起こるだろう事件を暗示するかのように、手袋をはめた手が古新聞の切り抜きをしている。「カルメン・エレーロ・ブランコ誘拐事件」と読める。誰かが閉じ込められ、それは過去の事件と関係していると知らせている。
B: ラウラの久しぶりの帰郷に家族や隣人を挨拶に登場させることで、これから始まる劇のメンバー全員が次々に紹介される。導入部としては合格点でしょうか。

(かつての恋人同士だったラウラとパコ、ラウラの娘イレネとパコの甥フェリペ)
A: この鐘楼に早速意気投合したイレネとフェリペが昇ってくる。ハトのメタファーがそれとなく分かるような仕掛けがしてある。その後ハトが飛び立つことから事件が解決に向かうことを観客は理解する。
B: 謎解きや犯人捜しを楽しむ複雑なストーリーのスリラー映画ではないということです。
A: 冒頭からの数ある伏線を見落とさずに見ていれば、かなり早い段階で誘拐犯人の当たりがついてくる。しかし本作では犯人が誰であるかは重要ではない。アスガー・ファルハディの狙いは謎解きではない。どんな平凡な家庭にも人に知られたくない秘密があり、知らないほうが却って幸せなこともある。
B: 秘密を守るためには嘘をついてでも隠し続けなければならない。しかし娘の命にかかわることとなれば、それは別の話になるだろう。
A: ところが万事休す暴露すれば、そんなこと本人以外「みんな知ってたよ」となってしまう。物語を動かすために犯人追及は重要だが、犯人の身元は重要ではない。つまり誘拐犯が分かっても、それはいずれ誰もが知っているのに誰も口にしない新たな秘密になるだけです。「沈黙は金」なのである。
B: 図らずも母の秘密を知ることになるだろう娘、更には娘の秘密を偶然にも知ってしまう母親が秘密の重さに耐えかねて共犯者を求めるシーンで幕を閉じる。それぞれ秘密を墓場まで持って行くことができるだろうか。
A: フィナーレの総括で、フラストレーションを引き起こした観客が多かっただろうと思います。娘を救い出し、家族や知人の亀裂を残したままラウラ一家は早々に引き揚げるが、全財産を失い不信を募らせる妻ベアとの関係も崩壊したパコの過失は、いったい何だったのだろうか。
B: 少し理不尽な気分が残った。しかしバルデム自身はパコの陰影のある実直さがえらく気に入ったようだ。もっとも本当にパコがすべてを失ったかどうかは、観客に委ねられた。
A: 多くの批評家が脚本を褒めているけれども、個人的には支離滅裂とまでは言わないがストレスを感じた。男としての責任感だけで今までの苦労を水の泡にできるものだろうか。
B: 作中での常識ある人間はパコの連れ合いベアだけだ。
A: 豪華なキャスト陣を動かすためだろうが、ほかにも脚本の曖昧さやもつれ方が気になった。過去のラウラとパコの関係はある程度想像できますが、ラウラが町を出たかったのは分かるとして何故アルゼンチンだったのかの必然性が感じられなかった。
B: 多分リカルド・ダリンを起用したかったからじゃないの (笑)。コメディが得意なダリンがずっと苦虫を噛み潰していた。かつては会社を経営していたという夫アレハンドロは、会社が倒産して2年前から失業中という設定でした。今時「神のご加護」に縋っている人間がいるなんて。
A: 誘拐犯に疑われるにいたっては馬鹿げすぎている。犯人が誰かは重要ではないけれど、土地勘のない異国の土地でいくら金欠でも単独では無理でしょう。

(ラウラと夫アレハンドロ、ペネロペ・クルスとリカルド・ダリン)
経済危機を背景にエゴがむき出しになる村社会
A: 本作ではスペインとアルゼンチン両国の長引く経済危機、失業問題が背景にある。加えて不法移民による格安の季節労働者の急増が土地の労働者を圧迫している。元の地主と小作間の土地紛争と相続問題、資産格差を打ち破る下剋上的な新旧の世代交代などテーマを詰め込みすぎだ。更にこれらを解決するのがテーマじゃないから、ただ並べただけで最後までほったらかしだった。
B: 時代が変わり没落していくかつての地主、夫婦の危機、兄弟姉妹間の口に出せない不平等感などもテーマの一つだった。他人の不幸は蜜の味は国を問わない。
A: 脇を固めた俳優たちに触れると、三姉妹の長女マリアナを好演したエルビラ・ミンゲス、本作でスペイン俳優連盟2019の助演女優賞を受賞しているベテラン。酒に溺れ頑迷でただのろくでなしになった老人アントニオの面倒を、夫フェルナンドとみている。美人の妹たちとは年もかなり離れ、幸せそうでない娘ロシオと孫を同居させている。隣人の陰口どおり貧乏くじを引いてしまっている。

(我慢強いマリアナと責任を取りたくないフェルナンドの夫婦)
B: 父役のラモン・バレアは、ビルバオ生れ(1949)の脚本家、舞台監督でもあり皆の尊敬を集めている。未公開作品ですがボルハ・コベアガの「Negociador」では主役も演じています。公開作品で他に何かありますか。
A: TVシリーズや短編を含めると160作ぐらいに出ていますが、本作のパンフレットは不親切で出演作はゼロ紹介でした。まず同郷の監督パブロ・ベルヘルの『ブランカニエベス』や『アブラカダブラ』、Netflixでは先述のボルハ・コベアガの『となりのテロリスト』、サム・フエンテスの『オオカミの皮をまとう男』、未公開ですがアナ・ムルガレンの「La higuera de los bastardes」など結構あり、当ブログでも何回かご登場願っています。

(尊敬を失った老いた父親アントニオ役ラモン・バレアとラウラ)
B: 娘婿フェルナンドに扮したエドゥアルド・フェルナンデスは、ご紹介不要でしょうか。バルデムと共演した『ビューティフル』、ダリンと共演した邦題が最悪だった『しあわせな人生の選択』など。
A: サンセバスチャン映画祭男優賞受賞の『スモーク・アンド・ミラー』に、ゴヤ賞助演男優賞を受賞した『エル・ニーニョ』など、当ブログでのご紹介記事も枚挙に暇がありません。
B: 枚挙に暇がないもう一人が、パコの妻ベア役のバルバラ・レニー、アルゼンチン出身だが今やスペインを代表する女優の一人です。クルスもレニーも出演本数はかなりあるほうですが、初めての美人スター対決、さぞかし火花が散ったことでしょう。
A: 二人ともギャラが高そうだから共演は難しい。バルバラが主演したハイメ・ロサーレスの新作『ペトラは静かに対峙する』が間もなく公開されます。ペネロペ・クルスはスクリーンの4分の3ほど苦しんでいましたが (笑)、シーンごとに表情の陰影が異なり、確実に演技は進化している。今が人生でいちばん油が乗っているというか充実しているのではないか。

(パコとベア、ハビエル・バルデムとバルバラ・レニー)
B: バルデムとダリンの共演も初めて。そもそもダリンはスペイン映画にはあまり出演していないし、バルデムも軸足をアメリカに置いていた時期が長いから当然です。
A: 三女アナ役のインマ・クエスタはコメディもこなす演技派、クエスタはクルスともバルデムとも初顔合わせです。2011年ダニエル・サンチェス・アレバロの『マルティナの住む街』で登場、脇役ながら存在感を示した。予想を裏切らずその後の活躍は『スリーピング・ボイス』『ブランカニエベス』『ジュリエッタ』と、いい作品に恵まれている。
B: 本作では前の交際相手と別れて金持ちらしいカタルーニャ人を結婚相手に選ぶ。二人の出会いは語られませんが、ラウラから「賢明な選択だった」と褒められたので「おや?」と思った。
A: 精神的な意味なのか経済的なものか推測するしかないのだが、花嫁側の経済的困窮を考えると後者かなと感じた。前半と後半の明暗を印象づけるためかもしれないが、困窮している花嫁側があれほど派手な披露宴をするのは不自然かな。
B: バルデムは「スペインの風習が正確に描写され」ていると語っているが、監督は常にイランとスペインの制度の違いを気にかけ「これはスペインでも可能なことか」と確認していたという。
A: 特にイスラム社会の婚姻制度は欧米とは異なっており、「婚姻は契約」であり、花婿は花嫁と家族に身支度金をいくら支払うか、離婚に至った場合の慰謝料をいくら払うか契約書に明記しなければならない。ここに精神的なものは含まれない。勿論離婚の権利は夫側にしかなく、妻が要求した場合は慰謝料は受け取れない。これは初めてアカデミー賞を手にした、2011年の『別離』でも描かれていた。
B: アナの結婚相手ジョアン役のロジェール・カザマジョールは、デル・トロのダーク・ファンタジー『パンズ・ラビリンス』に出演、ビダル大尉と対決するゲリラの闘士役を演じた。
A: 有名なのはゴヤ賞2011で作品賞以下9部門を制したアグスティ・ビリャロンガの『ブラック・ブレッド』で少年の父親になった。オリジナル版はカタルーニャ語、母語もカタルーニャ語です。ゴヤ賞は逃したがガウディ賞助演男優賞を受賞している。カタルーニャTVのシリーズの出演が多く、演技の幅は広い。実際もリェイダ生れのカタルーニャ人です。

(花嫁と花婿、インマ・クエスタとロジェール・カザマジョール)
B: 他ルイス役のハイメ・ロレンテは、シーズン3の配信が始まる『ペーパー・ハウス』のデンバー役、『ガン・シティ~動乱のバルセロナ』や『無人島につれていくなら誰にする?』など、最近の活躍が目立つ若手。
A: ラウラの幼い息子ディエゴ役のイバン・チャベロは、パコ・プラサのホラー『エクリプス』で主人公ベロニカの弟役でデビュー、若干背が伸びました。メガネは伊達ではないようだ。
B: 筋運びにもやもやがあるにしても、俳優たちの演技はよかったのではないか。
A: 演技派をこれだけ集められたのもオスカー監督ならではの威光でしょう。
撮影監督ホセ・ルイス・アルカイネの光と闇の拘り方
B: 最後になったが撮影監督のホセ・ルイス・アルカイネのバイタリティーには驚く。1938年生れだから既に80代に突入している。バルデム=クルス夫婦の初顔合わせとなったビガス・ルナの『ハモンハモン』他ルナ作品の専属だった。
A: アルモドバルの『バッド・エデュケーション』『ボルベール』『私が、生きる肌』ほか、ビクトル・エリセ、カルロス・サウラ、ビセンテ・アランダ、フェルナンド・トゥルエバなどスペインを代表する監督とタッグを組んでいる。ブライアン・デ・パルマなど海外の監督ともコラボして挑戦を止めない。

(ケーキカットのシーンから)
B: 本作では光と闇、雨または水が物語を動かす役目をもたされている。突然降り出す雨、ろうそくの明かりのなかでのケーキカット、土砂降りの闇夜のなかを走る車のヘッドライト、まぶしい陽光を遮るようにホースからほとばしる水しぶきなど、印象深いシーンが多かった。
A: その一つ一つに繋がりがあり、特にフィナーレのホースでプラサの汚れを洗い流す飛沫は、ベールで二人の共犯者を覆い隠すように幕状になっていく。こうして誰もが知っているが誰も口に出さない新たな秘密が誕生する。
最近のコメント