アメナバルの 『戦争のさなかで』 鑑賞記*ラテンビート2019 ⑬ ― 2019年11月26日 14:38
過去の歴史ではなく現在について語っている映画
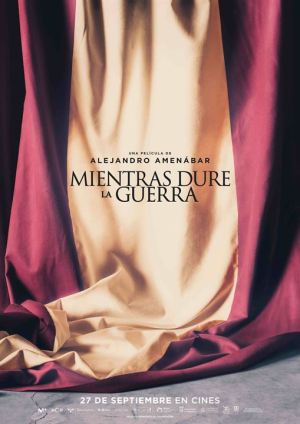
★アレハンドラ・アメナバルの新作『戦争のさなかで』は、スペインの作家にして哲学者、詩人、劇作家、ラテン語やギリシャ語を教える大学人、政治にもコミットした、ミゲル・デ・ウナムノの最晩年6ヵ月間を描いた作品。1936年7月17日勃発したスペイン内戦から12月31日の彼の死に至るまでを、彼の夢をフラッシュバックで挿入して描いている。2018年6月サラマンカでのクランクインからご紹介してきた本作を、今年のラテンビートで見ることができました。当時アメナバルが「過去の歴史に基づいているにもかかわらず、現在について語っている」作品と述べていたことが納得できる仕上りでした。戦争やファシズムは私たちのすぐそばにあり、勇気は戦いの中でだけ見せるものではない。
★ミゲル・デ・ウナムノにカラ・エレハルデを起用したことを周囲から危惧されたと監督は明かしていましたが、見れば分かる通り取りこし苦労でした。当ブログに度々登場させているエレハルデのフィルモグラフィーは、2014年エミリオ・マルティネス=ラサロのコメディ「Ocho apellidos vascos」で、コメディでゴヤ賞を取るのは難しいと言われながら助演男優賞にノミネートされた折にご紹介しています。結果はめでたく受賞しました。もう一人の主役ホセ・ミリャン・アストライを演じたエドゥアルド・フェルナンデスも、エレハルデ以上にご登場願っています。アルベルト・ロドリゲスの『スモーク・アンド・ミラーズ』の実在している元諜報員フランシスコ・パエサ役(SSIFF銀貝賞に当たる男優賞受賞)、最新作の愛娘グレタ・フェルナンデスと親子を演じた、ベレン・フネスの「La hija de un ladlón」では主役の泥棒になった。12月に入るとノミネーションが発表になるゴヤ賞2020では主演男優賞ノミネートは確実と予想しますので、追って別個にご紹介したい。
* カラ・エレハルデの主なキャリア紹介は、コチラ⇒2015年01月28日
★他のキャスト陣を便宜上分かる範囲でアップしておきます。過去の作品紹介、監督キャリアはオリジナル・タイトル「Mientras dure la guerra」でアップしております。脚本はアレハンドロ・エルナンデスが共同執筆しています。
*「Mientras dure la guerra」の紹介は、コチラ⇒2018年06月01日/2019年09月27日
* 脚本共同執筆者アレハンドロ・エルナンデス紹介は、コチラ⇒2018年06月01日
◎ 主なキャスト紹介(G体が主要登場人物)◎
カラ・エレハルデ(ミゲル・デ・ウナムノ、1864~1936年12月31日死去)
エドゥアルド・フェルナンデス(ホセ・ミリャン・アストライ将軍、1879~1954)
サンティ・プレゴ(フランシスコ・フランコ将軍、1892~1975)
ナタリエ・ポサ(アナ・カラスコ・ロブレド、サラマンカ市長夫人、1883~1958)
ティト・バルベルデ(ルイス・バルデス・カバニリェス将軍、1874~1950)
ルイス・ベルメホ(ニコラス・フランコ、フランコの兄弟)
パトリシア・ロペス・アルナイス(ウナムノの次女マリア、1902?~1983)
インマ・クエバス(ウナムノの三女フェリサ)
カルロス・セラノ(ウナムノの教え子、アラビア語研究家サルバドル・ビラ・エルナンデス、1904~36年10月22日に銃殺)
ルイス・サエラ(アティラノ・ココ、福音教会牧師、ウナムノの友人、1902~36年12月9日銃殺)
アイノア・サンタマリア(アティラノ・ココの妻エンリケタ・カルボネル)
ミレイア・レイ(フランコの妻カルメン・ポロ)
ルイス・カジェホ(エミリオ・モラ・ビダル将軍、1937年6月事故死)
ホルヘ・アンドレウ(ウナムノの孫ミゲリン)
ぺプ・トサール(エンリケ・プラ司教)
イジアル・アイツプル(家政婦アウレリア)
ミゲル・ガルシア・ボルダ(アルフレッド・キンデラン将軍)
マリアノ・リョレンテ(サラマンカ市長カスト・プリエト・カラスコ、1886~1936年7月29日に暗殺)
マルティナ・カリディ(青春時代のウナムノの妻コンセプシオン、コンチャ)
ミケル・イグレシアス(青春時代のウナムノ)
アルバ・フェルナンデス(フランコの娘ネヌカ)
ミゲル・デ・ウナムノの最晩年――観客に感動を強制しない
A: 東京国際映画祭TIFFの共催作品だったので、そちらで先に観られた方が多かったかもしれない。ラテンビート上映前に既に毀誉褒貶入り混じった記事を目にしました。過去の歴史がベースになっているのでネタバレ云々はありません。主な登場人物もスペイン内戦でお馴染みの歴史上の人物、ウナムノは実に複雑な性格で、ドキュメンタリーこそ製作されておりましたが、2015年にマヌエル・メンチョンが撮った「La isla del viento」が初めてのビオピック映画でした。しかし、これはフィクションを交えているので正確には伝記映画とは言えません。ですからウナムノの晩年に絞っておりますが、アメナバルの本作が最初の伝記映画となります。
*「La isla del viento」では作品紹介の他、ウナムノの経歴、著作などもアップしております。コチラ⇒2016年12月11日

(サラマンカ大学講堂で反戦を説くミゲル・デ・ウナムノ役のカラ・エレハルデ)
B: 善悪の二元論、観客に感動を強制しないのが先ずよかった。登場人物が大勢でしたが、なかで歴史書には登場しないウナムノの身近な家族、娘のマリア、フェリス、孫のミゲリンなども登場させている。
A: 特にウナムノの9人の子供のうち、民主主義に移行した1983年3月、脳溢血のため80歳で亡くなった次女マリアは、父親の「手厳しく、辛辣」という性格を強く受け継いだ子供として有名でした。米国テネシー州のナッシュビル大学でスペイン文学の教鞭を執った。生涯独身で晩年は、映画には登場しなかった長男フェルナンドや次男パブロ、長女サロメの子供たちとサラマンカで暮らしていたそうです。
B: ミゲリンと呼ばれていたウナムノの孫が1933年鬼籍入りしたサロメの息子のようでした。
A: 当ブログ初登場のマリアに扮したパトリシア・ロペス・アルナイスは、1981年バスク州ビトリア生れ、ジョン・ガラーニョ&ホセ・マリ・ゴエナガの「80 egunean」(10、バスク語)でデビュー、フリオ・メデムの「El árbol de la sangre」(17)他、TVシリーズ「La otra mirada」(18~19、21話)のテレサ・ブランコ役、同「La peste」(18、12話)など人気ドラマに出演、お茶の間でも知名度があります。アメナバル映画のキャスト陣はオール初出演、同じ俳優は起用しないやり方です。
B: フリオ・メデムもバスク出身の監督、上記の「El árbol de la sangre」は、『ファミリー・ツリー 血族の秘密』の邦題でNetflixで配信されています。

(マリア・デ・ウナムノに扮したパトリシア・ロペス・アルナイス)
A: ウナムノの夢の中に出てくる妻コンセプシオン(愛称コンチャ)は幼馴染の女性、父が亡くなった1970年ごろに出会い、結婚は1891年です。その後9人の子供が2年間隔で生まれています。長女サロメに続いてコンチャも1934年に亡くなるという不幸が続いていたが、同年サラマンカ大学終身総長の称号を送られている。
B: 禍福は糾える縄の如しでしょうか。時の権力者の思惑により作中でも終身総長を罷免されたり回復されたり目まぐるしかった。
A: 内戦の泥沼化を避けようとしてとった、彼のどっちつかずの態度も原因の一つ、1936年7月内戦勃発、その後、混迷を続ける共和国政府を批判したことで、アサーニャ大統領により8月に罷免、ところが批判したことで反乱軍の中心人物だったティト・バルベルデ扮するルイス・バルデス・カバニリェス将軍によって回復されている。
B: ところが10月12日「民族の日」(現ナショナルデー)にサラマンカ大学講堂に集まった反乱軍兵士たちの集会で反戦を説いたことで、新しく反乱軍最高司令官に就任したフランシスコ・フランコ総統によって剥奪され、自宅軟禁のまま生涯を閉じた。

(ティト・バルベルデ扮するルイス・バルデス・カバニリェス将軍)
現在も引きずる「カタルーニャとバスクはスペイン国家の二つの癌!」
A: この10月12日の演説の録音が残っており、作中でエドゥアルド・フェルナンデス扮するミリャン・アストライ将軍が「カタルーニャとバスクはスペイン国家の二つの癌!」とウナムノに反撃したのも事実だそうです。ウナムノを毛嫌いするミリャン・アストライ将軍とウナムノの一騎打ちが本作の山場の一つです。
B: モロッコ-スペイン戦争で左腕と右目を失ったミリャン・アストライ将軍の単細胞ぶりが対照的だった。モロッコ-スペイン戦争時の上官がフランコで、いわば生死を共にして戦った戦友の間柄、二人とも中央からすれば辺境になるガリシア州ア・コルーニャ出身なのでした。

(隻眼片腕のホセ・ミリャン・アストライ役のエドゥアルド・フェルナンデス)
A: サンティ・プレゴ扮するフランコ総統は良く似ていました。慎重というより本能的に狡猾で、冷酷冷静、気難しいキツネぶりを発揮していた。フランコは最初から反乱軍の指揮官ではなく、ルイス・バルデス・カバニリェス将軍や1937年6月事故死したエミリオ・モラ・ビダル将軍(ルイス・カジェホ)のほうが軍歴も長く先輩だった。映画では周りを警戒させないよう凡庸を演じながら、その実、二人を策略を凝らして排除していくさまが描かれていたが、40年間にも及ぶ独裁政権を維持した力量は、善悪は別として並のものではなかった。

(フランコ総統に似ていたサンティ・プレゴ)
B: カバニリェスはフランコの狡猾さを見抜いていたが、自身がフリーメイソンのメンバーであるという弱みを握られていた。反乱軍のスローガンは、反自由主義、反フリーメイソン、反ユダヤ、反マルクス主義などでした。
A: フリーメイソンは16世紀後半から17世紀初めに起源がある友愛結社(秘密結社)、諸説あるので深入りしないが、カトリック教との対立関係が長く、1738年時のローマ法王クレメンス12世がフリーメイソンを破門している。カトリック教国スペインではメンバーであることは極秘情報だった。
B: しかしその後も、カバニリェスは会合には出席していたようですね。同じ理由で目を付けられたのが福音教会の牧師アティラノ・ココ(ルイス・サエラ)でした。

(アティラノ・ココを演じたルイス・サエラ)
A: ウナムノの友人というだけでは逮捕できないから、かつてイギリスにいたときフリーメイソンと関係していたとして拉致、裁判もなく12月9日銃殺された。ルイス・サエラが演じたことで本人より年長に見えましたが、まだ34歳でした。
B: 妻のエンリケタ・カルボネル(アイノア・サンタマリア)は、赤ん坊を抱いていた。
不寛容な時代を生き抜くための処方箋はあるのか?
A: 裁判もなく銃殺されたのがウナムノの教え子で友人サルバドル・ビラ・エルナンデス(カルロス・セラノ)でした。サラマンカ生れですがマドリード中央大学(現コンプルテンセ大学)で学位を取得しています。その後サラマンカ大学のウナムノのもとで哲学と文学を学んでいる。非常に優秀なアラビア語研究家でしたが、プリモ・デ・リベラの独裁政府を批判して逮捕されたりしている。
B: 映画では家族は出てきませんでしたが、妻も子供もおりました。
A: 1928年から29年にかけてドイツに留学、そこで知り合ったゲルダ・ライムドルファーと結婚しています。父親がベルリンのユダヤ系新聞の編集長だったことも不利にはたらいたと思いますね。サルバドル同様逮捕された妻はカトリックの洗礼を強要されている。
B: 映画ではウナムノの優秀な教え子として書生っぽい印象でしたが、1935年12月には若くしてグラナダ大学の哲学と文学学部の臨時学部長に任命されていた俊才でした。

(ウナムノと議論するサルバドル・ビラ・エルナンデスを演じたカルロス・セラノ)
A: 1936年、学年度の終わりにサラマンカに休暇で家族で戻っていた7月17日に内戦が勃発、グラナダ大学の学部長を解雇されている。ウナムノが二人の友人の自由を求めてフランコに会いにいくが焼け石に水ですよね。フランコは唯の将軍ではなく、国家元首カウディーリョ、総統の地位を手に入れていたのですから、勝負はついていました。
B: 一介の老いぼれ哲学者など意に介しない。サルバドルはグラナダに移送され他の28人と一緒にビスナルで銃殺され、バランコ・デ・ビスナルの共同墓地に投げ込まれた。彼のように生かしておいても実害があるとは思えない人物でも、自分たちと考えが同じでないという理由で殺害された不寛容な時代でした。
A: ウナムノとの強い絆が殺害の理由の一つですが、このような不寛容は現在まで連綿として絶えることがない。アメナバルが「過去の歴史に基づいているにもかかわらず、現在について語っている」と語っていたことが思い出されます。カラ・エレハルデも「スペインはこの83年間、1ミリも前進しておりません」と語っていた。
B: サラマンカ市長夫人アナ・カラスコ・ロブレドを演じたナタリエ・ポサは、アルモドバルの『ジュリエッタ』やセスク・ゲイの『しあわせな人生の選択』に脇役で出演しています。
A: リノ・エスカレラの「No sé decir adiós」(17)の主役を演じ、ゴヤ賞2018主演女優賞を受賞しています。その年のフォルケ賞、フェロス賞などスペインの主だった演技賞を総なめにした実力者です。
B: 本作は、セルバンテス文化センターで開催された「スペイン映画祭2019」で『さよならが言えなくて』の邦題で上映されました。
*「No sé decir adiós」の作品紹介は、コチラ⇒2017年06月25日

(アナ・カラスコ・ロブレドに扮したナタリエ・ポサ)
A: 夫のサラマンカ市長カスト・プリエト・カラスコ(マリアノ・リョレンテ)は、ウナムノと同じ大学人でサラマンカ大学の医学部長、政治的には共和制支持者でした。市長だったのは1931年12月から1936年2月まで、ですから内戦が勃発した7月には正確には市長ではなかった。
B: 反乱軍に共和国支持者と目をつけられると、蜂起者たちによって暗殺されてしまった。作中でも道端に死骸が折り重なっているシーンが映しだされていた。昼日中でも大きな音がすれば死骸が転がった、これが内戦の恐怖です。
A: 国と国が戦う戦争ではあり得ないことです。戦争犯罪人として国際裁判所で裁かれる心配もありません。親子兄弟が敵味方に分かれて戦うのが内戦の悲惨です。フランコ総統の家族も兄は反乱軍、弟たちは共和国軍だったそうです。
B: サンセバスチャン映画祭2019の受賞予想はみごとに外れました。
A: 金貝賞は別として何かの賞に絡むと予想したのですが、全く当たりませんでした。審査委員長がニール・ジョーダンだったのを忘れていたと言い訳します(笑)。まさかパックストン・ウィンターズの『ファヴェーラの娘』になるとはね。男優賞も「複雑を極めたウナムノの人格をコインの裏と表のように演じ分け、注目に値する出来栄え」とエレハルデの評価は高かったのに素通りしました。

(撮影中の監督とカラ・エレハルデ、福音教会の門前のシーン)
B: 年明けに次々と結果が発表になる、フォルケ賞、フェロス賞、ゴヤ賞など、ノミネーションに限るなら大いに期待できます。一番手のフォルケ賞は発表になり(11月21日)、作品賞・男優賞にノミネートされている。今回はアルモドバルの新作「Dolor y gloria」が控えているから受賞がほぼ決定しているカテゴリーもありそうです。
A: 政治的な力学がはたらくから分かりません。しかしゴヤ賞の作品賞・脚本賞・撮影賞・主演男優賞あたりのノミネーションはありでしょう。本作を観て、つくづくスペイン内戦をテーマにした映画はこれからも作られ続けるだろうと実感したことでした。
B: 同じ SSIFF のコンペティション部門で上映された、バスクのトリオ監督、ジョン・ガラーニョ、ホセ・マリ・ゴエナガ、アイトル・アレギの「La trinchera infinita」も、内戦終結後30年間、自宅に隠れ住んでいた共和国軍兵士の物語でした。こちらは3人が揃って監督賞(銀貝賞)を受賞した。
A: 今作もフォルケ賞に作品賞・男優賞(アントニオ・デ・ラ・トーレ)がノミネートされています。では、これから横浜や大阪の会場でご覧になる方、お楽しみください。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://aribaba39.asablo.jp/blog/2019/11/26/9181567/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。