ラテンビート2014*あれやこれや ③ ― 2014年11月01日 14:00
★残る2作品『ブエノスアイレスの殺人』と『エル・ニーニョ』は共にサスペンス、横浜会場がこれからなので深入りできない。そうは言っても気分が切れないうちに印象を纏めておきたい。まずナタリア・メタの『ブエノスアイレスの殺人』から。
ブエノスアイレスのゲイ・コミュニティが語られる
A: 『ブエノスアイレスの殺人』に登場した若い警部の妖しい魅力に堪能できたら、それで充分でしょうか。そうはいきませんよね。しかし結末は書けないから、遠回り記事でお茶を濁すしかありません(⇒LB2014 ⑤ 9・29)。
B: 途中から犯人探しから微妙に焦点がずれてきて、本当のテーマは何なのと戸惑いました。
A: 詰め込みすぎてテーマが少し拡散してしまった印象かな。最初、TVドラマ・シリーズとして企画されたことが尾を引いているのかもしれない。
B: 少しジグザグしているけれど、1個1個ジグソーパズルのように嵌めこんでいくしかない。

A: 軍事政権から民政移管されたラウル・アルフォンシン政権時代(1983~89)の80年代半ばが時代背景ということですが、今まで禁じられていた諸々のこと、性の解放、アングラで秘かに行われていたゲイ・クラブ内での麻薬取引、海外への巧妙な麻薬密輸、遅れてやってきた70年代のシンセサイザーのグラムロックと、若い観客を飽きさせない仕掛けが盛り沢山。
B: 当時のゲイ・コミュニティに大胆に踏み込んでいますが、現在のように米国のトップ企業アップルのCEOがカミングアウトできる時代ではなかった。
A: それに<ストップ・エイズ>の嵐が吹きまわっており、エイズと分かれば、かつてハグし合った友人でも握手を拒んだ時代でした。80年代から90年代初めはホモ排斥が最高潮だった。彼らが現在獲得しているような自由は存在していなかった。
B: 「アン・リーの『ブロークバック・マウンテン』が本作の出発点だった。ワイオミングのカウボーイをブエノスアイレスの警察官に変えたらどうなるか」という監督談話を思い出しながら観ていた。
A: アルゼンチンのゲイ・コミュニティの著者、ジャーナリストで作家のアレハンドロ・モダレジィ*は、「自分は映画のプロではないので映画の良し悪しについては何とも言えないが、もっとも興味深かったのは政治的文化的な要素が提起されていたこと」と前置きして、時期を80年代半ばでなく1989年と限っています。
B: フィクションですから時代を忠実に反映していなくてもと思いますが、どんな理由ですか?

A: 時期を限るのは難しいが、アルフォンシン政府の内務大臣を1987年まで務めたアントニオ・トロッコリは大のホモ嫌い。在任中はゲイ・クラブの一斉検挙や手入れをして迫害した政治家で、ゲイは治療すれば治る病気と考えていた人です。ゲイの世界の情報は薄ぼんやりしていて、映画のようにゲイが受け入れられる状況ではなかったということです。
B: 女性が職務とはいえ<女人禁制>のゲイ・クラブに入れるのもあり得ないか。
A: モニカ・アントノプロス扮するドロレスは、ナタリア・メタ監督の視線を兼ねている。今までの女性の描き方は大方受け身のポジションにおかれたが、ドロレスはそうではなかった。もう一人、ルイサ・クリオクが演じた犠牲者の妹の人格も、良い悪いは別として計算高く利口な人物だった。女性監督の目線を感じました。

*Alejandro
Modarelli : “Fiestas, baños y exilios”/“Flores sobre el orín”など。軍靴の鳴り響く軍事独裁時代に、地下に潜ったゲイ社会の実情をテーマにした本を上梓している。後者は駅舎の公衆トイレを舞台にした軍事独裁時代のゲイたちの日常を描いた戯曲。‘orín’の意味は「錆」、稀に尿ですが、ここでは便器についた汚れのような意味。
チノ・ダリン無しでこの映画は作れなかった
A: 「男性の中にある欲情を騒がせるような魅力ある俳優が必要だった。チノ・ダリンには男の心を捉えるような」魅力があったと監督。もっともらしい顔で二枚舌を使っても、どこか憎めない魅力がありました。
B: ウラオモテノがあると気づきつつも、つい気を許してしまう魔力を備えている。
A: たった一度のチャベス警部との途方もないシーンも、10年前のアルゼンチンだったら一大スキャンダルだった、奥歯に物が挟まったような言い方ですが。
B: 危うい魅力を発散するヌード・ディスコ<マニラ>の歌手ケビンのカルロス・カセリャ、ウンベルト・トルトネセ扮するクラブ・オーナーのモヤノ、具体的なモデルがいそうですね。
A: 80年代だけでなく、90年代から新世紀にかけてニュースとなったゲイ殺害事件も織り込まれているようです。前出のアレハンドロ・モダレジィによれば、部屋の中で殺害されるケースは、たいていハイソサエティの人だそうで、犯人は子供のいる異性愛者だったり、極右のカトリック系のグループだったり、差別は水面下で続いている。
B: 映画に先住民やアフリカ系の人が出てこなかったように、85%が欧州系白人、先住民を含めたメスティーソが15%、ユダヤ系も一番多く、他のラテンアメリカ諸国とは一線を画している。
A: 自国をヨーロッパの一部と考える優越感、しかしヨーロッパ化が不完全だったという劣等感の間で微妙に揺れ動いている。経済のアップダウンも一番激しい国で、他のラテン諸国から批判されても仕方がない面がありますね。
B: 80年代のノスタルジーを楽しむか、70年代のグラムロックにしびれるか、または犯人が行きずりの物取りか、痴情犯罪か、雇われ暗殺者の仕業か推理しながら見るのも一興です。
A: 評価は賛否両論、はっきり二分されているようです。来年のオスカー賞アルゼンチン代表作品に“Relatos
salvajes”(Wild Tales)が選ばれたことはご紹介済みですが(⇒10・24)、こちらには本作の主役の一人チノ・ダリンの父親リカルド・ダリンが出演者の一人です(写真下)。

ラテンビート2014*あれやこれや ④ ― 2014年11月03日 15:07
★劇場公開に一番近いポジションを占めているのが、映画祭の目玉だったダニエル・モンソンの『エル・ニーニョ』です。しかし2009年の「スペイン映画祭」上映の前作『第211号監房』(“Celda 211”)は、スペイン・サイドでは日本公開がアナウンスされていたにもかかわらずポシャってしまった経緯がある。DVD化こそされましたが、なんと邦題が『プリズン211』、タイトルは自由に付けていい決まりですけどアンマリです。

サスペンスが120分を超えると・・・
A: 残念ながら、やはりホルヘ・ゲリカエチェバリアは来日しませんでした。
B: アレックス・デ・ラ・イグレシアが来日なら一緒に来るんじゃないかと思っていましたが。
A: 公開が決まっていて、モンソンが一緒ならプロモーションを兼ねて来たでしょう。それにしても本映画祭のゲストの少なさは課題の一つですね。
B: スポンサーが充実している東京国際映画祭のようにはいきません。作品で勝負するしかなさそうです。
A: さて既に、キャスト並びに監督以下スタッフを紹介しているので書くことないかなと思っていましたが(⇒LB2014 ②9月20日)、中だるみ気になって思い直しました。軽快な滑り出しにヨシヨシと身を乗り出し、これは<監房>より面白くなりそうだとワクワクしましたが、136分が長かった。
B: 前作は110分、最近は2時間超える作品が少なく、特にサスペンスが120分を超えるとキツイ。主人公エル・ニーニョとムスリムの仲間ハリルの姉、麻薬の運び屋を引き受けたアミナとの愛の物語が長すぎたんじゃないですか。
A: 前にも書いたことですが、「モデルは存在するが実話ではない」から愛の物語も結構です。しかし、「20年前30年前の話ではなく、現在日常的に起こっている」事件という触れ込みが途端に嘘っぽくなってしまった。前作でも感じたことですが、モンソンもゲリカエチェバリアもラブストーリーは得意じゃなさそうです。
B: しかし、前作より幅広い層に受け入れられたのは、「女性を感激させるエモーショナルなスリラーだから」と監督は分析していますよ(笑)。
A: へえ、そうですか、女性も千差万別だから。ヘスス・カストロは突然スカウトされて出演したわけで、勿論演技を学んでいたわけではない。撮影当時二十歳そこそこだったことを考慮すれば仕方ないかもしれないが、アクション・シーンの格好良さとの落差がありすぎました。
B: 出演が決まってからは大車輪でランチや水上バイクの運転練習、アクション・シーンの演技指導とシゴかれ、愛の指導は時間切れだったのではないの。
A: これはアクション好きの若者をターゲットに製作されたのだから、そういう意味では興行的にも大成功、観客層が女性にも広がったのはオマケかもしれない。

B: ルイス・トサール扮するヘススとバルバラ・レニー扮するエバの関係もヤキモキさせた。ただの相棒じゃなさそうです。
A: こちらは抑制型、犯人に勘づかれないよう恋人を装って腕を組んで追跡するシーンが切ない(笑)。相手にはバレバレなんですが。それでニセの情報をつかませられ、国家に大損害を与えてしまう。
B: 凄いシーンでした。本当の冷凍魚を切り刻んだのでしょうね。もう一つの愛がエル・ニーニョの仲間エル・コンピとアンダルシア娘のマリフェ、父親の職業が警官なのには笑えました。モンソン映画はコメディ部分が結構楽しい。
度肝を抜く首なし死体が風に吹かれてゆらゆら
A: 伏線として、首なし死体が橋の欄干に吊るされるシーンが出てくる。次に吊るされるのは誰だろうか。かなりシュールな映像です。
B: こういう制裁の仕方は事実としてあるのでしょうか。裏切り者というより麻薬取引に失敗して組織に損害を与えた人ですね。命がけなのは、密売者、取締官の双方にある。
A: 組織を危うくした者には「見せしめの制裁」を加える、これがオキテなんでしょう。
B: いいところまで犯人を追いつめるが、あと一歩で逃げられる理由は、警察内部に裏切り者がいるというのがイロハです。仲間を疑うわけだから疑心暗鬼になる。
A: まず警察腐敗は上司を疑えが定番、『L.A. コンフィデンシャル』でも『ダーティ・ハリー』でも、汚い裏切り者は上司だったからね。
B: 上司役セルジ・ロペスは、『パンズ・ラビリンス』の憎きビダル大尉になった人、強面だから冷酷無比なファシスト役にはぴったりだった。悪役が多そうだね。
A: パリの演劇学校で演技を学んだからフランス語ができる。フランス映画にも悪役で出演しているバルセロナ派のベテラン。イサベル・コイシェの『ナイト・トーキョー・デイ』(09、公開10)にも顔を出していた。

B: ヘススの同僚セルヒオに扮したのがエドゥアルド・フェルナンデス、娘を費用の掛かる海外の学校に行かせている。
A: 父親という役柄かもしれませんが、白髪混じりのフェルナンデスには冷酷な時の流れを感じました。トサールと同じように、どんな役をやっても地でやってると思わせるカメレオン役者。安心して見ていられる。
B: エル・ニーニョ役のヘスス・カストロのゴヤ賞2015新人男優賞は太鼓判ですが、エバ役のバルバラ・レニーも助演女優賞に絡んできそうです。
A: 本作というより、カルロス・ベルムトの“Magical Girl”のほうかもしれない。こちらはサンセバスチャン映画祭で作品賞と監督賞の異例のダブル受賞をした作品です。
経済的困難にもめげず映画好きのスペイン人
B: 封切り3日間で300万人が見たという本作ですが、人気は衰えていないのですか。
A: 10月に入ってサンチャゴ・セグラの“Torrente 5”が公開され、観客53万人(360万ユーロ)とトップを走っています。アルベルト・ロドリゲスのスリラー“La isla mínima”(⇒9月16日)が80万、続く『エル・ニーニョ』が50万7000と3作で約500万ユーロ、全興行成績の70%を占めるそうです(レントラックRentrak 10月5日調べ*)。
B: 消費税が21%と値上がりしたのにね。
A: 『エル・ニーニョ』は公開1ヵ月で1400万ユーロですから、国家に充分貢献しています。
*Rentrak:アメリカのメディア調査会社、視聴率データを取っている。
B: 経済的な困難が映画産業を苦しめているというわりには、好い数字になっている。
A: 失業して時間があるから映画館に行ってるわけではないでしょう。
B: 観客が楽しんでくれる映画作りをモットーにしているモンソン監督、「これといった大宣伝はしないのに多くの観客が見てくれるのは、観客のクチコミのお蔭」と観客に感謝している。
A: 過去に密売に携わった関係者に取材して細部を固め、小道具の一つだったハシッシュ(大麻)の密輸品を押収するシーンでは治安警備隊の警官を動員してもらえた。ヘリコプターも、3トンのランチも、出動してくれた治安警備隊もホンモノだった。(前回の資料部分を下記に再録しました)
<資料再録>
キャスト:ルイス・トサール(警察官ヘスス)、ヘスス・カストロ(エル・ニーニョ)、イアン・マクシェーン(エル・イングレス)、セルジ・ロペス(ビセンテ)、バルバラ・レニー(ヘススの相棒エバ)、ヘスス・カロッサ(エル・コンピ)、エドゥアルド・フェルナンデス(セルヒオ)、Saed Chatiby(ハリル)、ムサ・マースクリ(ラシッド)、マリアン・ビチル(アミナ)、スタントマンも含めてその他大勢。
プロット:エル・ニーニョは、英領ジブラルタルの国境沿いラ・リネア・デ・ラ・コンセプションに住んでいるモーターボートの修理工。ある夜、ダチのエル・コンピと出掛けたパーティの帰途、二人はムスリムの青年ハリルと出会った。彼の叔父ラシッドは麻薬密売のディーラーを生業にしている。エル・コンピに説得され、得意のモーターボートを駆使してブツをアフリカからスペインに運び込む「運び屋」を引き受ける。一方ベテラン警官のヘスス、その相棒エバは、ジブラルタルの密売組織を牛耳っているイギリス人麻薬密売人エル・イングレスの足跡を2年間ずっと追い続け包囲網を狭めていくが尻尾が掴めない。そんなとき若い二人の運び屋ニーニョとコンピの若者が網に掛かってきた。 (文責:管理人)
★ダニエル・モンソン Daniel Monzón Jerez:1968年マジョルカ島のパルマ生れ、監督・脚本家・俳優。脚本家として出発した短編を撮らない珍しい監督。
*監督としてのフィルモグラフィー*
1)1999“El corazón del guerrero” 邦題『クイーン&ウォリアー』(アドベンチャー・ファンタジー)、2002年5月公開。
2)2002“El robo más
grande jamás contado”(アントニオ・レシネス主演のコメディ)本作からホルヘ・ゲリカエチェバリアとタッグを組み現在に至る。
3)2006“The Kovak Box”(“La caja Kovak”西= 英合作、西語・英語・独語)、『イレイザー』の邦題でDVD化されたSFサスペンス、未公開。
4)2009“Celda 211”『プリズン211』DVD (映画祭タイトル『第211号監房』)未公開。
5)2014“El Niño”『エル・ニーニョ』LB2014上映。

★ホルヘ・ゲリカエチェバリア Jorge Guerricaechevarría:1964年アストゥリアスのアビレス生れ、脚本家。アレックス・デ・ラ・イグレシア(ゴヤ賞にノミネートされた『ビースト 獣の日』、『みんなの幸せ』、『オックスフォード殺人事件』他、ほぼ全作)、ペドロ・アルモドバルの『ライブ・フレッシュ』、モンソンの第2作から本作までを執筆している。
★ヘスス・カストロJesús Castro:1993年カディスのベへール・デ・ラ・フロンテラ生れの21歳、俳優。父親はカフェテリアを経営している。母親はヒターノ出身、弟と妹がいる。スカウト前はカディスの中央部に位置するラ・ハンダ La Jandaの高等学校 Ciclo Formativo de Grado Medio で電子工学を学んでいた。ESO(中等義務教育12~16歳)資格がないと入れない。同時にディスコで働き、父親のカフェテリアでチューロを作って家族の経済を支えていたという孝行息子です。他にサンセバスチャン映画祭2014オフィシャル・セレクション正式出品のアルベルト・ロドリゲスのスリラー“La isla mínima”に出演している。
★第29回を迎えるゴヤ賞2015の「栄誉賞」にアントニオ・バンデラスが決定、記者会見がありました。一気に30歳ぐらい若返り、サプライズを超えて我が目を疑いました。次回は古くなってしまった<ニュース>も含めて落ち穂拾いを致します。
アントニオ・バンデラス*ゴヤ賞2015の栄誉賞に決定 ― 2014年11月05日 13:56
★去る10月20日、アントニオ・バンデラス(マラガ1960)の第29回ゴヤ賞2015の「栄誉賞」受賞発表がありました。いやぁ驚きました。こんな若いシネアストが受賞するなんて、ゴヤ賞始まって以来のことです。更にバンデラスはノミネートこそ5回ありますが(データ参照)、未だ無冠でした。うち3回はペドロ・アルモドバル作品です。彼をスカウトして『セクシリア』でデビューさせ、『欲望の法則』、『神経衰弱ぎりぎりの女たち』と起用した育ての親より先に受賞してしまった。アントニオが『マンボ・キングス/わが心のマリア』出演のためハリウッドに渡ったときのアルモドバル監督の失望は大きかったと言われています。別に他の監督作品に出演しなかったわけではないけれど。(写真下、プレス会見場で)

★スペイン・アカデミー発表の受賞理由:大西洋を挟んだ二つの大陸で、俳優として、監督として、製作者として、諸々の輝かしいキャリアでもってわが国の価値を高めるのに寄与してくれた。受賞は選考員の満場一致だった。・・・彼は、危険や厳しい状況を乗り越え、演技者の<戦士>として、国境を越えて活躍するマラガ人であり、幅広い優れた経歴の持ち主である(抜粋)。
★ハリウッドの重い扉を開けてくれたパイオニアの一人に違いありませんね。『セクシリア』(1982)から最新作のSF映画“Autómata”(2014)まで、トータルで90作以上に出演は、チョイ役でなかっただけに改めて感心いたします。当ブログで、メラニー・グリフィスと離婚して故郷マラガに新居を購入という記事を書いた時には、想像もしませんことでした(⇒6月21日)。ハリウッド作品では『フィラデルフィア』(93)、『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(94)、『デスぺラード』(95)、『エビータ』(96)、『マスク・オブ・ゾロ』(98)・・・と1990年代の活躍は目覚ましい。
★監督デビュー作品“Crazy in Alabama”(99、英語)が翌年のヨーロッパ・フィルム賞、サン・ジョルディ賞他を受賞、第2作“El
camino de los ingleses”(06)は、ベルリン映画祭2007ヨーロッパ・シネマ賞を受賞、ラテンビート2007で『夏の雨』の邦題で上映されました。
★主なる受賞:ゴヤ賞は無冠でしたが、2004年アカデミー「金のメダル」賞、2008年サンセバスチャン映画祭「ドノスティア」賞、2014年シッチェス・カタロニア映画祭「栄誉賞」をそれぞれ受賞しています。またペンシルバニア大学やマラガ大学の名誉博士号も貰っております。
★54歳とはいえ、二十代の初めに故郷マラガを後にマドリードに出て、ハリウッドを目指して既に35年のキャリアがある。90年代のスペインには、ハリウッドに行って自分を試すなんて慣例はなかった時代でした。「海外からやってくるものは、映画といわず全てが驚きだった。長い独裁政が終わって、社会全体を覆っていた、ある種のコンプレックスを打ち壊した。ハリウッドでの勝利は、多分一粒の種を播いたことになった」と、控えめながら自分もスペイン映画界に貢献しているという自負を受賞会見で覗かせました。
★「どんな資金難にも、決して降参しないぞ」と、決意のほどを熱く語ったバンデラス、「みんな、賞など重要じゃないと言いますが、それは貰うまでの話だ」と。貰ってみればその大きな威力というか素晴らしさに驚くというわけです。自分の経歴についての評価は他人がすることで、自分はあれこれ言う立場じゃない。しかしスペインの「偉大な巨人たち、フェルナンド・フェルナン・ゴメス(07没)、アグスティン・ゴンサレス(05没)、ホセ・ルイス・ロペス・バスケス(09没)など、私たち映画界の<バッファロー>に出会えて一緒に仕事ができたことは望外な<喜び>であった」と。最後にメラニー・グリフィスのことを訊かれたバンデラス、「彼女との関係は仕事だけ、遥か昔に彼女に出会い女優として感嘆した、その気持ちは今でも同じだよ」と応じていました。もう終わったことだよ、記者の皆さん。

★現在、三本の脚本を執筆中。サンセバスチャン映画祭コンペティションにサイエンス・フィクション“Autómata”(⇒9月16日)が公開された(これはゴヤ主演男優賞にノミネートされる確率が高い?)。テレンス・マリックの“Knight of Cups”(15英語)、カルロス・サウラの“33 dias”(15西・仏語)、ここではパブロ・ピカソになり、愛人の一人ドラ・マールにはグウィネス・パルトローが扮する。彼女は10代にスペインで暮らしたことがありスペイン語は堪能だそうです。ヒュー・ハドソンの“Altamira”(15英語)が目下撮影進行中という。ハドソン監督は『炎のランナー』(81)でアカデミー賞作品賞を受賞している。
*ゴヤ賞ノミネート作品*
1987 Matador『マタドール<闘牛士>炎のレクイエム』ペドロ・アルモドバル 助演男優賞
1991 Atame!『アタメ』ペドロ・アルモドバル 主演男優賞
1997 Two Much『あなたに逢いたくて』フェルナンド・トゥルエバ 主演男優賞
2012 La piel que habito『私が、生きる肌』ペドロ・アルモドバル 主演男優賞
2014 Justin and the Knights of Valour(Justin y la espada del valor)言語:英語
*長編アニメーション賞(ヴォイス出演)作品賞なので製作者がノミネートされました。
ゴヤ賞授賞式もマラゲーニョのダニ・ロビラに決定
★栄誉賞に先だって、ゴヤ賞2015授賞式の総合司会者もアナウンスされました(10月14日)。当ブログで何回か登場してもらったエミリオ・マルティネス・ラサロのコメディ“Ocho apellidos vascos”(2014)の主役ダニ・ロビラです。1980年マラガ生れの34歳とこちらも若返り。マラガは熱くなっている? 発表予定はもっと後だったようですが、マラガのメディアが嗅ぎつけて騒ぎだしたせいで急遽正式発表とあいなった。メイン司会者の資格は明記されているわけではないが「進行役として1年以上のキャリアがあること」が慣例になっていて、ロビラはそれを満たしていなかったという事情もあったらしい。ただし過去にもカルメン・マチやアントニア・サン・フアンが同じケースだった。

(嬉しさ半分、怖さ半分のダニ・ロビラ)
★現アカデミー会長エンリケ・ゴンサレス・マチョ自らが公表しました。例年通りテレビション・エスパニョーラがライブ放映する。
★ダニエル・ロビラは、「プッシュがあったとき思わずオーケーと言ってしまったが、後で考えてみたら怖くなってしまった。いまは嬉しさと恐怖が半々だが、ガラが近づいてきたら恐怖でいっぱいになると思う。責任重大なのは分かってるよ」と正直です。アタマの回転の速い人だし、舞台負けしない自信がある由、コメディアンの素質は“Ocho
apellidos vascos”で証明済み、本作で主演男優賞ノミネートは確実です(!)。2015年は栄誉賞受賞者と司会者がノミネートされるという大変な年になりそう。

★例年、政治的発言が取りざたされる授賞式ですが、ガラのシナリオはやはり欠かせません。ロビラはブラック・ユーモアというより「アイボリー・ホワイト」のユーモア派だそうです。オブラートに包んでやんわりやるのでしょうか。当日が楽しみです。
*大成功によりシリーズ化されるのか、続編が決まった“Ocho apellidos vascos”は、コチラにアップしております(⇒3月27日/5月13日)。
『フラワーズ』*東京国際映画祭2014 ① ― 2014年11月09日 15:42
★台風接近でラテンビートでの鑑賞を断念した『Flowers』を、共催上映した東京国際映画祭TIFFで見てきました。こちらのタイトルは『フラワーズ』、原題の“Loreak”の意味は「花」です。既にラテンビート2014③で作品データ・監督・キャスト他を紹介した記事(⇒9月22日)を、下記にコンパクトに纏めて再録しております。

サンセバスチャン映画祭オフィシャル・セレクションに初のバスク語映画
A: バスク自治州の都市サンセバスチャンで開催される映画祭も今年で62回を迎えました。まあ老舗の映画祭と言えますね。そこで話題になったのが本映画祭コンペ部門でバスク語映画が初めて選ばれたということでした。
B: オフィシャル・セレクション以外なら当然過去にもあった、お膝元の映画祭ですから。
A: フランコ時代は使用禁止言語だったからバスク語映画そのものが作れなかったし、学校で生徒が喋ろうものならムチで叩かれた。
B: でも考えると不思議ですよね。もうすぐフランコ没後40年になるんだから。
A: いいえ、当事者にとったらたったの40年です。ETAのテロが頻発したのはフランコ没後、最も血が流れた年は1980年、200回のテロで95人が犠牲になった。その「1980年」をタイトルにしたイニャーキ・アルテタのドキュメンタリー“1980”が、バジャドリード映画祭で上映され話題になりました。アルテタはETAにテーマを絞って映画作りをしている監督です。
B: 今年前半のメガヒット、エミリオ・マルティネス・ラサロの“Ocho apellidos vascos”は、テロだの爆弾だのは一切出てこないコメディ、そしてスリラーを加味させたヒューマンドラマの本作と、バスク映画も多様化の時代になりました。
A: サンセバスチャンには、プロモーションも兼ねて主演女優3人が花束を抱えて登場しました。大スクリーンで本作を見たエル・パイス紙の批評家カルロス・ボジェロは、「登場人物が自分たちが日常使っている言語で自然に演じていた。もしこれがカスティーリャ(スペイン)語だったら、こんなにしっくりした自然体で演じられなかったろう」と述べています。
B: セリフは多くなかったと思いますが、母語で演じることは論理的なことですよ。

(左から、ガラーニョ監督、ベンゴエチェア、アランブル、アイツプル、イトゥーニョ、
ゴエナガ監督 サンセバスチャン映画祭にて)
A: サンセバスチャンでの評価が高く、10月末に全国展開されることになりましたが、コピーはスペイン語吹替版になったようです。「この映画は登場人物の声で届けるべきですが、バイリンガルでの製作は資金的にできなかった」と、二人の監督は吹替版を残念がっていました。それでも国内の多くの観客に見てもらえるチャンスを喜んでいました。
B: 現在生粋のバスク人は、バスク語とスペイン語のバイリンガルなんでしょうね。日本ではバスク語版で見られたが、いずれにしろどちらでも分かりません。でも日本語吹替えだったらと思うとゲンメツです(笑)。スペインの吹替版上映は曲がり角にきています。そういう意味では、日本は本当に字幕上映<先進国>です。
孤独とコミュニケーションの難しさがテーマか
A: 花束は口を利きませんが、ここでは雄弁に語る、「花束は口ほどに物を言う」です。此岸の人のために、向こう岸に渡ってしまった彼岸の人のためにも語りかける花束だ。言葉で言えないことを表現するための有効な道具になっている。
B: 花に隠された言葉ですね。直線コースに突然現れるカーブ、暗い歩道を照らす街灯、ガードレール、ざわめく黒々とした木々、標識に固定された二つの花束が浮かび上がる、テレとアネが手向けた花束だ。
A: 道行く人、運転する人、旅する人が、この美しい花束に心が和らぐ。花束に添えられた思い出のカードや写真も静かに物語を奏でている。孤独と伝達の難しさを描いた点では、第1作“80 egunean”*の続編かもしれない。

(花束に添えられていたカードを読むアネ)
B: この物語は不安のなかに或る種のロマンを忍びこませて進んでいく。
A: アネと夫の関係はそれぞれ自分の殻に閉じこもって互いに無関心、だから喧嘩も起きない。そこへ匿名の花束が突然やってくる。空気がピーンと張りつめる。
B: 不信と不安を隠しきれない夫は、「匿名の人に住所も訊かず花を売っていいのか」と花屋にねじ込んで、花屋を呆れさせる。
A: そんな義務も法律もありません(笑)。医者から更年期を宣告され塞ぎこんでいたアネだが、夫以外の男性からの思いがけない花束に何故か心が華やぐ。
B: 一方テレは、息子ベニャトがバツイチのルルデスと結婚したのは仕方ないが、夫婦がもう子供はいらないと決めているのが納得できない。テレにとってルルデスの連れ子は孫ではない。この母子も夫婦も普通の会話が成り立たない。賢いベニャトは母の味方も妻の味方もせず、三人は孤立している。
A: ベニャトはアネと同じ職場で働いている。彼は大型クレーンの操縦をしており、高い操縦室から下界を双眼鏡で眺めている。この危険な個室にいるときが一番心が安らぐのだ。
B: ルルデスの職場はハイウエーの料金所のブース、やはり狭いボックスに閉じ込められている。これは象徴的なメタファーです。
*“80 egunean”(2010バスク語)のストーリー:少女だった遠い昔、親友だったアスンとマイテの二人はひょんなことから50年ぶりに邂逅する。アスンは農場をやっているフアン・マリと結婚するため引っ越して以来田舎暮らしをしていた。両親と距離を置きたい娘は離婚を機にカリフォルニアに移り住んでいる。レズビアンのマイテはピアニストとして世界を飛び回ってキャリアを積んでいたが既に引退して故郷サンセバスチャンに戻ってきた。別々の人生を歩んだ二人も既に70歳、不思議な運命の糸に手繰り寄せられて再び遭遇する。この偶然の再会はアスンに微妙な変化をもたらすことになる、自分の結婚生活は果たして幸せだったのだろうか。マイテにサンタ・クララ島への旅を誘われると、アスンは自分探しの旅に出ることを決心する。アスンにテレ役のイツィアル・アイツプル、マイテにマリアスン・パゴアゴが扮した。トゥールーズ・シネ・エスパニャ2011で揃って女優賞を受賞した。パゴアゴは本作がデビュー作。年輪を重ねた知性豊かな二人の女性のナチュラルな演技が観客賞に繋がった。

(アスン役のアイツプルとマイテ役のパゴアゴ)
巧みに張られた伏線を楽しむ
A: ベニャトの突然の事故死に三人の女性は直面する。もうアネに花束は届かない。ルルデスは夫がベランダで丹精をこめて育てていた花の鉢植えを残さず粉々に割る。自分に不意に訪れた不幸に耐えられない。
B: 観客には贈り主が分かるのだが、当事者たちが知るのはもっと後、特にルルデスは職場の同僚と暮らし始めている5年後だ。この同僚とは生き方の違いが伏線として張られており、幸せからはほど遠い。
A: アネが決定的に贈り主を知るのは職場で失くしたネックレスがクレーンの操縦室にあったから。冒頭で医者から更年期の始まりを聞いていたとき、ずっと弄っていたネックレスだ。かつて夫からプレゼントされたものだから唯のネックレスではない。それを知っててベニャトは操縦室にぶら下げていたのだ。 アネと一緒にいたかったのだ。
B: 嫁姑のいがみ合いの遠因の一つとして、夫婦がテレ名義のピソに住んでいたことが挙げられる。綺麗好きのテレには、嫁が掃除嫌いなのが耐えられない。自分が穢されていると感じる。
A: 夫婦の留守中にテレが部屋をピカピカにする理由を、観客はベニャトが死んで初めて知る。
B: ベニャトが双眼鏡で放牧されているヒツジを眺めるシーンが繰り返し出てくる。
A: 事故死の直接の原因は、夜道に迷い込んだヒツジを避け損ねたからだ。
B: 同じようなシーンが最後にもう一度出てきますね。
A: 死者というのは残された人々が想っているあいだは生きている。死者は生きてる人々を支配するのだ。残された人々が記憶を消したい、記憶が重荷になったとき、初めて本当の死者になる。
B: テレは息子を失った苦しみから逃れるように痴呆が始まる。時折り息子の名前さえ思い出せない。
A: アネにもベニャトは死者になりつつある。花束はもう手向けない。過去から逃れたいからだ。
B: ルルデスは夫が別の女性を想っていたことが許せない。もうこの世の人ではないというのに。5年後、医学用に献体していたベニャトが <灰になって> 帰還する。
A: ベニャトの遺灰はルルデスの手元に置かれることになるだろう。結局、花束は花束でしかなかったのかもしれない。
音楽監督パスカル・ゲーニュ
A: まだゴヤ賞予想は早すぎますが、音楽監督パスカル・ゲーニュ*が、もしかしたら候補になるかもしれない。彼はノルマンディー地方のカーン生れのフランス人ですが、1990年から本拠地をサンセバスチャンに移して、主にスペイン映画の音楽活動をしています。ビクトル・エリセやイマノル・ウリベ、モンチョ・アルメンダリスとコラボしています。
B: 前作“80 egunean”も、両監督のそれぞれ第1作も彼が担当。ラモン・サラサールの『靴に恋して』(02)は公開された。
A: ラテンビート2007で上映されたダニエル・サンチェス・アレバロの『漆黒のような深い青』や「スペイン映画祭2009」上映の『デブたち』、イシアル・ボリャインの『花嫁の来た村』や新作ドキュメンタリー“En tierra extraña”も担当している。
B: サンセバスチャンFFのパブロ・マロの“Lasa y Zabala”(コンペ外)も担当、つまり1914年製作の話題作3作を手掛けていることになる。
A: どれかがゴヤ賞候補になるのは間違いない、複数もありえるか。大分前になるがエドゥアルト・チャペロ≂ジャクソンの話題作“Verbo”が、2012年ゴヤ賞オリジナル歌曲賞にノミネートされた。
B: 本作で流れるシングソングライター、セシリアのベストセラー『スミレの小さな花束』(Un ramito de violetas)は、35年前にLPで発売された曲だそうです。
A: 今回調べたのですが、1974/75年、まだフランコ体制のときです。少し体制批判の匂いがあって検閲を受けたようです。映画ではスミレの花束ではありませんが、この歌を口ずさんで育った観客には懐かしいのではありませんか。
B: 二人の監督が生れた頃流行った曲、彼らの母親世代、テレの世代のの曲ですかね。
A: 両映画祭ともバスク語映画は初めてと思いますが、しみじみとわが身を振り返った味わい深い映画でした。
*パスカル・ゲーニュ Pascal Gaigne:1958年フランス生れ、1990年よりサンセバスチャン移住。作曲家、映画音楽監督、演奏家。ポー大学で音楽を学ぶ。トゥールーズ国立音楽院でベルトラン・デュプドゥに師事、1987年、作曲とエレクトロ・アコースティックの部門でそれぞれ第1等賞を得る。映画音楽の分野では短編・ドキュメンタリーを含めると80本を数える(初期のアマヤ・スビリアとの共作含む)。演奏家としてもピアノ、シンセサイザー、ギター、バンドネオン他多彩。『マルメロの陽光』ではバンドネオンの響きが効果的だった。以下は話題作、代表作です(年代順)。

1984『ミケルの死』 監督:イマノル・ウリベ(アマヤ・スビリア共作、スペイン映画祭1984)
1992『マルメロの陽光』 監督:ビクトル・エリセ(公開)
1998“Mensaka” 監督:サルバドール・ガルシア・ルイス
1999『花嫁の来た村』 監督イシアル・ボリャイン(シネフィルイマジカ放映)
2001 “Silencio roto” 監督:モンチョ・アルメンダリス
2002『靴に恋して』 監督:ラモン・サラサール(公開)
2003“Las voces de la noche” 監督:サルバドール・ガルシア・ルイス
2004“Supertramps” 監督:ホセ・マリ・ゴエナガ(デビュー作)
2006『漆黒のような深い青』 監督:ダニエル・サンチェス・アレバロ(LB2007上映)
2007“siete mesas de billar francés” 監督:グラシア・ケレヘタ
2009『デブたち』 監督:ダニエル・サンチェス・アレバロ(スペイン映画祭2009上映)
2010“Perurena” 監督:ジョン・ガラーニョ(バスク語、デビュー作)
2010“80 egunean” 省略
2011“Vervo” 監督:エドゥアルト・チャペロ≂ジャクソン(2012年ゴヤ賞歌曲賞ノミネート)
2014“En tierra
extraña” 監督イシアル・ボリャイン
2014『フラワーズ』 省略
2014“Lasa y Zabala” 監督:パブロ・マロ
*“Loreak”『フラワーズ』データ*
製作:Irusoin / Moriarti Produkzioak
監督:ジョン・ガラーニョ& ホセ・マリ・ゴエナガ
脚本:アイトル・アレギAitor Arregi /ジョン・ガラーニョ/ホセ・マリ・ゴエナガ
製作者:アイトル・アレギ/ハビエル・ベルソサ Berzosa/フェルナンド・ラレンドLarrondo
撮影:ハビエル・アギーレ
音楽:パスカル・ゲーニュ
データ:スペイン、2014、バスク語、99分 スペイン公開10月17日
*サンセバスチャン映画祭オフィシャル・セレクション(9月22日)、チューリッヒ映画祭(9月28日)、ロンドン映画祭(10月18日)など多数。
キャスト:ナゴレ・アランブル(アネ)、イツィアル・アイツプル(テレ)、イツィアル・イトゥーニョ(ルルデス)、ジョセアン・ベンゴエチェア(ベニャト)、エゴイツ・ラサ(アンデル)、ジョックス・ベラサテギ(ヘスス)、アネ・ガバライン(ハイオネ)、他
プロット:三人の女性に人生の転機をもたらした花束の物語。平凡だったアネの人生に、ある日、匿名の花束が家に贈り届けられる。それは毎週同じ曜日、同じ時刻に届けられ、やがて、その謎につつまれた花束は、ルルデスとテレの人生にも動揺を走らせることになる。彼女たちが大切にしていたある人の記憶に結びついていたからだ。忘れていたと思っていた優しい感情に満たされるが、夫婦の間には嫉妬や不信も生れてくる。結局、花束は花束でしかない。これはただの花束にしか過ぎないものが三人の女性の人生を変えてしまう物語です。 (文責:管理人)
★監督紹介
*ジョン・ガラーニョ Jon Garano :1974年サンセバスチャン生れ、監督、脚本家、製作者、編集者。2001年短編“Despedida”でデビュー、短編、ドキュメンタリー(TVを含む)多数、短編“Miramar Street”(2006)がサンディエゴ・ラティノ映画祭でCorazón賞を受賞。長編第1作“Perurena”(バスク語2010)のプロデューサーがホセ・マリ・ゴエナガ、彼とコラボしてバスク語で撮った第2作“80 egunean”(“80 Days”2010)が、サンセバスチャン映画祭2010の「サンセバスチャン賞」を受賞したほか、トゥールーズ・シネ・エスパニャ2011で観客賞、女優賞(イツィアル・アイツプル、マリアスン・パゴアゴ)、脚本賞を受賞したほか、受賞多数。イツィアル・アイツプルは第3作“Loreak”でテレを演じている。
*ホセ・マリ・ゴエナガ Jose Mari Goenaga:1976年バスクのギプスコア生れ、監督、脚本家、製作者、編集者。短編“Compartiendo Glenda”(2000)でデビュー、長編第1作“Supertramps”(2004)、第2作がジョン・ガラーニョとコラボした“80 egunean”、受賞歴は同じ。本作が3作目となる。

(チューリッヒ映画祭で歓迎を受ける両監督、左ゴエナガと右ガラーニョ、9月28日)
★キャスト紹介
*ナゴレ・アランブル(アネ役)Nagore Aranmburu:バスクのギプスコア(アスペイティア)生れ。1998年TVドラマでデビュー、フェルナンド・フランコの“La herida”(2013、ゴヤ賞2014作品賞受賞他)に出演している。
*イツィアル・アイツプル(テレ役)Itziar Aizpuru:1939年生れ。2003年TVドラマでデビュー、前述の“80 egunean”以外の代表作はオスカル・アイバルの“El Gran Vazquez”(2010)、TVドラマ、短編など出演多数。
*イツィアル・イトゥーニョ(ルルデス役)Itziar Ituño:1975年バスクのビスカヤ生れ。Patxi Barkoの“El final de la noche”(2003)の地方紙のデザイナー役でデビュー、サンセバスチャン映画祭のオフィシャル・セレクション外にエントリーされたパブロ・マロの“Lasa y Zabala”に出演(時間切れで未紹介ですが、1983年のETAのテロリズムがテーマ)。ほかバスク語のTVドラマに出演している。
『ヴォイス・オーヴァー』*東京国際映画祭 ② ― 2014年11月13日 21:35
★サンセバスチャン映画祭SIFF 2014「オフィシャル・セレクション」ノミネート作品、クリスチャン・ヒメネス監督は3度目の来日、今回は女性プロデューサー、ナディア・テュランセブとジュリー・ガイエのお二人と一緒でした。SIFFにはスタッフとキャストが揃って参加、話題のジュリー・ガイエさんはパパラッチに追いかけられたようです。TIFFでは2回上映されたうち10月25日のQ&Aを織り混ぜて少しお喋りします。

(SIFFでの監督、ガイエ、テュランセブ)
製作:Rouge
International / Jirafa Films / 1975 Productions
監督・脚本・撮影・製作者:クリスチャン・ヒメネス
共同脚本:ダニエル・カストロ
共同撮影:インティ・ブリオネス
製作者:総指揮アウグスト・マッテ/ブルーノ・ベタティ/ナディア・テュランセブ/
ジュリー・ガイエ/ニコラ・コモー他
編集:ソレダド・サルファテ
音楽:アダム・バイト他

データ:チリ≂フランス≂カナダ合作、スペイン語、2014年、コメディ、96分 チリ公開2015年
出演:イングリッド・イセンセ(妹ソフィア)、マリア・シーバルド(姉アナ)、パウリナ・ガルシア(母マティルデ)、クリスチャン・カンポス(父マヌエル)、マイテ・ネイラ(ソフィア娘アリシア)、ルーカス・ミランダ(ソフィアの息子ロマン)、ニールス・シュナイダー(アナの夫アントワン)クリストバル・パルマ(ソフィアの元夫カリシム)、センダ・ロマン(姉妹の祖母マミ)、バネッサ・ラモス(父の恋人)他
プロット:最近離婚したばかりの美人のソフィアは35歳、2人の子どもを引き取って育てている。最近、彼女の人生は何もかも悪いほうへと転がっていく。父が母を残して出て行ってしまうかと思うと、姉が家族を連れてチリに戻ってきた。彼女流儀の論理でかき回すからイライラは募るばかりだ。ソフィアのベジタリアンは親戚から顰蹙を買っている。成長期の子どもたちに肉を食べさせないのは栄養学的にも間違っていると。更にはふとしたことから父親の不愉快な秘密が次々と明るみに出て、父娘関係もギクシャクしてくる。
「フレームの外」で語られていることが現実
A: サンセバスチャン映画祭では主役のイングリッド・イセンセより、製作者の一人ジュリー・ガイエが注目を集めてしまいました。
B: 新年早々フランス大統領フランソワ・オランドとの不倫疑惑報道があり、「大統領のチャーミングな恋人来る」で、餌食にしようとパパラッチが待ちかまえていた。
A: プライバシー侵害として記事を載せた芸能誌を告訴している。プロデューサーの仕事は『盆栽』から参加、監督との出会いはここ東京国際映画祭2009です。監督はデビュー作『見まちがう人たち』、ジュリー・ガイエはシャビ・モリアのデビュー作『エイト・タイムズ・アップ』で来日して知りあった。
B: 脆弱さとタフさを兼ね備えたヒロインの演技が評価されて最優秀女優賞を受賞したんでした。さて、そろそろ肝心の本題に。冒頭から登場人物がどっと押し寄せて、それもショッキングな出産シーンを家族で見ているところから始まる。
A: 最初はアナの出産シーンを家族みんなで見ているのかと錯覚してビックリする。アナの夫アントワンの母親が撮ったビデオと分かるのだが、この「枠・フレーム」に入った映像を見るというのが一つのテーマだった。映画のナレーションのように「枠」に映っていない「枠外」で起きていることに耳を澄ますと言い直してもいいようです。「語られないヴォイス=セリフが重要」だからタイトルは<ヴォイス・オーヴァー>なんですね。

(TIFFでのテュランセブ、監督、ガイエ)
B: Q&Aでは、「見えているもののフレームの外で語られていることが現実」で重要であると話していた。アントワンの母親は「枠外」に、つまり姿を現さないのだが、家族も観客も彼女の視点で撮られたビデオを見ていることになる。
A: テレビとかパソコンの映像を見るシーンが繰り返し出てくるが、テレビもパソコンも一種のフレームですね。そしてソフィアに、大分前から映画もテレビもインターネットも読書も遠ざけて暮らすという、相当ラディカルでストイックな選択をさせている。この人格と「枠外」は興味深い。監督のアタマの中は複雑だから、説明してもらわないと分かりにくいね。
幼児化してチリで暮らすプチブル階級
B:「家族の映画を撮ろうとしたとき、場所はバルディビアでなくてもいいと考えた。ただ大都市でないこと、小さい都市でも大学があって知的階層の人が住んでいること、世界と繋がっていることが必要だった」と述べていた。
A: チリの都市ならどこでもということなのか、世界のどこの都市でもなのか分からなかったが、要するに生れ故郷バルディビアはぴったりだったというわけです。生活臭の希薄なインテリのプチブル階級が住んでる場所が条件ね。
B: 「ソフィアとアナの造形には、私の二人の妹たちの人格が流れ込んでいる」と明かしていました。
A: サンセバスチャンのプレス・インタビューでも、「ウチの家族はお喋りの才能があって、話をしながら食事をする。そのとき聞いたエピソードを思い出しながら、素材に手を加えたり削ったり、ときには強調もいれてミニ・プロットを作っていく」と語っていました。個人的な家族の経験が流れ込んでいるようです。
B: 友人知人から聞いた話をメモして膨らませて行くらしいから、プライバシーを保ちたいなら監督との雑談は要注意です(笑)。
A: 登場人物が多すぎて1回見ただけだと家系図があやふやです。この家族は両親も娘も離婚しているのだが、その理由は「枠外」で分からない。母親は夫が自分を捨てて出て行ってしまったことが信じられない。父親は性懲りもなく、もう一度の青春を夢見ているモラトリアム人間。
B: 突然帰国した姉一家は、家探しをするがケチをつけてずっと実家に居座っている。年下らしい夫アントワンもアナのいいなりでお気楽に見える。誰も彼も自分勝手でジコチュウすぎて素直に笑えない。
A: 大人は幼児化して観客はなかなか自分を重ねられない。まともなのは両親の離婚のせいであっちこっちと行ったり来たりを強いられる二人の子供だ。子供の視点を入れたことで、前作より視点が複眼的になったかな。
B: 子供が釘を踏むシーンは、実は「私自身に起きたこと」と会場を笑わせていた。「私自身」が踏んだ後、痩せ我慢して「痛くない」と言ったので妹さんが踏んだ(笑)。本当は痛い。
苦しみや痛みを語ること・語らないこと
A: このシーンのメタファーは何かしらね。観客を笑わせるために入れたとは思えない。大体さらっと表層だけ見たら何も残らないコメディだ。色眼鏡をかけなくてもいいが、なにしろチリという国は、独裁者ピノチェトが16年間も君臨した国、彼が没してからでも10年にならない。これを除外してチリの映画を見るのは難しい。
B: 現在でも親ピノチェト反ピノチェトが30%ずつ、残りはどちらでもない人です。死者・行方不明者は公式には3196人と少ないが、実際に人権侵害を受けた人は10万人とも、亡命者は当時の人口の10%に当たる100万とも言われている。無視はできない。
A: 秘密を抱えていない家族は少ないし、口に出しては生き残れなかった人も多かった。メタファー探しなど無意味という意見があってもいいけど、作品が作り手から離れたら判断や解釈は観客に委ねられる。これは映画に限らない、作品は一人歩きを始めるからね。
B: この映画はチリで起きている苦しみや痛みのメタファーとして目に見えるようには語られていないが、「語られていないのは事実だけれど、完璧に見えてきてしまう」し、「物事を隠したままにしておかないことが必要です、結局記憶は取り戻されるから」と、サンセバスチャンでイングリッド・イセンセ(ソフィア役)も語っていた。
A: Q&Aの最後のほうで監督は、ナチの強制収容所の生存者のドキュメンタリーに触れて「親世代が苦しみを語らなかった家族の子供は、収容所に入ったことがないのにストレスをより多く感じていた」が、「反対に親世代が語った家族の子供は、それほどトラウマを抱えていなかったことが、この映画のアイディアの一つだった」と語っていた。
B: 語られていないことが親から子へ伝達され受け継がれていってしまう、語らないことでより強くストレスを感じてしまうと。
A: 痛みや苦しみが存在しても、言葉のレベルでそれを伝達せず断絶してしまうと、そこに混乱や苦悩、喧騒や汚染が世代から世代へと受け継がれていくということですかね。しかし伝達は複雑で、糸電話遊びのようにとんでもない方向に行ってしまうから難しい。
チリ映画にはカスティーリャ語字幕が必要―-コミュニケーションの困難さ
B: 物語はソフィアを中軸に進行する。妹は前進しつづけるには互いに理解しあい、人の話に耳を傾け、きちんと整頓していきたいタイプ。対照的に姉は頭もよく博士号をもっている自立したしっかり者、テキパキと仕事をこなすが強引なタイプ。
A: 水と油です。ソフィアは子供がいるから親であり、両親にとっては子供、祖母マミに対しては孫である。そして姉アナの妹です。別れた夫に対しては元妻だ。人間はたいてい何役も兼ねる存在です。この元夫はターバンをしていたから、もしかしたらシーク教徒なのかしら。
B: バルディビアでは珍しくないのか、これは意外な設定でした。アナの夫アントワンも外国人で慣れないスペイン語に苦労していた。このコミュニケーションの困難さもテーマの一つですか。

A: 実際アントワンを演じたニールス・シュナイダーはカナダ人で、少しはスペイン語が喋れたようですが訛りの強い「チリ弁」には四苦八苦したらしい。SIFFではチリ弁も一応スペイン語だから西語字幕は付かなかった(笑)。それでネイティブ観客から苦情が出た。
B: 「カスティーリャ語の字幕をつけろ」ですね。映画祭での評価がイマイチだったのには、この苛々も原因だったかもしれない。
A: 私たちは英語字幕の翻訳で見たわけで、チリ弁だろうがカスティーリャ語だろうが関係ないと思うでしょうが、重訳で見るわけですから、こんなこと書籍だったら絶対に許されない。
B: 姉妹同士の軋轢というのは、兄弟同士ほどそんなに描かれていないのでしょうか。
A: どうでしょうか。アン・リーやエドワード・ヤンの家族をテーマにした映画は見ていたようですが、敢えて参考にしなかったようです。もっと違った切り口にしたかったらしい。
B: つまり、アン・リーの『いつか晴れた日に』とは違うものという意味ですか。
A: エドワード・ヤンでは『ヤンヤン夏の思い出』などを想像しますが、個人的な自分の家族が関わった映画を作りたかったのではないですか。
チリの若手監督グループ<ジェネレーションHD>の躍進
B: ラテンビートで上映された、アンドレス・ウッドの『マチュカ』や『サンティアゴの光』、パブロ・ララインの『トニー・マネロ』や『NO』、セバスティアン・シルバの『家政婦ラケルの反乱』や『マジック・マジック』『クリスタル・フェアリー』など、今年はフェルナンデス・アルメンドラスの『殺せ』がエントリーされ、ジャンルもテーマも多彩になってきた。
A: 昨年はセバスティアン・レリオの『グロリアの青春』が話題をさらった。<ジェネレーションHD>と言われる「クール世代」に属しているようです。『殺せ』と本作は方向が違うように見えますが、チリの社会構造、過去の歴史に拘っている点では同じともいえます。本作は配給元もCinema Chileに決まって2015年の公開が決定しました。チリの観客がどんな反応をするのか気にかかります。
関連ブログ:
『NO』 ⇒2013・9・21
『家政婦ラケルの反乱』 ⇒2013・9・27
『マジック・マジック』 ⇒2013・9・26/10・26
『クリスタル・フェアリー』 ⇒2013・9・25/10・29
『殺せ』 ⇒2014・10・8/10・30
『グロリアの青春』 ⇒2013・9・12
スタッフ
*クリスチャン・ヒメネスCristián Jiménez :1975年チリのバルディビア生れ。デビュー作『見まちがう人たち』と第2作『Bonsai~盆栽』が東京国際映画祭2009と2011で上映され、2回ともゲスト出演のため来日した。チリ「クール世代」の代表的な若手監督。
◎監督フィルモグラフィー
2009『見まちがう人たち』サンセバスチャン映画祭2009、ブラチスラヴァ(スロバキア)映画祭2009でエキュメニカル審査員スペシャル・メンション賞、ケーララ(インド)映画祭2010出品。
2011『Bonsai~盆栽』カンヌ映画祭2011「ある視点」出品、ハバナ映画祭2011国際批評家連盟賞受賞、マイアミ映画祭2012グランド審査員賞受賞他。
2014『フラワーズ』トロント映画祭、サンセバスチャン映画祭「オフィシャル・セレクション」、リオデジャネイロ映画祭、チューリッヒ映画祭、ハンブルク映画祭、ストックホルム映画祭、各2014年。

*ジュリー・ガイエ Julie Gayet :1972年フランスのシュレンヌ生れ、女優、脚本家、製作者。公開作品では、エリ・シュラキのコメディ『君が、嘘をついた。』(95)、アルノー・ヴィアールの『メトロに恋して』(04)、パトリス・ルコントのコメディ『ぼくの大切なともだち』(06)などに出演。前述のTIFF2009コンペティション、『エイト・タイムズ・アップ』で最優秀女優賞を受賞した。ヒメネス監督とは『盆栽』に続いてのコラボである。話題提供に貢献したので特別に紹介。

(左から、ナディア・テュランセブ、ジュリー・ガイエ SIFF上映後の記者会見)
キャスト
*イングリッド・イセンセ Ingrid Isensee : 1974年チリのサンチャゴ生れ、『Bonsai~盆栽』に脇役で出演、今回主役ソフィアを射止めた。他にマリアリー・リバスの“Joven y alocada”(2012)に出演、本映画祭2012の「ホライズンズ・ラティーノ」部門の上映作品。今年短編“El Puente”で監督デビューした。
*マリア・シーバルド María José Siebald : 本作の他、エリサ・エリアシュのコメディ“Aqui Estoy, Aqui No”(2011)、ロドリーゴ・セプルベダの“Aurora”(2014)など。
*パウリナ・ガルシアPaulina García:1960年チリの首都サンティアゴ生れ。女優、監督、劇作家。チリ・カトリック教皇大学の演劇学校で演技を学び、のち同校の演劇監督、劇作家の資格を得た。現在は母校で後進の指導にもあたっている。映画デビューが2002年と比較的遅いのは、このような経歴から舞台女優として出発(1983)、合わせてテレドラ出演の成功でお茶の間の人気を博したせい。チリではPaly Garcíaのニックネームで知られている。社会学者の夫とのあいだに3人の子供がいる。セバスチャン・レリオの『グロリアの青春』(2013)国際的な賞を独り占めの圧倒的な演技が記憶に新しい。この凄いバイタリティーは人生を諦めてリングにタオルを投げさせなかったグロリアにも通じている。≪ラテンアメリカのメルリ・ストリープ≫とか。サンセバスチャン映画祭2013の審査員の一人に選ばれた。
2002“Tres noches de un sábado”ホアキンEyzaguirre監督、Altazor賞ノミネート
2004“Cachimba”シルビオ・カイオツィ監督
2007“Casa de remolienda”ホアキンEyzaguirre監督
2012“Gloria”『グロリアの青春』セバスティアン・レリオ監督、リオデジャネイロ映画祭2014、トロント映画祭「コンテンポラリー・ワールド・シネマ」出品、チューリッヒ映画祭2014、他
2013“Las
analfabetas”モイセス・セプルベダ監督デビュー作
2013“I am from Chile”ゴンサロ・ディアス監督デビュー作
『ロス・ホンゴス』*東京国際映画祭2014 ③ ― 2014年11月16日 22:59
★スペイン語映画の3本目は、最近紹介されることの多くなったコロンビア映画、邦題「ロス・ホンゴス」についての文句は後回しにして、麻薬密売物ではないもう一つのコロンビアが描かれていた。コンペティション部門で3回上映という破格の扱い、ルイス・ナビア監督と製作者ゲルリー・ポランコ・ウリベさんとのQ&Aを織り混ぜております(司会者:プログラミング・ディレクター矢田部吉彦氏、鑑賞日10月25日)。

*『ロス・ホンゴス』“Los hongos”*
製作: Contravia Films / Burning Blue / Arizona Films
監督・脚本:オスカル・ルイス・ナビア
共同脚本:セサル・アウグスト・アセベド 他
撮影:ソフィア・オッジョーニ・ハティ
美術:ダニエル・シュナイダー/アレハンドロ・フランコ
音楽:Zalama Crew / La Llegada del Dios Rata / セバスティアン・エスコフェ
編集:フェリペ・ゲレーロ
プロデューサー:ゲルリー・ポランコ・ウリベ
グラフィティ・アーティスト:Fuzil--Arma Gráfica / Mario Wize / La Pulpa
/ Repso / Mesek
データ:コロンビア≂仏≂独≂アルゼンチン合作、スペイン語、 2014、103分、アジアン・プレミア
*ベルリンFFのワールド・シネマ基金、ロッテルダムFFのヒューバート・バルズ基金、イタリアのトリノフィルム・ラボ、ブエノスアイレス・ラボ、カンヌFFのシネ・フォンダシオン・レジデンスの支援を受けて製作された。
受賞歴:ロカルノ映画祭2014(スイス)特別審査員賞受賞&金の豹賞ノミネート
ロッテルダム映画祭2014 ヒューバート・バルズ基金ライオンズ・フィルム賞(Hubert Bals Fund Lions Film)受賞/TIFF 2014コンペティション出品
*トロント、サンセバスチャン、トリノ、カイロ、セビーリャ・ヨーロッパ、各映画祭2014に正式出品。

キャスト:ジョバン・アレックシス・マルキネス(RAS)、カルビン・ブエナベントゥーラ・タスコン(カルビン)、アタラ・エストラーダ(カルビンの祖母)、グスタボ・ルイス・モントーヤ(カルビンの父グスタボ)、マリア・エルビラ・ソリス(RASの母マリア)、ドミニク・トネリエ(カルビンのガールフレンド)、アンヘラ・ガルシア(パンク・バンドのリーダー)、他
ストーリー:RASは建設現場の仕事を終えると、毎晩、近所の壁に落書き(グラフィティ)をしている。RASと母親のマリアはパシフィック・ジャングルからカリ東部の町へ移住してきた。RASは眠れない日々が続き白昼夢を見始める。そんな息子を見てマリアは、息子が何かに憑りつかれ、そのうち正気を失うのではないかと心配する。ある日、RASは職を失う。現場からペンキの缶を盗み、家の隣の壁に巨大な絵を描いていたからだ。彼はもうひとりの若いグラフィティ・アーティスト、カルヴィンを探しにいく。ふたりは目的もなく町をさまよう。さながら、道に迷って戻れなくなることを望むかのように。 (TIFF公式プログラムより引用)
★監督キャリア紹介
オスカル・ルイス・ナビアOscar Ruiz Navia:1982年カリ生れ、監督、脚本家、プロデューサー他。コロンビア国立大学の映画学校で学んだあと、バジェ大学の社会情報科を卒業。アントニオ・ドラド・スニェガの“El Rey”(2004)に撮影アシスタントとして参加(これはフィクションであるがカリの麻薬密売王をモデルにした映画)、カルロス・モレノの話題作“Perro come perro”(08)では助監督になった。2006年、バジェ大学の社会情報科の卒業生が設立したContravia Filmsに参加、長編デビュー作“El vuelco del cangrejo”(2009 英題Crab Trap)の製作会社、ベルリン映画祭2010「フォーラム」部門に出品され、批評家連盟賞を受賞したほか、数々の国際映画祭で高評価を得た。また2012年には、ウイリアム・ベガのデビュー作“La sirga”(英題“The
Towrope”)をプロデュースした。カンヌ映画祭2012「監督週間」に出品されたほか、トロント、サンセバスチャン、ロンドン、ハバナなど各映画祭に出品された。
*主なフィルモグラフィー*
2006“Al vacio 1,2,3”(短編)
2008“En la barra hay un Cerebro”(短編ドキュメンタリー)
2009“El vuelco del
cangrejo”ベルリンFFの他、ブエノスアイレス・インディペンデント・シネマ2010「特別メンション」、フライブルク映画祭2010、ハバナ映画祭2009、ラス・パルマス映画祭2010などで受賞している他、ノミネーション多数。
2013“Solecito”(短編)オーバーハウゼン国際短編映画祭2014「特別メンション」を受賞、他
2014“Los hongos”邦題『ロス・ホンゴス』(上記)
この映画の真髄は「生」である
A:: Q&Aは監督が英語、プロデューサーがスペイン語というわけで通訳者二人、やはりこれが難物、時間が掛かりすぎてヤキモキするね。日本の印象、礼儀正しいとか食事が美味しいとかは省略しよう。
B: 何故生れ故郷カリに戻って映画を撮ろうとしたか。カリにいなかったようですね。
A: お祖母さんがガンに罹って看病のために戻った、結局亡くなってしまったのだが、このことがきっかけでカリを舞台にバックグラウンドの違う二人の青年を軸にした「死から生」への物語を撮ろうと考えた。祖母の死というかなり個人的な「痛み」が構想の出発点だったようです。コロンビアのプレス会見では、亡くなったのは5年前と語っていたから、だいぶ前から温めていたようです。
B: 監督によれば、「みんなキノコというタイトルだと聞くと、ドラッグとか快楽とか幻覚的なイメージをもつかもしれませんが、このタイトルのメタファーは、腐敗とか死が充満しているなかに突然現れてくる生と希望のシンボルとしてのキノコなんです」と。こう要約してよかったでしょうか。
A: サイケデリックとは全く反対ということですね。キノコは光が届かないジメジメした場所で葉緑素なしで生きていけるし、腐敗したものに生える寄生生物だから「生」とはかけ離れた印象があるけど、腐敗=死から新しい命=生が現れるのも事実です。腐敗した世の中で生きている青年二人に新しい生が訪れる映画です。
沈黙しないよう学ぶための実践マニュアル映画
B: サンティアゴ・デ・カリは、太平洋に面したコロンビア南西部に位置するバジェ・デル・カウカ県の県都です。首都ボゴタ(700万)、メデジン(230万)につづいて三番目に人口の多い大都市です(220万)。麻薬密売、バイオレンス、殺人、誘拐、汚職、ゲリラなど、コロンビアのイメージは日本人にはあまり芳しくない。
A:: ラテンビート上映の『デリリオ―歓喜のサルサ―』でも触れましたが、負の遺産が多すぎる。社会の中に道徳や公正さが失われ腐敗があることは否定できない。コロンビアで政治と無縁の映画を撮ることは出来ないが、しかし、そこに新しい血液を注ぎ込むことは出来る、と監督の世代のシネアストたちは考えているようです。
B: RASとカルビンは、まだ自分のしたいことが分からないが、グラフィティ・アーティストとして自分たちの考えを壁に描くことで表現しようとする。しかし他人の家の壁に描くわけだから許されないわけですね。
A: 本作に出てくるグラフィティ・アーティストたちは、全員ホンモノで有名人だそうです。彼らの協力を得られたことも成功の理由の一つ。社会の不合理に沈黙しないことがテーマでもあるね。別のセクターに育った二人の若者の友情と都市文化を融合させるにはどうしたらいいか、それが難しかった。グラフィティに辿りついて構想が固まっていった。
お祖母さん役は私の本当の大叔母です!
B: 本作は群衆劇ですが、スペイン語では「合唱劇」といわれる。こちらのほうがぴったりする。
A:: 最初は無関係だった登場人物がやがて自然に調和してハーモニーを奏でていくからね。
B: Q&Aの最初の質問者がお祖母さんの生き方や演技を褒めたら、観客から期せずして温かい拍手が沸いた。毎年滋賀県から見に来る有名人らしい(笑)。
A: 主催者にとって、こういう観客は貴重な存在だね。監督が「実は私の本当の大叔母です。あのクレージーな父親も私の父親なんです」と答えて、これまた会場は爆笑に包まれた。

(発声練習をするクレージーなお父さん、グスタボ・ルイス・モントーヤ)
B: 二人の青年がアマチュアなのは直ぐ分かりましたが、全員が映画初出演ということでしたか、ちょっとはっきり聞きとれなかった。
A:: 全くのアマチュアだけというわけでもないようですが、最初に浮かんだアイディアは登場人物は現実にそれをやってる人に、アーティストの役はカリのマリオ・ワイズを筆頭に実際のアーティストに出てもらう、ミュージシャンも同じようにということだった。一番難しかったのは、RASとカルビンの二人の主人公、それはまるで「藁小屋で落とした針を探す」ようなものだった。
B: 全エストラート*の教育センターを巡って約700人ぐらいの若者にインタビューした。
A:: カルビン・ブエナベントゥーラ・タスコンが演じたカルビンは、アントニオ・ホセ・カマチョ学校で見つかった。まだ大人になりきっていない体つきと優しい顔つきがぴったりだった。タトゥとピアスをして、両親が離婚したので癌治療中のお祖母さんと暮らしているという設定だった。
B: RASは絵を描くことが好きなアフロ系の青年、そのうえスケボーができることが条件だったのでジョバン・アレックシス・マルキネスは願ったり叶ったりだったとか。
A:: 宗教的にはラスタファリズムというアフリカ回帰のジャマイカの宗教を信じていて、そういう宗教的なグラフィティを描く。昼間は建設現場で働くということにした。
B: カルビンの父親と祖母は監督が述べた通りですね。楽しんで演じていたのが伝わってきた。
A:: RASの母マリアに扮したマリア・エルビラ・ソリスはパシフィックの歌手、役柄もパシフィック・ジャングルからカリに移ってきた母子という設定だった。デビュー作“El vuelco del cangrejo”の舞台がそこで、太平洋に面したブエナベントゥーラ市の近くです。マリアのように白人と黒人の混血ムラートやメスティーソ、黒人が住んでいる地域です。
B: カルビンのガールフレンドのドミニク・トネリエは、パリで演技を学んでいたから全くのアマチュアではない。名前から判断するにフランス系の人ですね。
A: 女性のパンク・バンドのリーダーになったアンヘラ・ガルシアはモデルをしている。この二人の女性からはRASもカルビンもそこそこに遊ばれて、結局はぐらかされてしまう(笑)。二人はまだコドモです。

(卵料理を食べるRASと母マリア)
A:: お父さんも相当ユニークだが、お祖母さん役のアタラ・エストラーダの演技してない演技が光った映画でした。家族アルバムを説明するシーンで使われたのもホンモノだということでした。ここでコロンビアの歴史の一端を語らせる巧みな演出に感心しました。
B: お祖母さんは癌の放射線治療を受けているのか、髪をスカーフで包んでいる。痒くて眠れないと言うと、孫のカルビンが寝入るまで優しく頭皮を揉んでやる。
A:: このシーンね、デビュー作にも出てくる。主人公が絶望で死にそうになっているとき、女の子が優しく頭を揉んでやる。ああ、これは監督が実際にやってやったり、してもらったりしているんだな、と感動したんです。
B: グラフィティも音楽も素晴らしかったが、こういう一見何でもないシーンが観客を惹きつけるんですね。

(ポスターをバックにお祖母さんになったアタラ・エストラーダ)
ロス・ホンゴスかロス・オンゴスか、どっちでもいい?
B: タイトル「Los hongos」のスペイン語の意味は、カタログ解説にあるように特別「マッシュルーム」を指しているわけではなく、「キノコ・菌類」のこと、スペイン語はHを発音しないから「オンゴス」にして欲しかった。
A:: 困った題名の一つかな、クレームつけてるブログがあった。個人的には上映してくれるだけで満足すべきと諦めているから「どっちでもいい派」なんです。しかし1年前、最初のタイトル「ブランカニーヴス」にクレームがついたことで、公開時には『ブランカニエベス』に訂正されたことがあった。文句言った人の知名度が物を言ったのかも(笑)。
B: 誰が見ても聞いても意味不明だから、作品がイメージできない。英語のカタカナ起しは長いと幾度目にしても記憶できないが、もう市民権を得ましたね。
A:: 本作はデビュー作のように英題がまだ決まってないらしく、映画祭でのプレミアは仕方なかったのでしょう。最後のシーンで二人が登る大木は、サマネア・サマンといって中南米に主に生息する。葉っぱから垂れ下がっている白いものがオンゴスです。大木に寄生しながら「死から生」へ向かう、未来を二人が確信するシーンです。
B: 記憶に残る美しいシーンでしたが、ちょっとあり得ない展開でした。最後にきて飛躍が起こった印象でした。

(サマネア・サマンの木の下のRASとカルビン)
A: このブログはまだ1年ちょっとしか経っていませんが、アンドレス・バイス、フランコ・ロジィ、リカルド・ガブリエリなど、既にコロンビア映画を10本ほど記事にしています。テーマも切り口も多様、最近の躍進ぶりは5年ほど前のチリ映画を思い起こさせます。オスカー賞2015のコロンビア代表作品に選ばれたのは、マリア・ガンボアのデビュー作“Mateo”と、これまた新星現るで、裾野が広がってきたことは間違いありません。

*エストラートestrato:1993年に創設された「社会プログラム受益者選定システム」のこと。各家庭の経済状態を「1から6」までの階層に格付けしたもの。各家族が国家に納めるべき税金の額によって社会階層が決まってくる。もっとも社会経済状態が低いのが「階層1」(22.3%)で、「階層2」(41.2%)が多数を占める。「階層3」は中の下の階層、都会に住む大多数の家族が「2と3」である。「階層4」は中流階級に入り、プロフェッショナルな職業についている人や商人である。「階層5」(1.9%)は中流の上、「階層6」(1.2%)は、邸宅や豪華マンションに住み数台の車を所有し、持てるすべてのものを持つエリートである。証明書が発行され、それによって公共料金の額(階層1は免除)とか、大学授業料が決まる仕組み。RASの家庭は「階層1」、カルビンの家は「2か3」でしょうか。コロンビアが階層によって分断された社会であることが、監督の「政治抜きに映画は作れない」という発言になっていると思います。
ダビ・トゥルエバの新作*ラテンビート2014 最終回 ― 2014年11月21日 17:24
★本作がアカデミー賞スペイン代表作品に決定したこと、このスペイン的色彩の濃い映画がノミネーション5作品まで辿りつける可能性は少ないこと、10月半ばロスアンゼルスで開催された「スペイン映画祭」のオープニング作品に選ばれ、トゥルエバ監督がプロモーションを兼ねてロス入りしたことなどはお知らせしました。監督の親戚が住んでいるロスでは、今ではアメリカ人になっている大勢の従兄弟たちが応援に馳せつけ嵐のようなベソとハグを受けたようです。1915年、カリフォルニアの炭鉱で一旗揚げようと渡米したエウロヒオおじさんの三世にあたる子孫かな、何しろ1世紀前ですから。アメリカ陸軍に志願、そこで学んだ理容の技術を活かして、除隊後ロスで理髪店を開業した。
★ラテンビートのチラシによると、松竹メディア事情部提供とあるので、公開またはDVD発売が検討されているのだろうか。間もなく公開される『スガラムルディの魔女』他の配給会社、来年には邦題は未定だが、ガベ・イバニェスのSF“Automata”を公開してくれる。アントニオ・バンデラスが主役ということで「ゴヤ栄誉賞2015」やサンセバスチャン映画祭の記事で既にご紹介しています。
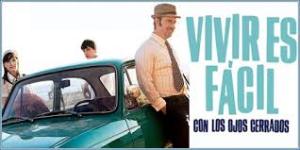
★東京会場では上映のなかった唯一の作品、横浜会場のチケットは完売でした。当日の朝、予約を入れなかったら危うく涙の帰宅になるところでした。涙は館内で流さないといけません。こんなに素敵なハビエル・カマラを見たことなかった。ゴヤ賞主演男優賞の名に恥じない演技に感動、「ノスタルジック」とか「メランコリー」とか、前作“Madrid 1987”(2011)をより高く評価する評者もいるようですが、カマラの演技を貶す人は見当たりませんでした。
*“Vivir es fácil con los
ojos cerrados”(“Living is Easy With Eyes Closed”)*
製作:フェルナンド・トゥルエバ P.C. S.A.
(クリスティナ・ウエテ フェルナンデス=マキエイラ)ゴヤ賞作品賞受賞
監督・脚本:ダビ・トゥルエバ (ゴヤ賞監督賞・オリジナル脚本賞受賞)
撮影:ダニエル・ビラル
音楽:パット・メセニー チャーリー・ヘイデン(同オリジナル作曲賞受賞)
*ゴヤ賞受賞:主演男優賞(ハビエル・カマラ)、新人女優賞(ナタリア・デ・モリーナ)
*同ノミネート:衣装デザイン賞(ララ・ウエテ)
キャスト:ハビエル・カマラ(アントニオ)、ナタリア・デ・モリーナ(ベレン)、フランセスク・コロメル(フアンホ)、ホルヘ・サンス(フアンホ父)、アリアドナ・ヒル(フアンホ母)、ロヘリオ・フェルナンデス(ブルーノ)、ラモン・フォンセレ(ブルーノの父ラモン)他
*ザ・ビートルズのジョン・レノン、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、ポール・マッカートニーの記録映像で登場。
データ:スペイン、スペイン語、2013、コメディ、108分、撮影地:アルメリア県(アンダルシア州) 2013年10月31日スペイン公開、他
*サンセバスチャン映画祭2013コンペティション正式出品。
*パーム・スプリングス映画祭2014「ラテン映画賞」受賞。カリフォルニア州のパーム・スプリングス市で1月に開催される国際映画祭。アマ・エスカランテの『エリ』と賞を分かち合いました。
プロット:1966年、ジョン・レノンが映画撮影のためアルメリアにやって来る。ビートルズの歌を教材に英語を教えていた高校教師のアントニオは、自分のヒーローに会おうと決心、休暇をとって短い旅に出る。道中何かから逃げてきたらしい若い娘ベレン、16歳のミニ家出少年フアンホが仲間に加わり、1966年のアルメリアは3人にとって生涯忘れることができない季節になる。
無名の人が物語の主人公になった
A: ハビエル・カマラが扮した英語教師アントニオにはモデルがいる。監督によると、2006年のことだがアドルフォ・イグレシアスという記者が書いた「カルタヘナの英語教師」という記事を目にした。フアン・カリオンという美声の英語教師がビートルズの歌を使って英語を教えている。そしてジョン・レノンが映画撮影のためアルメリアにやって来るというので会いに出掛けた、という記事です。
B: モデルといっても、この記事に着想を得たというだけで、殆どフィクションですよね。
A: 勿論、登場人物の造形段階では取材していない。トゥルエバは確かな情報を収集して、それを土台に伝記映画を作ろうとしたわけではありませんからね。しかし撮影現場にはカリオン氏も現れて当時の状況などを若い出演者にサジェスチョンしたようです。
B: ゴヤ賞授賞式には監督の隣りに座っていました。オリジナル脚本賞は「あなたのものです」と挨拶していた。

A: ビートルズ・ファンなら題名を見て、ジョン・レノンの永遠に残る「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」(1967)から取られたことが分かります。ビートルズ映画を撮った監督リチャード・レスターの『ジョン・レノンの僕の戦争』*撮影のため、レノンは実際にアルメリアに滞在していた。
B: ライヴ・ツアーを一時中止していて、精神的にちょっと参っていた時期ですね。オノ・ヨーコと出会うのは同年11月です。しかしこれはレノンの伝記映画でもない。
A: 監督は、フアン・カリオンの伝記映画でもレノンのでもない、或る時代の、1960年代のスペインの「肖像画」を描こうとした。つまり、無名の人を物語の主人公にしたわけです。時代は1966年、フランコ体制も26年が過ぎた灰色のスペインだった。アルメリアの人々は農業と漁業に従事して生活は貧しく、自由に憧れる若者にとってビートルズはまさにヒーロー、希望の星でもあった。
B: そこに先輩監督フアン・アントニオ・バルデムがフランコ没後の第1作として撮ったコメディ“El puente”(1977)**がひらめいた。
A: 主役のアルフレッド・ランダが夏季休暇を利用してバイクリードからトレモリノスへ旅をする話で、一種のロード・ムービーでした。そこでカリオン氏のカルタヘナ(ムルシア州)をアルバセテ(カスティリャ=ラマンチャ州)に変更してオリジナル脚本を書いたというわけです。
B: 舞台となるアルメリア(県都)もかれこれ40年も経てば様変わりしていて、60年代を再現するのは難しかったそうですね。
A: ロケ地探しには苦労したと語っています。アルメリア県内の内陸部のタベルナス、ロダルキラル、地中海沿いの「カボ・デ・ガタ」などで撮影は行われた。
*原題“How I Won the
War”(1967英)、パトリック・ライアンの同名小説の映画化。未公開だったがビデオが発売されたときに付けられた邦題(廃盤)。戦争の愚かさをブラック・ユーモアで笑い飛ばした映画で、本作のメタファーになっている。
**直訳は「橋」ですが、休日に挟まれた平日に「橋」をかけて連休にする意味もあり、ここでは「夏季休暇」がベターかも。
アントニオとレノンは“Help”と叫んでいた!
A: 1966年のスペインでは、まだ英語が話せる人はほんの少数派、文部省の人たちは、スペイン語という先祖伝来の言葉があるのに英語を学ぶなんて余計なこと、と傲慢にも全く英語教育に気を配らなかったそうです。
B: だから地方の一介の英語教師がビートルズの歌詞を使って子供に英語を教えているのは画期的なことだった。更にビートルズたちがこの歌詞の中に何を込めて歌っているのか知ることはもっと重要だった。
A: 主人公アントニオは、肩に背負っていた重い荷物は取りあえずここに下ろして、自分を解放するための旅に出たかった。レノンもロック・スターの頂点を極めたが孤独に苦しんでいて「ヘルプ!」と叫んでいた。
B: アントニオも村のバルの主人ラモンも、世界から遅れた古くさいスペイン、力ずくで子どもを躾けようとしたり、長髪はなよなよしたゲイだから短くしろとか、そういう子供っぽいスペインに変化が必要と考えていた人たちです。
A: フアンホの父親は旧弊な父権的な人ではありませんが、規律を重んじるタイプですね。多分実のお父さんが投影されていると思います。監督は8人兄弟姉妹の末っ子、母親に甘やかされて7歳まで学校に行かなかった話は有名。父親はタイプライターの訪問販売業を営み、そのタイプライターで幼少時から物を書いていたという早熟な子供だった。
B: 『ふたりのアトリエ~ある彫刻家とモデル』(ラテンビート2013上映)で初来日したフェルナンド・トゥルエバ監督は実のお兄さん。

A: この映画で彫刻家のモデルになったのが1992年交通事故のため42歳で亡くなった長兄マキシモです。フアンホのモデルは、16歳のとき長髪を切るのを拒絶して3日間家出したお兄さんだと語っています。映画では一番上に見えましたから、そうするとマキシモ兄さんかもしれない。
(来日Q&A記事はコチラ⇒2013年10月31日)
B: いずれにしてもホルヘ・サンス扮する父親のモデルは実父かもしれない。
A: 彼は作中では子沢山でしたが、実生活でも『バレンチナ物語』で共演したパロマ・ゴメスと結婚、パパになったと報じられましたが、早くも結婚を解消して、現在はジャーナリストのオルガ・マルセと親密交際中、妊娠説も流れたが否定しています(笑)。
ジョン・レノンが見たら気に入った?
A: この奇妙なトリオの設定は、実際にはあり得ないですが、センチメンタルなロード・ムービーだと酷評するほどじゃない。三人とも暗い現実からか、先が見えない未来からか分からないが、何かから逃げてきています。しかし他人を思いやることが必要だと分かっている。友情が芽生え、やがてアモールになっていく。
B: 声高なセリフはありませんが、何故か胸を打つ。小さい物語ですが、ホロ苦いユーモア、優しさ、リリシズムに溢れている。
A: それに複雑に入り組んだ感情の動きも見逃せない。これが監督がずっと求めてきたことなんだと思います。実らないと思うが、アントニオはベレンがきっと好きになってしまったんだ、と観客が思った通りになる(笑)。
B: メランコリー・コメディと言う人も、おセンチすぎると感じる人もいるでしょうが、こういうオハナシはいい。厳しい現実を前にして感性が鈍感な人物、力強さと優しさを併せ持つ人物を、よく調和させている。
A: アントニオの人格にはレノンと似ているところがあって、それが流れ込んでいる。
B: 村のバルの主人も印象に残る。一見すると負け組に見えるが実はそうではない。絶望しているわけでも人生を諦めているわけではない。
A: しかし、待つだけの人生は辛いとね。アクションが必要なんだと考えている。部分的にモタモタするところもあるが、最後のほうで一気にアントニオの感情が爆発する。観客は思わず小さく快哉を叫ぶ。モタモタは雲散霧消して映画館を出られる。
B: 無知で閉鎖的なスペインをぶち壊す、フアンホの世代が古くさいスペインを変えていくことが暗示される。
A: ジャンルはコメディということですが、そういう区分けに収まらない映画です。仮にレノンが生きていて見たら、きっと気に入るだろう、という評は最大の褒め言葉です。
B: 勿論、パット・メセニーのギター、チャーリー・ヘイデンのゆったりしたコントラバスの音色、二人のミュージシャンの功績も大きい。ヘイデンは今夏に76歳で惜しくも鬼籍入りしてしまいました。
A: 温かい音色、叙情性のある旋律、彼のライフスタイルを慕うファンは多いのではないですか。
人生は本当に長い、カリオン氏に捧げたいゴヤの胸像
B: いままで10回もゴヤ賞がノミネートに終わったのには何が足りなかったのか、今回はその理由を掴んだと思いますか。
A: 多分ね。暴力や皮肉が描かれる映画に受賞が優先されることが時々あるが、自分はそういう映画を作りたいとは思わない。でも今まで貰えなかったことを一度も悪く解釈したことはないと語っている。人生は本当に長いと思う。ある日、誰かが近寄ってきて、「ダビ、昨夜ホテルのテレビで君の映画を見たよ、とっても感動した」と言ってくれたらいい。そういう映画を作りたい。
B: まさに本作はそういう映画でした。
A: 本作のモデルになったフアン・カリオンは既に90歳を越している。「彼に負うところが多かった、彼が映画を気に入ってくれて本当に嬉しかった」とインタビューに応えていました。

(監督とカリオン氏 イビサにて)
(以下の監督・キャスト紹介は主に2014年1月31日の記事に加筆訂正を加えて再構成したもの)
*監督キャリア紹介*
ダビ・トゥルエバ David
Rodriguez Trueba :1969年マドリード生れ、監督・脚本家・作家・俳優・ジャーナリスト。マドリード・コンプルテンセ大学ジャーナリズム情報科学科卒業。1992年米国に渡り「アメリカン・フィルム・インスティチュート」脚本科に入学。大学在学中に脚本を書き始め、エミリオ・マルティネス・ラサロに認められる。後に彼の『我が生涯最悪の年』(1994)*の脚本を書き、ゴヤ賞1995脚本賞にノミネートされている。
*ゴヤ賞は「10回ノミネートで無冠」のレコード保持者でしたが、11回目で宿願を果たしました。「永遠に二番手」と囁かれていましたけれど。現在は小説の新作を準備中、映画は目下予定はないようですが、本作の成功で資金が集まれば、次回作も期待できる。
*“Los peores anos de nuestravida”日本スペイン協会創立40周年記念を祝して開催された「スペイン映画祭1997」で上映されたときの邦題。フアンホの父親役ホルヘ・サンスと母親役アリアドナ・ヒルが、ここでは若い恋人役を演じている。彼女はトゥルエバ夫人だったが離婚、2009年にヴィゴ・モーテンセンと再婚した。
◎1991 “Felicidades, Alberti”(TV映画)の脚本家として出発。
◎1993 “El peor programa de la semana”(TVシリーズ5話)で監督デビュー。
◎1996 “La buena vida”(長編映画デビュー作)、ゴヤ賞1997新人監督賞・脚本賞にノミネートされた他、カルロヴィー・ヴァリー映画祭特別審査員賞、トゥリア賞(第1作監督賞)受賞。
◎2003 “Soldados de Salamina”、ハビエル・セルカスの同名小説『サラミスの兵士たち』(翻訳題名)の映画化、オスカー賞2004スペイン代表作に選ばれるも最終候補に残れなかった。またコペンハーゲン映画祭脚本賞、トゥリア賞(スペイン映画部門)を受賞、ゴヤ賞はノミネートに終わる。
◎2006“Bienvenido a casa”
◎2007“Rafael Azcona, oficio de
guionista”(TVドキュメンタリー)、脚本の恩師であり、ダビのシナリオ作家としての才能を開花させたと言われる名脚本家アスコナの業績を辿ったドキュメンタリー、翌年2月に鬼籍入りした。
◎2011“Madrid, 1987”、主役のホセ・サクリスタンにフォルケ賞をもたらして映画。
◎2013“Vivir es
fácil con los ojos cerrados”(省略
*他、短編、脚本、俳優出演多数。兄トゥルエバの『あなたに逢いたくて』(95)や『美しき虜』(98)、アレックス・デ・ラ・イグレシアの『ぺルディータ・ドゥランゴ』(97)の脚本に参加している。

(ゴヤ賞受賞式でのトゥルエバ監督)
*キャスト紹介*
★ハビエル・カマラJavier Camara Rodriguz:1967年、ラ・リオハ生れ、俳優、監督。高等学校では演劇クラブに所属、ログローニョの演劇学校で学んだ後、RESAD*で本格的に演技を学ぶためマドリードに移住する。かたわら映画にも興味を抱くようになる。
*1991年、ロぺ・デ・ベガの『オルメドの騎士』で初舞台を踏む。1993年、フェルナンド・コロモの“Rosa Rosae”で映画デビュー、同監督の“Alegre ma non troppo”(94)、“ESO”(95)などコロモ監督の映画に出演する。並行してTVドラ・シリーズにも出演、日本で知られるようになったのは、1998年、サンチャゴ・セグラの監督デビュー作『トレンテ』シリーズの第1作目あたりから。その後、フリオ・メデムの『ルシアとSEX』、アルモドバルの『バッド・エデュケーション』、イサベル・コイシェの『あなたになら言える秘密のこと』、アグスティン・ディアス・ヤネスの『アラトリステ』などで多くのファンの心を掴んでいる。2013年ラテンビート上映の『アイム・ソー・エキサイテッド』のゲスト出演とプロモーションを兼ねて来日した。

(ハビエル・カマラ ゴヤ賞ガラにて)
*以下はゴヤ賞ノミネート作品だけ列挙します。
1)1998 “Torrente, el brazo tonto
de la ley” 監督:サンチャゴ・セグラ、新人男優賞
2)2002 『トーク・トゥ・ハー』監督:ペドロ・アルモドバル、主演男優賞
3)2003 “Torremolinos 73”監督:パブロ・ベルヘル、主演男優賞
4)2005 『あなたになら言える秘密のこと』監督:イサベル・コイシェ、助演男優賞
5)2008 『シェフズ・スペシャル』監督:ナチョ・G・ベリジャ、主演男優賞
6)2013 “Vivir es
fácil con los ojos cerrados”主演男優賞を受賞
◎6回ノミネート、トゥルエバ監督との合言葉は、「僕たち、1個もゴヤを持ってない」でしたが、二人仲良くゴヤの胸像を手にすることができました。
*RESAD:Real Escuela Superior de Arte Dramatico の略称、1831年、フェルナンド7世の王妃マリア・クリスティナ(・デ・ボルボン)が創設した演劇の伝統校。現在活躍中の俳優では、エドゥアルド・ノリエガ、ブランカ・ポルテージョ、バルバラ・レニーなどが卒業生。
★ナタリア・デ・モリーナ Natalía de molina : リナレス生れ(アンダルシアの観光地ハエン近郊)、グラナダで育った(正確な生年がIMDbでもアップされていないが、2013年11月に受けたインタビューで23歳と答えているので1990年ごろか)。俳優・歌手・バレエダンサー(短編で共演しているセリナ・デ・モリーナとは姉妹)。マラガ高等演劇芸術学校で2年間ミュージカルの基礎を学んだ後、マドリードに出て、演劇学校ガレージ・リュミエールGaraje Lumiere やスタジオ・コラッサEstudio Corazzaで演技を学ぶ。長編第1作でゴヤ新人女優賞にノミネートされたシンデレラ・ガール。インタビュアーから「スター誕生ですね」と言われて、「そうなれば嬉しい」と答えた通り、新人女優賞に輝いた。
*本作では独身で妊娠してしまった21歳のマラゲーニャ役、アンダルシア訛りが出来ることが出演の幸運を呼び込んだ。「撮影中はまるで一つの家族のようだった」と語っていたナタリア、ナタリー・ポートマンに似ていると言われるとのこと。彼女も踊れて演技できるから「とても光栄に思っている」由。

(シンデレラ・ガールのナタリア・デ・モリーナ)
★フランセスク・コロメルFrancesc Colomer (フアンホ役) :1997年、バルセロナ生れ。本作では実年齢を演じている。アグスティ・ビリャロンガの『ブラック・ブレッド』(2011)の少年アンドレウで既にゴヤ賞新人男優賞受賞を果たしている。他にダニ・デ・ラ・オルデンのカタルーニャ語のコメディ“Barcelona, nit d’estiu”(2013“Barcelona, noche de
verano”スペイン語題)で主役を演じている。3年ですっかり若者になりましたが、あの独特の目ですぐ分かります。
*フアンホは、長髪を禁じる父親に反抗して3日間のミニ家出をした、当時16歳だった監督の兄弟の一人がモデルになっている。
★ラモン・フォンセレRamon Fontsere(ラモン役):1956年バルセロナ生れ、俳優。ダビ・トゥルエバの“Soldados de Salamina”でファランヘ党員の詩人サンチェス・マサスを演じた。同“Madrid, 1987”、マル・コルのカタルーニャ映画“Tres dies amb
la familia”(2009“Tres dias con la familia”スペイン語題)などが代表作。
*本作では村のバルの主人になり、キャスト陣の中でもその演技は際立っていた。人生がラモンに与え、そして奪っていったものが何であるか知っている、着実な人生観をもった人物。彼に魅了されずにいるのは不可能です。

(左から、演技が光ったラモン・フォンセレとハビエル・カマラ)
★ロヘリオ・フェルナンデスRogelio Fernandez(ブルーノ役):本作でデビュー。ラモンの小児麻痺の息子を演じた。
★ホルヘ・サンスJorge Sanz(フアンホの父親役: 1969年、マドリードうまれ、映画・舞台・テレビ俳優。ペドロ・マソの“La miel”(79)に9歳でデビュー、1982年アントニオ・ベタンコールがラモン・センデルの小説を映画化した『バレンチナ物語』の名子役ぶりが話題になる。つづくフェルナンド・フェルナン・ゴメスの“Mambrú se fue a la guerra”(85)、フェルナンド・トゥルエバの“El año de las
luces”(86)でマリベル・ベルドゥと共演、子役から大人へと無事に変身できた。ビセンテ・アランダの『アマンテス 愛人』(91)と『リベリタリアス自由への道』(96)、兄トゥルエバの『ベルエポック』(92)など、ヒット作に次々と出演した。『バレンチナ物語』で共演したパロマ・ゴメスと4~5年前に再会して結婚、息子も生れたが、互いに合意して離婚した。映画では「プラトニックな恋に終わった二人だが、実人生では恋を成就できた」と報道されたのに、束の間に終わった。
*最近の舞台出演は、映画“Orquesta Club
Virginia”(92)の劇場版にアントニオ・レシネス、ビクトル・エリアス、マカレナ・ゴメス等と出演している。

(左から撮影中のホルヘ・サンス、ロヘリオ・フェルナンデス、監督)
★アリアドナ・ヒルAriadna Gil(フアンホの母親役):1969年、バルセロナ生れ、映画・舞台女優、テレビ出演多数。ビガス・ルナの“Lola”(86)で映画デビュー、代表作にオスカー賞を受賞したフェルナンド・トゥルエバの『ベルエポック』(92)でゴヤ賞主演女優賞を受賞した。エミリオ・マルティネス・ラサロの『我が生涯最悪の年』、“Soldados de Salamina”、ギジェルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』(07)、フェルナンド・トゥルエバの『泥棒と踊り子』(09)など。アグスティン・ディアス・ヤネスの『アラトリステ』(06)で共演したヴィゴ・モーテンセンと2009年結婚した。他にアルゼンチンの「コンドル・デ・プラタ」女優賞を受賞した“Nueces para el amor”(01)がある。

(結婚5周年のお祝いができたヴィゴ・モーテンセンとアリアドナ・ヒル)
★トゥルエバ兄弟の作品のほとんどを手掛けている製作者のクリスティナ・ウエテ(兄トルエバ夫人)については、コチラ⇒2014年1月12日 / 2月13日
第1回ガルシア・マルケス短編小説賞にギジェルモ・マルティネス ― 2014年11月24日 18:17
★新しい文学賞「ガルシア・マルケス短編小説賞」*の第1回受賞者が、アルゼンチンの小説家で数学者のギジェルモ・マルティネスの“Una felicidad repulsiva”(2013、プラネタ社、アルゼンチン)に決定、去る11月21日、コロンビアの首都ボゴタで授賞式がありました。コロンビアのフアン・マヌエル・サントス大統領よりトロフィーが手渡されました。ガルシア・マルケスのコロンビアでの国葬に拘った少々目立ちたがり屋の大統領ですね。
*Premio
Hispanoamericano de Cuento Gabriel Garcia Marquezが正式名称、今年4月17日にメキシコ市の自宅で亡くなった『百年の孤独』の著者、コロンビアのノーベル賞作家に因んだ文学賞。ラテンアメリカ諸国とスペインで出版された短編小説に与えられる。コロンビア文化省・国立図書館、及びスペインのセルバンテス協会が主催、賞金は10万ドル(8万ユーロ)。

(フアン・マヌエル・サントス大統領と受賞者ギジェルモ・マルティネス)
★ガルシア・マルケスは1947年の“La tercera resignación”の出版以来、40作以上の短編を書いていたそうで、短編というのは「日常生活での飾らない人間の本質に手を加えずに描くことができるジャンル」と語っていた由。短編は重要だと分かっていても売れないから、出版社はどうしても敬遠する。その短編に光を当てた賞がやっと登場しました。選考委員は、委員長にスペインの作家クリスティナ・フェルナンデス・クバス、コロンビアの風刺作家でジャーナリストのアントニオ・カバジェロ、エルサルバドルのオラシオ・カステジャノス・モヤ、アルゼンチンのメンポ・ジアルディネッリ、メキシコのイグナシオ・パディジャの5人。
★最終選考5作品に残った作家と作品:
カロリーナ・ブルック(アルゼンチン)“Las otras”
エクトル・マンハレス(メキシコ)“Anoch dormí en la montaña”
オスカル・シパン(西)“Quisiera tener la voz de Leonard Cohen para pedirte que
te marcharas”
アレハンドロ・サンブラ(チリ)“Mis documentos”
ギジェルモ・マルティネス 省略
*以上は、ラテンアメリカ諸国、スペインで刊行された123作品から選ばれた5作品。
★受賞作“Una felicidad repulsiva”は、2~3ページの短いものから50ページを越える11作で構成されている。審査委員によると、「思慮の錯乱、偶然がなせる不遇、悪夢を引き離して、繊細なスタイルに溢れている」。また「確固として繊細、そして調和がとれていて、このジャンルを見事に手中にしている」短編集、「日常生活から端を発した不条理なもの、恐怖や幻想性、予期しないものに完璧な手さばきで特殊な視点を反映させた作品」ということです。
*ギジェルモ・マルティネスによると、10年間に書きためていた作品で、共通しているのはサスペンスものが多い。「日常生活を描いた物語ですが、ある瞬間に忍びよる不運、悪夢、狂気、ふっと過ぎっていく恐怖」が描かれていると語っている。短編集には、トロツキーの最後の一日について書いたものや、光に当てないで息子を育てている過保護な母親の話、などが入っている。

★ギジェルモ・マルティネス Guillermo Martínez:1962年、ブエノスアイレス州バイア・ブランカ生れ、作家、数学者、文芸評論家。14歳のときから書きはじめたという早熟な少年だが、「私の最初の文学の師は、最近亡くなった父親です。私たち兄弟に本を読むことの大切さや楽しさを教えてくれたから」とインタビューに答えています。
*1984年、国立スール大学数学科卒、1992年、ブエノスアイレス大学で数理論理学の博士号取得、国立学術技術研究審議会の奨学金を得て、オックスフォード大学大学院に留学した。2002年、アイオワ大学の国際作家プログラムに参加した。アルゼンチンの最優秀小説家5人の1人に選ばれている(2004~07年)。

*主な小説と短編集*
1989“Infielno grande”短編集(レガサ社、アルゼンチン/2001、デスティノ社、西)
1993“Acerca de Roderer” (プラネタ社、アルゼンチン/1996、デスティノ社、西)
1998“La mujer del maestro”(プラネタ社、アルゼンチン/1999、デスティノ社、西)
2003“Crímenes imperceptibles”(プラネタ社、アルゼンチン/2004、デスティノ社、西
“Los crímenes de Oxford”に改題)
2007“La muerte lenta de Luciana B”(プラネタ社、アルゼンチン/同、デスティノ社、西)
『ルシアナ・Bの緩慢なる死』(2006、扶桑社、和泉圭亮訳)
2011“Yo también tuve una novia bisexual”(プラネタ社、アルゼンチン)
2013“Una felicidad repulsiva” 短編集(プラネタ社、アルゼンチン)
*他に文芸評論“Borges
y la matematica”(2003)、他
★アレックス・デ・ラ・イグレシアの『オックスフォード連続殺人』(08)を見た人でも、オリジナル・タイトルがギジェルモ・マルティネスの“Crímenes imperceptibles”だというのは、推理小説ファン以外は御存じないかもしれない。上記したように2004年にスペインのデスティノDestino社から出版されたとき“Los crímenes de Oxford”と改題され、映画もこちらを採用、日本で翻訳されたときの邦題も『オックスフォード連続殺人』(06、扶桑社、和泉圭亮訳)で出版されました。本作は現在37の言語に翻訳されている本格的なミステリー小説。
(写真下は映画のポスターから)

(イライジャ・ウッド、レオノル・ワトリング、ジュリー・コックス、ジョン・ハート)
第1回フェニックス賞に『金の鳥籠』が受賞 ― 2014年11月26日 10:16

★イベロアメリカの「オスカー賞」という触れ込みで、新しい映画賞「Los
Premios Fénix」が誕生しました。去る10月31日、メキシコシティの「テアトロ・デ・ラ・シウダ」で、第1回授賞式が開催され、監督、製作者、俳優など大勢のラテンアメリカやスペインのシネアストが集いました。第1回の受賞者は『金の鳥籠』、ディエゴ・ケマダ≂ディエス監督のデビュー作でした。本作は劇場未公開作品ですが、「難民映画祭2014」で東京・札幌・西宮で上映されました。

(大賞を手中にしたディエゴ・ケマダ≂ディエスと出演者たち)

(『ブランカニエベス』の憎しみを水に流して抱擁するベルドゥとヒメネス・カチョ)
*主な受賞作品・受賞者*
◎フェニックス賞:『金の鳥籠』“La jaula de oro”ディエゴ・ケマダ≂ディエス(メキシコ)
◎最優秀監督・脚本賞:アマ・エスカランテ『エリ』“Heli”(メキシコ)ダブル受賞

(両手に花ならぬトロフィーのアマ・エスカランテ)
◎最優秀男優賞:ヴィゴ・モーテンセン“Jauja”(米国・アルゼンチン)

◎最優秀女優賞:レアンドラ・レアル“O lobo atras da porta”(ブラジル)

◎最優秀撮影賞:フリアン・アペステギア“El Ardor”(アルゼンチン)
★フェニックス栄誉賞は、メキシコのアルトゥーロ・リプステイン監督(1943生れ)。今年鬼籍入りした友人ガルシア・マルケスの思い出を語った。まだ無名だったリプステインのデビュー作『死の時』(“Tiempo de morir”1966)にガルシア・マルケスが脚本家として参加したこと、半世紀に及ぶ映画人生で「このフェニックス賞のトロフィーは、私の50年間の集大成」と壇上で述べた。
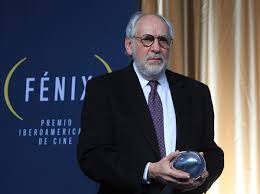
◎『金の鳥籠』はアリエル賞2014の受賞作品、コチラ⇒2014年6月5日
◎『エリ』はカンヌ映画祭2013の監督賞受賞作品、コチラ⇒2013年10月8日/11月23日
◎“Jauja”は、カンヌ映画祭2014 コチラ⇒2014年5月6日/5月27日
◎アルトゥーロ・リプステインとガルシア・マルケス コチラ⇒2014年4月27日
*俄かには信じがたい失踪殺害事件の全貌が明らかになったのは11月4日、親たちは信じられずにいたが、8日になってメキシコ検事総長の会見で追認された。犯人は麻薬組織に通じていたイグアラ市長夫妻とイグアラ市警察本部長というに及んでは開いた口がふさがらない。麻薬密売組織がらみということは最初から想定されていたようですが、全員殺害、遺体は古タイヤやゴミと一緒に焼却され、袋に入れられて川に流されたという。市長夫妻には12万ドルの報奨金が掛けられていた。何故麻薬組織の一味が選挙で市長に選出されたのか、何故師範学校の学生が標的になったのか、まったく謎だらけの事件だが、願わくば、どこか他の惑星で起こったことと思いたい。

(赤絨毯に一緒に現れたG.G.ベルナルと新恋人アリシー・ブラガ)
メキシコのカイ・パルランヘ監督の第1作は誘拐事件の実話 ― 2014年11月28日 21:40
★前回ゲレロ州イグアラ市で起きた師範学校生43名の拉致殺害事件の記事を書いたばかりですが、カイ・パルランヘのデビュー作“Espacio interior”(2012、メキシコ=スペイン合作)がやっとスペインで公開されました。1990年8月29日、建築家ボスコ・グティエレス・コルティナが実際に遭遇した拉致幽閉事件の恐ろしい実話から生れました。そんな昔の事件というなかれ、今でもメキシコでは誘拐事件は日常茶飯事、国家統計研究所のデータによると、2012年の誘拐は105,682人に上るという。この数字を信用するなら、毎日300人近い人が誘拐されていることになる。昨年のコントロール・リスクのレベルは世界トップであった。

(ポスターを背景にインタビューを受けるカイ・パルランヘ監督、バルセロナにて)
*“Espacio
interior”(Interior
Space)*
製作:Glorieta Films / Sin Sentido Films
監督・脚本:カイ・パルランヘ・テスマン
共同脚本:ピエール・ファヴロー・アルカサル、ビセンテ・レニェロ
撮影:フアン・ホセ・サラビア
音楽:ハビエル・ウンピエレスUmpierrez
美術:ディアナ・キロス
製作者:アレハンドラ・カルデナス、ラファエル・クエルボ、カルロス・コラル
データ:メキシコ=スペイン、スペイン語、2012年、89分、撮影地:メキシコシティ、プエブラ、プエルト・エスコンディド他、公開:メキシコ2013年7月/スペイン2014年11月
キャスト:クノ・ベッカー(ラサロ)、アナ・セラディリャ(妻マリア)、ヘラルド・タラセナ(テンソ)、エルナン・メンドサ(KDT)、ロシオ・ベルデホ(グレニャス)、マリナ・デ・タビラ(ホセファ)、フアン・カルロス・コロンボ(ドン・ペドロ)他
プロット:ラサロはある犯罪組織の手によって誘拐され、完全に外部から隔離された小部屋に閉じ込められる。家族の個人情報を明らかにせざるを得なくなり、深い絶望に陥る。檻のなかに幽閉され、家族が身代金を払わなければ殺害すると度々脅迫された。決して解放されることはないと思ったが、強い意思と精神力、揺るぎない信仰と誇り、人間らしい精神の本質を発揮する。
観客を誘拐する――1,5×3メートルの穴倉
★グティエレス・コルティナは、家族によって身代金が支払われるまで、1,5×3メートルの穴倉のような小部屋に幽閉された。白づくめの目だし帽を被った見張り番がドアの小窓から無言で水と食事を与えるだけ、意思の疎通は筆談でやり取りされた。時折り寛容になり国民の祝日にはウイスキーがふるまわれたという。結果的には身代金を支払わずに257日目に穴倉から脱出できた。カイ・パルランヘ監督がこの誘拐事件を知ったきっかけは偶然のことだった。

(1,5×3メートルの穴倉に横たわるラサロ)
★友人から建築学部設立のための設計図を録画して欲しい旨の要請があり引き受けた。著名な建築家ボスコ・グティエレス・コルティナを撮影して終了、完成したものを引き渡した。打ち上げパーティでワインのボトルが開けられると、グティエレスはかつて自分がうけた257日に及ぶ拉致幽閉の体験を語り始めた。「私は誘拐され、9か月後に脱出できたんです」と。この言葉が大袈裟でなく監督の人生を変えたというのだ。
信仰と希望――克服の物語
★建築家は敬虔なカトリック信者で朝のミサを欠かさなかった。1990年8月29日の朝も同じように妻と5人の子供たちに見送られて家を出た。すると武装した4人の男たちに取り囲まれ、あっという間に誘拐されたという。この映画は単なる誘拐脱出劇を描いたものではなく、制限された状況のなかで如何にして生き残るかを描いたものだ。この狭い穴倉に閉じ込められ、身代金の支払いをひたすら待つ。数日か過ぎると精神に異常をきたさないような闘いを始めた。
★理性を失わないよう、まず白い壁にデッサンを描き、筋肉が落ちないよう腕立て伏せのような腹筋運動を開始した。自分自身と信仰を見失わないよう何度もマントラつまり祈りや讃歌を繰り返した。だんだん見張り番も一緒に祈るようになったという。ここではストックホルム症候群の反対の現象が起きたのではないか。犯人が被害者と長く一緒にいることで同情や好意を抱くようになる。被害者である建築家の敬虔な信仰が犯人に感化を及ばしたのではないだろうか。冷酷な上層部の計画犯と下っ端の見張り番との意識の違いかもしれない。この映画は長い地獄の描写が中心だが、脱出時の最後のクライマックスも一つの見せ場だということです。

(壁一面に描かれたデッサンと筋肉運動をする主人公ラサロ)
映画に精神的な要素を盛り込むことが不可欠だ
★監督によると、映画は「価値あるものとは何かを伝え、大衆がそれを受け入れられるようにすべきだ」と主張する。「この映画は人を熟考に駆り立てる力をもっており、宗教を含めて精神的なものを重視している」。精神を重視した映画は観客の心を強く打つ。この映画を作ることで宗教を再発見したとも語っている。

(クノ・ベッカー、アナ・セラディリャ、監督)
★<閉じ込め>で真っ先に思いつく映画は、ロドリーゴ・コルテスの『リミット』(10)だが、参考になった映画は、アルフォンソ・キュアロンの『ゼロ・グラビティ』(13)、スピルバーグの『シンドラーのリスト』(93)、ジュリアン・シュナーベルの『潜水服は蝶の夢を見る』(07)などであった。この映画は誘拐された主人公の視点で語られ、観客を主人公の内面へと導いていくからだ。
★メキシコでは悪いニュースばかりで、悲しいことに国民は暴力に麻痺してしまっている。警察や行政機関の当局者にとって一番困難なのは、信頼すべき情報収集が不可能という現実だとパルランヘ監督。「政治に鈍感では映画は作れない」と語っていた『ロス・ホンゴス』のルイス・ナビア監督の言葉が思い起こされる。ただキュアロン、デル・トロ、イニャリトゥ、レイガーダス、エスカランテなどのお蔭で、作家性の強い映画も認められるようになってきた。資金作りは相変わらずだが、スペインからの資金も得られるようになったという。「映画祭で受賞することも重要だが、一番は配給会社が見つかって公開されること」だと。次回作のテーマは決まっていて先住民の女性が主人公、2015年初めにクランクインする。
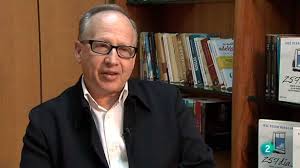
(現在では子供が9人になったという建築家ボスコ・グティエレス・コルティナ)
最近のコメント